秋の「なんとなくだるい」を解消!気を補ってやる気を取り戻す東洋医学的生活法【千葉県柏市の女性の悩み専門の鍼灸院】
2025-10-27 季節の養生法
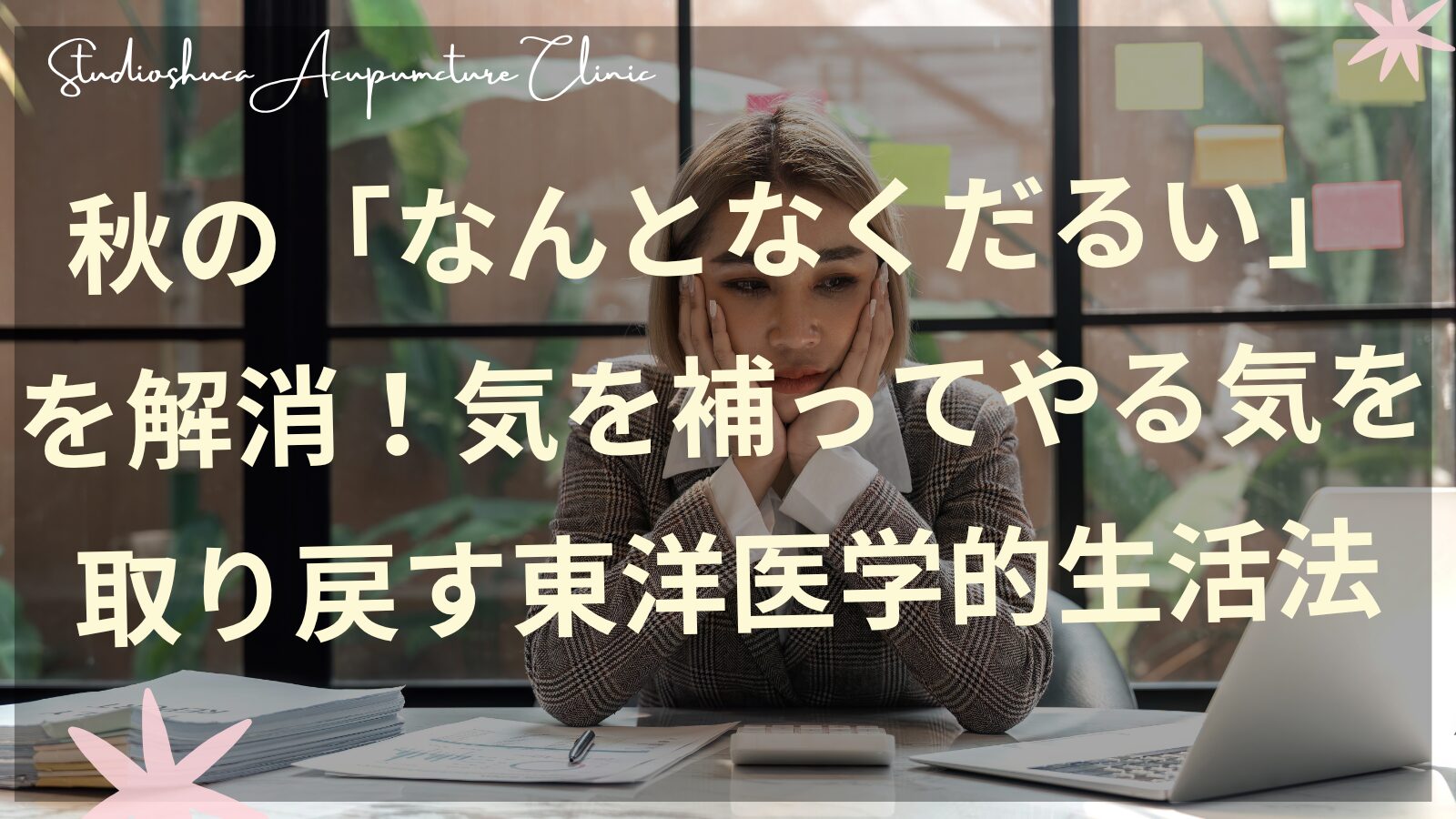
秋に「だるい」「やる気が出ない」と感じる理由
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
最近、こんなことはありませんか?
朝起きても体が重くて、やる気が起きない…。
仕事や家事をこなすだけで精一杯で、好きなことをする気力が湧かない…。
特に病気じゃないけど、なんとなくずっとだるい…。
秋になると、こういった「なんとなくだるい」という感覚に悩まされる方が本当に多いんです!
実はこれ、東洋医学では「気虚(ききょ)」という状態かもしれません。
気虚とは、体を動かすエネルギーである「気」が不足している状態のこと。
この記事では、秋の倦怠感やだるさの背景と、気を補ってやる気を取り戻す東洋医学的な生活法をお伝えします。
この記事を読むとわかること:
- 秋になると「だるい」「やる気が出ない」理由
- 東洋医学から見た「気虚」の考え方
- 気を補う食材とツボの具体的な活用法
- 日常生活で無理なく続けられる3つの習慣
この記事はこんな方におすすめ:
- 秋になると毎年疲れやすくなる30代・40代・50代の女性
- 「なんとなく不調」が続いているけれど、病院に行くほどではないと感じている方
- 自然な方法で体質改善をしたいと考えている方
それでは、一緒に見ていきましょう!
夏の疲れが抜けきらないまま秋を迎える
秋のだるさの大きな原因の一つが、夏の疲れの蓄積です。
東洋医学には「夏傷於暑、秋必痎瘧(かしょうおしょ、しゅうひつがいぎゃく)」という言葉があります。
これは「夏に暑さで傷つくと、秋に病む」という意味なんです。
夏の暑さや冷房の効いた室内との温度差で、私たちの体は想像以上にエネルギーを消耗しています。
特に女性は、冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎて胃腸を冷やしてしまいがち。
胃腸が弱ると、食べ物から気(エネルギー)を作り出す力が低下してしまうんです。
その結果、秋になっても夏の疲れが回復しきらず、「なんとなくだるい」状態が続いてしまいます。
秋の乾燥と寒暖差が体に与える影響
秋は気温の変化が激しい季節ですよね。
朝晩は冷え込むのに、日中は暖かい…そんな日が続きます。
この寒暖差が、自律神経に大きな負担をかけると言われています。
自律神経が乱れると、体温調節がうまくいかなくなり、疲れやすさやだるさを感じやすくなるんです。
また、秋は空気が乾燥する季節。
東洋医学では、秋は「肺」に影響が出やすい時期とされています。
肺は呼吸を通じて気を取り込む大切な臓器。
乾燥によって肺の働きが弱まると、気の生成がスムーズにいかなくなり、体全体のエネルギー不足につながると考えられています。
女性特有のホルモンバランスと気の消耗
女性は月経周期によって、定期的に血と気を消耗します。
東洋医学では「女子は血を以て本と為す」と言われるように、女性にとって血と気の関係はとても密接なんです。
特に30代・40代・50代の女性は、仕事や家事、育児、介護などで心身ともに忙しい時期。
ストレスも多く、気を消耗しやすい状況にあります。
月経前後や排卵期には特にエネルギーが必要なため、秋の季節的な影響と重なると、より一層「だるい」「やる気が出ない」と感じやすくなるんです。
一般的に「秋バテ」とも言われるこの状態。
東洋医学の視点から見ると、気の不足が大きく関わっていると考えられています。
秋の不調でお悩みの方へ
「なんとなくだるい」「やる気が出ない」という秋特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
東洋医学から見た「気虚」とは?
「気」とは体を動かすエネルギーのこと
東洋医学でいう「気」とは、一言で言えば体を動かすエネルギーのことです。
目には見えませんが、私たちの体の中を巡り、さまざまな働きをしていると考えられています。
気の主な働きには、次のようなものがあります:
- 推動作用:体を動かし、血液を巡らせる
- 温煦作用:体を温める
- 防御作用:外部からの邪気(病気の原因)を防ぐ
- 固摂作用:汗や尿などが過度に出るのを防ぐ
これらは東洋医学の伝統的な考え方です。
現代風に言い換えると、気は「免疫力」「代謝」「体温」「活力」などに関わるエネルギーとイメージしていただくとわかりやすいですね。
気虚の主な症状チェックリスト
あなたは今、気虚の状態かもしれません。
以下の症状に3つ以上当てはまる場合は、気が不足している可能性があります。
気虚セルフチェック:
- 朝起きるのがつらい、目覚めてもすぐに動けない
- 疲れやすく、少し動いただけで息切れする
- 声が小さくなった、話すのが面倒に感じる
- 食欲はあるけれど、食後に眠くなる
- 風邪をひきやすい、治りにくい
- 汗をかきやすい、または全く汗をかかない
- 顔色が悪い、くすんでいると言われる
- やる気が出ない、何もしたくない日が多い
いかがですか?
複数当てはまる方は、気を補う生活法を取り入れることで、体調が整っていく可能性があります。
ただし、個人の体質により感じ方には個人差がありますので、気になる症状がある場合は医療機関にご相談くださいね。
秋は「肺」と「脾」の働きが重要になる季節
東洋医学では、季節と臓腑(内臓)には深い関係があると考えられています。
秋に特に影響を受けやすいのが「肺」です。
肺は呼吸を司り、気を取り込む入口のような存在。
秋の乾燥した空気は、肺を傷つけやすく、その結果、気の生成が滞ると言われています。
また、「脾(ひ)」も重要な臓器です。
脾は胃腸の働きを表し、東洋医学では「気血生化の源」と呼ばれます。
つまり、気と血を作り出す工場のような役割を担っているんです。
夏に冷たいものを摂りすぎたり、不規則な食生活を続けたりすると、脾の働きが弱まります。
脾が弱ると、どんなに栄養のあるものを食べても、気に変換する力が低下してしまいます。
秋のだるさを解消するには、肺と脾の両方をケアすることが大切だと考えられています。
具体的なケア方法は、この後の「気を補う3つの生活法」でお伝えしますね!
気を補う3つの生活法
【生活法①】気を補う食材を意識的に取り入れる
東洋医学では、食べ物には「五味(ごみ)」という味の分類があり、それぞれが異なる働きをすると言われています。
気を補うのに特に効果的なのが「甘味」です。
甘味は脾(胃腸)の働きをサポートし、気を作り出す力を高めると考えられています。
ただし、ここでいう甘味は、砂糖たっぷりのお菓子ではありません!
自然な甘みを持つ、消化に優しい食材のことです。
気を補うと言われる食材リスト:
- 米・雑穀類:白米、玄米、もち米、あわ、ひえ
- いも類:さつまいも、じゃがいも、山芋、里芋
- 豆類:大豆、黒豆、小豆、豆腐、納豆
- きのこ類:しいたけ、まいたけ、しめじ
- 肉類:鶏肉、牛肉(少量)
- その他:かぼちゃ、栗、なつめ、はちみつ
これらの食材に共通するのは「甘味があり、温性で、消化に優しい」という特徴です。
具体的な献立例:
朝食:温かいご飯、味噌汁、納豆、卵焼き、焼き海苔
昼食:鶏肉ときのこの炊き込みご飯、さつまいもの煮物、ほうれん草のおひたし
夕食:白身魚の蒸し物、豆腐と山芋のスープ、玄米ご飯、温野菜
おやつ:焼き芋、栗、なつめ、温かいほうじ茶
食べ方のコツ:
- 温かい状態で食べる(冷たい料理は避ける)
- よく噛んで、ゆっくり食べる
- 腹八分目を心がける
- 朝食をしっかり食べる習慣をつける
胃腸に負担をかけず、じんわりと体を温めながらエネルギーを補給できる。
それが、気を補う食事の基本なんです。
関連記事:秋の乾燥から肌と体を守る!潤いを保つ東洋医学的ケア法
【生活法②】「補気のツボ」を優しく刺激する
自宅で簡単にできる気を補う方法の一つが、ツボ刺激です。
東洋医学では、体には「経絡(けいらく)」という気の通り道があり、その上に「経穴(けいけつ)」、いわゆるツボが点在していると考えられています。
気を補うと言われる代表的なツボを3つご紹介します。
①足三里(あしさんり)
場所:膝のお皿の外側から指4本分下がったところ。すねの骨の外側にあります。
伝統的な意味:足の陽明胃経に属し、胃腸の働きをサポートし、全身の気を補うと言われています。
刺激法:
- 親指でゆっくりと円を描くように押す
- 痛気持ちいい程度の強さで5秒×5回
- 朝起きた時や午後の疲れを感じた時に
②気海(きかい)
場所:おへそから指2本分下がったところ。
伝統的な意味:任脈に属し、「気の海」と呼ばれ、全身の気を巡らせると言われています。
刺激法:
- 手のひら全体を使って、時計回りに優しくさする
- 5分程度、ゆっくりと続ける
- お風呂上がりや就寝前がおすすめ
③関元(かんげん)
場所:おへそから指4本分下がったところ。
伝統的な意味:任脈に属し、女性の元気の源をサポートすると言われています。
刺激法:
- カイロや湯たんぽで温める(10~15分)
- 低温やけどに注意して、タオルを一枚挟む
- 生理前や疲れがたまっている時に特におすすめ
セルフケアの注意点:
- 清潔な手で、リラックスした状態で行う
- 強く押しすぎない(痛気持ちいい程度)
- 毎日続けることが大切
- 効果の感じ方には個人差があります
ツボ刺激は、専門的な施術ほどの刺激ではありませんが、日々のセルフケアとして取り入れることで、気の巡りをサポートできると言われています。
関連記事:季節の変わり目に揺らぐ自律神経を整える!五月病予防の東洋医学的アプローチ
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な気の補い方をご提案いたします。
気虚の体質改善について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
【生活法③】気を消耗しない生活リズムを作る
気を補うことも大切ですが、無駄に気を消耗しない工夫も同じくらい重要です。
東洋医学には「子午流注(しごるちゅう)」という考え方があります。
これは、時間帯ごとに活発になる経絡(気の通り道)が変わるという理論です。
この考え方を活かして、1日のリズムを整えることで、気を上手に補い、消耗を抑えることができると言われています。
朝の過ごし方(7時~9時)
7時~9時は「胃経」の時間。
胃の働きが最も活発になる時間帯です。
- 朝日を浴びて深呼吸(5分)
- 白湯や温かいお茶を飲む
- 温かい朝食をしっかり食べる
- 無理に早起きせず、十分な睡眠を確保する
朝食を抜くと、気を作り出す材料が不足してしまいます。
少量でもいいので、温かいものを食べる習慣をつけましょう。
日中の過ごし方(15時前後)
午後は気が下降し始める時間帯。
疲れやだるさを感じやすくなります。
- 15時前後に10~15分の仮眠(寝すぎない)
- デスクワークの合間に軽いストレッチ
- 一度に頑張りすぎず、こまめに休憩を取る
- 温かい飲み物で小休憩
仮眠は長すぎると逆効果。
10~15分の短い仮眠が、気をリフレッシュさせるのに最適と言われています。
夜の過ごし方(21時以降)
23時~1時は「胆経」、1時~3時は「肝経」の時間。
この時間帯に深い睡眠をとることが、気を作り出すのに重要とされています。
- 21時以降はスマホやPCの使用を控える
- ぬるめのお風呂(38~40度)にゆっくり浸かる
- 軽いストレッチやツボ押しでリラックス
- 23時までには就寝する
東洋医学では「気は夜に作られる」と考えられています。
質の良い睡眠が、翌日の気を充実させる基本なんです。
一般的に、睡眠不足が続くと免疫力が低下し、疲労が蓄積しやすいと言われています。
(参考:厚生労働省 e-ヘルスネット)
関連記事:妊活中の睡眠の質を高める方法!ホルモンバランスを整える夜の習慣
関連記事:秋バテを予防する体づくり!気の巡りを整える生活習慣とセルフケア
スタジオシュカの鍼灸でできる気虚のケア
鍼灸施術で期待される体験
スタジオシュカでは、東洋医学の伝統的な考え方に基づいた鍼灸施術を行っています。
気虚の状態に対して、鍼灸では「補法(ほほう)」という手技を用いることがあります。
補法とは、不足している気を補うようにアプローチする方法です。
鍼灸施術で期待される体験としては:
- 施術中のリラックス感、心地よさ
- 施術後の体の軽さ、温かさ
- 継続することで、疲れにくさを感じる方もいる
- 睡眠の質が整ってきたと感じる方もいる
ただし、効果の感じ方には個人差があります。
また、鍼灸は医療行為の代替ではありませんので、気になる症状がある場合は医療機関にもご相談ください。
お一人おひとりの体質に合わせたアプローチ
同じ「気虚」でも、人によってその原因や背景は異なります。
当院では、初回のカウンセリング時に、東洋医学の「四診(ししん)」という伝統的な診察法を用いて、あなたの体質を詳しくお伺いします。
四診とは:
- 望診:顔色、舌の状態などを見る
- 聞診:声の調子、呼吸音などを聞く
- 問診:症状、生活習慣などを詳しくお聞きする
- 切診:脈診、腹診などで体の状態を確かめる
これらの情報を総合的に判断し、あなたに最適なツボの組み合わせや施術方法をご提案します。
たとえば:
- 胃腸が弱いタイプの方には、脾胃を補うツボを中心に
- 呼吸器が弱いタイプの方には、肺を補うツボを中心に
- ストレスが多い方には、気の巡りを整えるツボも組み合わせる
一人ひとりの体質や生活スタイルに合わせた、オーダーメイドのケアをご提供しています。
セルフケアと鍼灸の併用がおすすめな理由
この記事でご紹介した「気を補う3つの生活法」は、ご自宅で今日から始められるセルフケアです。
一方、鍼灸施術は、より深い部分にアプローチし、体質を根本からサポートすることを目指します。
セルフケアと鍼灸の併用がおすすめな理由:
- セルフケアで日々の気を補い、鍼灸で体質の土台を整える
- 専門家のアドバイスで、自分に合った方法が見つかる
- 継続的なサポートで、季節の変わり目も安心
- 「未病を治す」東洋医学の予防的アプローチが実践できる
「未病を治す」とは、病気になる前の段階で体を整えるという東洋医学の大切な考え方です。
気虚も、放っておくとより深刻な不調につながることがあります。
早めのケアが、健やかな毎日を過ごすための鍵なんです。
関連記事:ストレスで乱れた自律神経をリセット!妊娠しやすい体づくりの呼吸法とセルフケア
関連記事:秋のウォーキングで血の巡りケア!東洋医学が勧める適度な運動法
まとめ – 秋の「なんとなくだるい」は気を補うことから
小さな習慣の積み重ねが大切
ここまで、秋の「なんとなくだるい」「やる気が出ない」という不調の背景と、気を補う3つの生活法をお伝えしてきました。
おさらいすると:
- 生活法①:気を補う食材を意識的に取り入れる
- 生活法②:「補気のツボ」を優しく刺激する
- 生活法③:気を消耗しない生活リズムを作る
どれも特別なことではなく、日常生活の中で少し意識を変えるだけで実践できることばかりです。
まずは一つだけ、できそうなことから始めてみてください。
たとえば:
- 朝食に温かいご飯と味噌汁を加える
- 寝る前に足三里のツボを押してみる
- 23時までに就寝する日を週に3日作る
小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化につながります。
気は一日で満タンになるものではありません。
毎日コツコツと、気を補い、消耗を減らす。
その繰り返しが、あなたの体を根本から変えていくんです。
関連記事:妊活中の疲れが取れない原因とは?体を労わる3つのケア方法
無理せず、自分のペースで続けていきましょう
「なんとなくだるい」状態が続くと、焦りや不安を感じることもあるかもしれません。
でも、大丈夫です。
あなたの体は、ちゃんと回復する力を持っています。
東洋医学では「気は生命の根本」と言われます。
気が満ちてくれば、自然とやる気も湧いてきます。
焦らず、無理せず、自分のペースで。
体の声に耳を傾けながら、毎日を大切に過ごしてくださいね。
秋の心地よい風を感じながら、ゆっくりと深呼吸。
あなたの中に眠っている気を、少しずつ目覚めさせていきましょう。
もし一人では続けるのが難しいな…と感じたら、いつでもスタジオシュカにご相談ください。
あなたの体質に合わせた、無理なく続けられる方法を一緒に考えていきましょう。
季節の変わり目も、笑顔で過ごせますように。
心から応援しています!
(参考:気象庁 – 季節予報)
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた気を補う生活プランを一緒に考えていきましょう。
※個人の体質により体験には個人差があります。
※施術効果を保証するものではありません。
※鍼灸は医療行為の代替ではありません。気になる症状がある場合は、医療機関にご相談ください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
