多嚢胞性卵巣でも妊娠をサポート!生活リズムとツボ押しで体を整える方法【松戸・流山・我孫子から10分の不妊鍼灸院】
2025-11-05 不妊治療
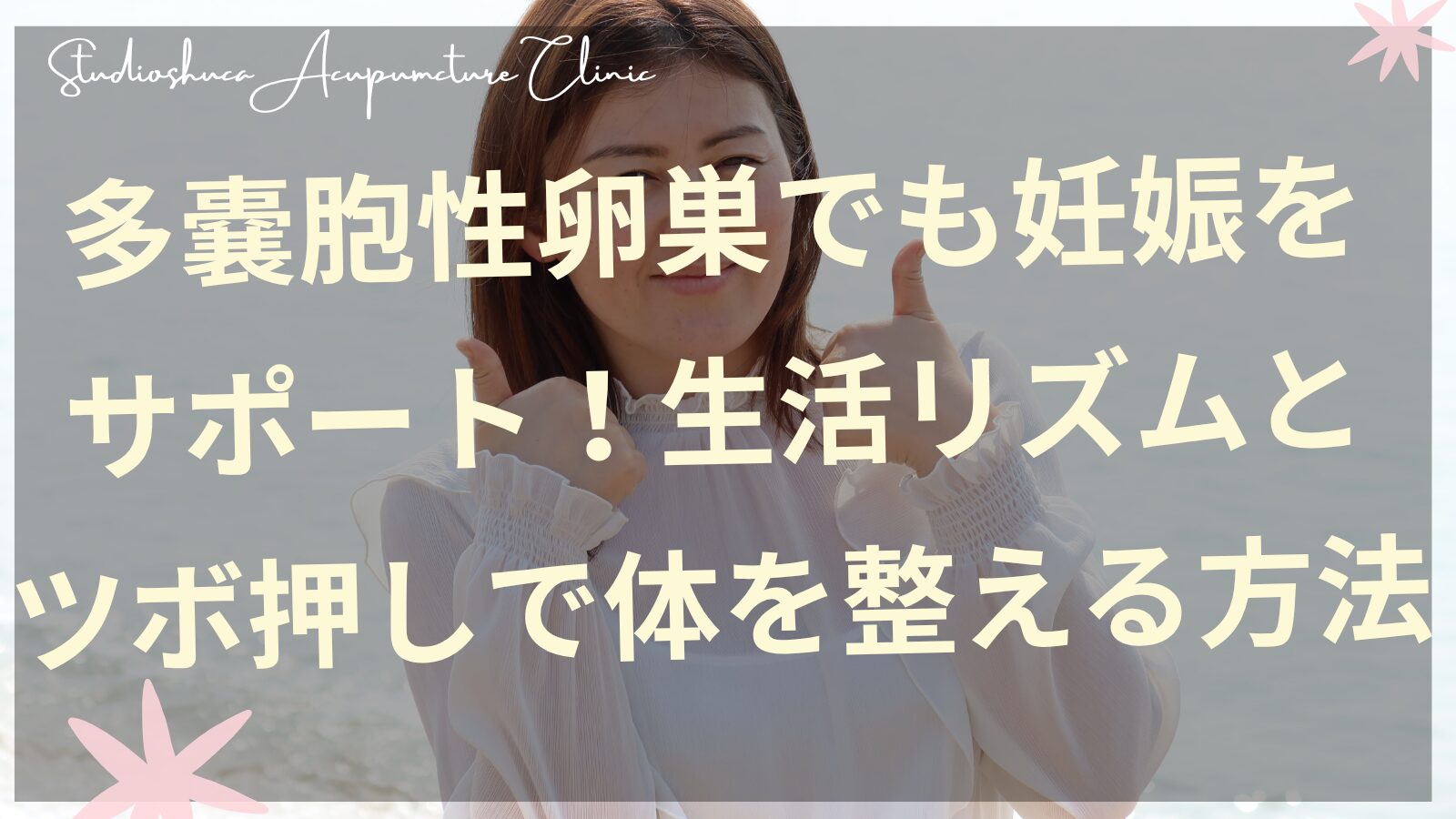
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
「PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)と診断されて、妊娠できるか不安…」
「生理不順が続いていて、自分でできることはないかな?」
そんなお悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。
PCOSは、排卵の乱れやホルモンバランスの変化が関わっていると言われています。でも、諦める必要はありません!生活リズムを整えたり、ツボ押しを取り入れたりすることで、体の巡りをサポートできる可能性があるんです。
このブログを読むと分かること
- PCOSの方が取り組める生活習慣の整え方
- 自宅でできるツボ押しの方法
- 東洋医学から見たPCOSへのアプローチ
- 鍼灸でのサポート内容
こんな方におすすめです
- PCOSと診断されて妊活中の方
- 生理不順や排卵の乱れにお悩みの方
- 病院での治療と並行して、自分でもケアしたい方
- 鍼灸や東洋医学に興味がある方
一緒に、あなたらしい体づくりを始めていきましょう♪
妊活がつらい人この4つだけやって
PCOSと診断されて不安を感じている方、生理不順や排卵の乱れに悩んでいる方、あなたは一人ではありません。当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、妊娠しやすい体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし鍼灸や東洋医学に興味がおありでしたら、こちらのページで詳しく解説しています。
PCOSってどんな状態?基本を知ろう
PCOSの主な特徴
PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)は、卵巣に小さな卵胞がたくさんできてしまう状態を指します。
この状態では、排卵が起こりにくくなり、生理不順や無月経といった症状が現れることがあります。ただし、症状の現れ方には個人差があり、人によって状態は様々です。
一般的には以下のような特徴が見られると言われています。
- 生理周期が不規則になる(35日以上空く、または年に数回しか来ない)
- 排卵が起こりにくい
- 卵巣に小さな卵胞が複数確認される
- 体重が増えやすい傾向がある
PCOSと診断されても、適切なケアやサポートで妊娠されている方はたくさんいらっしゃいます。大切なのは、ご自身の体と向き合い、できることから始めていくことなんです。
ホルモンバランスとの関係
PCOSの背景には、ホルモンバランスの変化が関わっていると考えられています。
特に、LH(黄体形成ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)のバランス、男性ホルモンの影響などが指摘されています。また、インスリン抵抗性との関連も注目されているんです。
こうしたホルモンのバランスが乱れることで、排卵がスムーズに起こりにくくなると言われています。
でも、生活習慣を整えることで、体の巡りをサポートし、ホルモンバランスのケアにつながる可能性があります。次のセクションで、東洋医学の視点から見ていきましょう。
東洋医学から見たPCOSの背景
「気血水」の滞りとPCOS
東洋医学では、体を「気・血・水」という3つの要素で捉えます。
この3つがスムーズに巡っている状態が、健康な体と考えられているんです。PCOSの背景には、この「気血水」の滞りが関わっていると捉えられています。
気の巡りが悪い状態
ストレスや緊張が続くと、気の流れが滞りやすくなります。イライラしやすい、胸が詰まる感じがする、といった症状が現れることがあります。
血の滞り
血の巡りが悪くなると、生理痛がひどい、経血に塊が混じる、といった状態になることがあります。卵巣や子宮への栄養供給にも影響すると言われています。
水の停滞
体内の水分代謝が悪くなると、むくみやすい、体が重だるい、といった症状が出やすくなります。
PCOSでは、これらが複雑に絡み合っていることが多いんです。だからこそ、総合的に体の巡りを整えていくことが大切なんですね。
体質タイプ別の考え方
東洋医学では、PCOSの方を体質別に捉え、それぞれに合ったアプローチを考えます。
肝気鬱結タイプ
ストレスで気が滞りやすいタイプです。イライラしやすい、胸が詰まる感じがする、生理前に気分が落ち込むといった特徴があります。
腎虚タイプ
エネルギー不足で、卵巣機能が低下しやすいタイプです。疲れやすい、腰がだるい、夜間頻尿などの特徴が見られることがあります。
痰湿タイプ
水分代謝が悪く、体内に余分な湿が溜まりやすいタイプです。むくみやすい、体が重い、おりものが多いといった特徴があります。
個人の体質により、アプローチ方法は異なります。スタジオシュカでは、お一人おひとりの体質を見極めながら、最適なケアをご提案させていただいています。
PCOSの体質改善について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
生活リズムを整えてホルモンバランスをサポート
睡眠リズムの重要性
実は、睡眠リズムを整えることが、ホルモンバランスのケアにとても大切なんです。
毎日同じ時間に起床・就寝することで、体内時計が整いやすくなります。朝起きたら、まずカーテンを開けて朝日を浴びましょう!
朝日を浴びることで、セロトニンという幸せホルモンの分泌がサポートされます。そして、このセロトニンが、夜になるとメラトニンという睡眠ホルモンに変わるんです。
このサイクルが整うと、視床下部-下垂体-卵巣軸の調整にも役立つと言われています。
おすすめの睡眠習慣
- 毎日同じ時間に起床する(休日も含めて)
- 朝起きたらすぐにカーテンを開ける
- 夜11時までには布団に入る
- 寝る1時間前からスマホやPCの使用を控える
質の良い睡眠は、妊活の基本です。できることから少しずつ始めてみてくださいね。
食事のタイミングと内容
食事のタイミングと内容も、ホルモンバランスのケアに大きく関わっています。
特にPCOSの方は、血糖値の乱高下に注意が必要です。インスリン抵抗性が関わっていることがあるため、血糖値を安定させることが大切なんです。
食事のタイミング
- 3食を決まった時間に摂る
- 朝食を抜かない(血糖値の安定に重要)
- 夕食は就寝3時間前までに済ませる
食事の内容
- 低GI食品を意識する(玄米、全粒粉パン、そばなど)
- 野菜を最初に食べる(ベジファースト)
- たんぱく質をしっかり摂る(魚、大豆製品、卵など)
- 揚げ物や甘いものは控えめに
食事の工夫について、詳しくはこちらの記事もご参考にしてください。
適度な運動で気の巡りを促す
適度な運動は、気の巡りを促し、ストレス解消にもつながります。
ただし、激しすぎる運動は逆効果になることもあるんです。大切なのは、継続できる軽い運動を習慣にすることです。
おすすめの運動
- ウォーキング(20~30分程度)
- ヨガ(ゆったりとした動き)
- ストレッチ(特に股関節周り)
- 軽い筋トレ(スクワットなど)
週3回、20~30分程度を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。運動後は、体がポカポカして気持ちいいですよ♪
PCOSでも諦めないで。あなたの体は変わります
生活リズムやツボ押しなど、自宅でできるケアはたくさんあります。でも、一人で頑張りすぎなくて大丈夫。当院では、鍼灸を通じて体の巡りを整え、妊娠しやすい体質づくりをサポートしています。
不妊治療を受けている方、妊活中の方のお悩みに寄り添います。
自宅でできる!PCOSケアのツボ押し
ここからは、自宅で簡単にできるツボ押しをご紹介します。
東洋医学では、ツボ(経穴)への刺激が、体の巡りをサポートすると考えられています。毎日続けることで、体質のケアにつながる可能性がありますよ。
三陰交(さんいんこう)
場所
内くるぼしから指4本分上のところです。骨の際を探ってみると、少し凹んでいる部分があります。
期待される作用
婦人科系のトラブルに伝統的に用いられてきたツボです。生理不順、冷え、むくみのケアに良いと言われています。
押し方
親指で優しく、1回3~5分程度押します。痛気持ちいいくらいの強さがちょうど良いですよ。
関元(かんげん)
場所
おへそから指4本分下のところです。下腹部の中心にあります。
期待される作用
子宮周りを温めると言われるツボです。下腹部の冷えや、気力の低下に用いられてきました。
押し方
手のひら全体で、温めるようにゆっくり押します。お風呂上がりに行うと、より効果的と言われています。
血海(けっかい)
場所
膝のお皿の内側から、指3本分上のところです。太ももの内側にあります。
期待される作用
血の巡りをサポートすると言われるツボです。生理痛や生理不順のケアに用いられてきました。
押し方
親指でゆっくり、円を描くように押します。両足とも行いましょう。
太衝(たいしょう)
場所
足の親指と人差し指の骨が交わる手前の凹みです。
期待される作用
ストレス緩和、気の流れを整えると言われています。イライラや不眠にも良いとされるツボです。
押し方
気持ち良いと感じる程度に、ゆっくり押します。深呼吸しながら行うと、よりリラックスできますよ。
ストレスと排卵の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ツボ押しの基本ポイント
ツボ押しを効果的に行うためのポイントをお伝えします。
- 1日1回、リラックスした状態で行う
- 痛すぎない、気持ち良い程度の強さで
- 入浴後など、体が温まっている時がおすすめ
- 継続することが大切です
- 爪を立てず、指の腹で押す
無理のない範囲で、毎日の習慣にしてみてくださいね。
より詳しいツボについては、こちらの記事もご覧ください。
食事でPCOSの体質をサポートする方法
血糖値を安定させる食材選び
PCOSの方にとって、血糖値の安定はとても大切です。
血糖値が急激に上がったり下がったりすると、インスリンの分泌に影響し、ホルモンバランスが乱れやすくなると言われています。
おすすめの低GI食品
- 玄米、雑穀米
- 全粒粉パン、そば
- 野菜全般(特に葉物野菜)
- きのこ類、海藻類
- 豆類(大豆、ひよこ豆など)
控えめにしたい食品
- 白米、白いパン
- お菓子、ケーキ
- 清涼飲料水
- 加工食品
食べる順番も大切です。野菜→たんぱく質→炭水化物の順で食べる「ベジファースト」を心がけましょう。
ホルモンの材料になる栄養素
ホルモンは、食事から摂る栄養素を材料に作られます。
特に、たんぱく質、ビタミンB群、亜鉛などが重要と言われています。
たんぱく質
魚(特に青魚)、大豆製品(豆腐、納豆)、卵、鶏肉など。1食あたり手のひらサイズが目安です。
ビタミンB群
玄米、豚肉、納豆、アボカド、バナナなど。エネルギー代謝をサポートすると言われています。
亜鉛
牡蠣、レバー、ナッツ類、卵など。ホルモン合成をサポートすると言われています。
バランスよく、毎日の食事に取り入れていきましょう。
体を温める食材
東洋医学では、体を温めることが妊活の基本と考えられています。
冷えは、気血水の巡りを悪くする大きな要因なんです。日頃から、体を温める食材を意識して摂りましょう。
体を温める食材
- 生姜、ネギ、ニンニク
- シナモン、唐辛子(適量)
- 根菜類(ごぼう、れんこん、にんじん)
- かぼちゃ、さつまいも
- 黒豆、小豆
控えめにしたいもの
- 冷たい飲み物(特に氷入り)
- 生野菜の食べ過ぎ
- 南国のフルーツ(バナナ、パイナップルなど)
温かいお茶や白湯を飲む習慣もおすすめです。体の内側から温めていきましょう。
冷え対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
鍼灸でのPCOSケア~当院のアプローチ~
鍼灸がPCOSにどうアプローチするか
スタジオシュカでは、東洋医学の視点から、PCOSの体質ケアをサポートしています。
鍼灸は、ツボへの刺激を通じて、気血水の巡りを整えることを目指します。体のバランスをケアすることで、妊娠しやすい体づくりのお手伝いをさせていただいています。
期待されるアプローチ
- 気血水の巡りを整えるサポート
- 自律神経のバランスケア
- ストレス緩和、リラクゼーション
- 骨盤周りの血流ケア
ただし、鍼灸は医療行為ではなく、体質ケアのお手伝いです。効果には個人差があり、施術効果を保証するものではありません。
PCOSと鍼灸については、こちらの記事もご参考にしてください。
施術の流れと期間の目安
初回の流れ
- カウンセリング(お悩みや体質のチェック)
- 体の状態確認(舌診、脈診など)
- 施術(お一人おひとりに合わせたツボ選び)
- 今後のケアプランのご提案
通院の目安
週1回~2週に1回のペースが一般的です。体質を整えるには、3ヶ月程度継続されることをおすすめしています。
ただし、個人の体質により体験には個人差があります。体の変化を見ながら、最適なペースをご提案させていただきます。
不妊治療との併用について
スタジオシュカでは、病院での不妊治療と並行して、鍼灸でのケアを受けていただけます。
実際に、体外受精や人工授精を受けながら、当院に通われている方もたくさんいらっしゃいます。治療内容を共有いただくことで、より適切なサポートが可能になります。
併用のメリット
- 治療のストレスケア
- 体調を整えながら治療に臨める
- 採卵前、移植前のコンディション作り
医師の指示に従いながら、鍼灸でのケアを取り入れていただくことが大切です。医療行為の代替ではありませんので、病院での治療はしっかり続けてくださいね。
不妊治療との併用については、こちらの記事もご覧ください。
まとめ:PCOSでも諦めないで。体は変わります
ここまで、PCOSの体質をサポートする方法について、お伝えしてきました。
PCOSと診断されても、妊娠の可能性をサポートする方法はたくさんあります。生活リズムを整える、食事を見直す、ツボ押しを続けるなど、自宅でできることから始めてみましょう。
そして、鍼灸は、体の巡りを整え、ホルモンバランスをサポートするお手伝いができます。
一人で頑張りすぎず、専門家のサポートを受けることも大切です。焦らず、ご自分のペースで体づくりを続けていきましょうね。
あなたらしい妊活を、スタジオシュカが全力でサポートします。
松戸・流山・我孫子から車で10分、柏市富里のスタジオシュカ鍼灸治療院で、お待ちしています♪
一緒に、あなたらしい妊活を
PCOSがあっても、妊娠の可能性をサポートする方法はあります。生活習慣の見直しや、鍼灸でのケアを通じて、体を整えていきましょう。
当院では、一人ひとりの体質やお悩みに合わせた施術とカウンセリングで、妊活をサポートしています。
個人の体質により体験には個人差があります
施術効果を保証するものではありません
医療行為の代替ではありません
体験者の声もご紹介しております。
