乾燥する秋に潤いチャージ!肺を守る食材選びと東洋医学ケア【松戸・流山・我孫子】
2025-10-04 季節の養生法
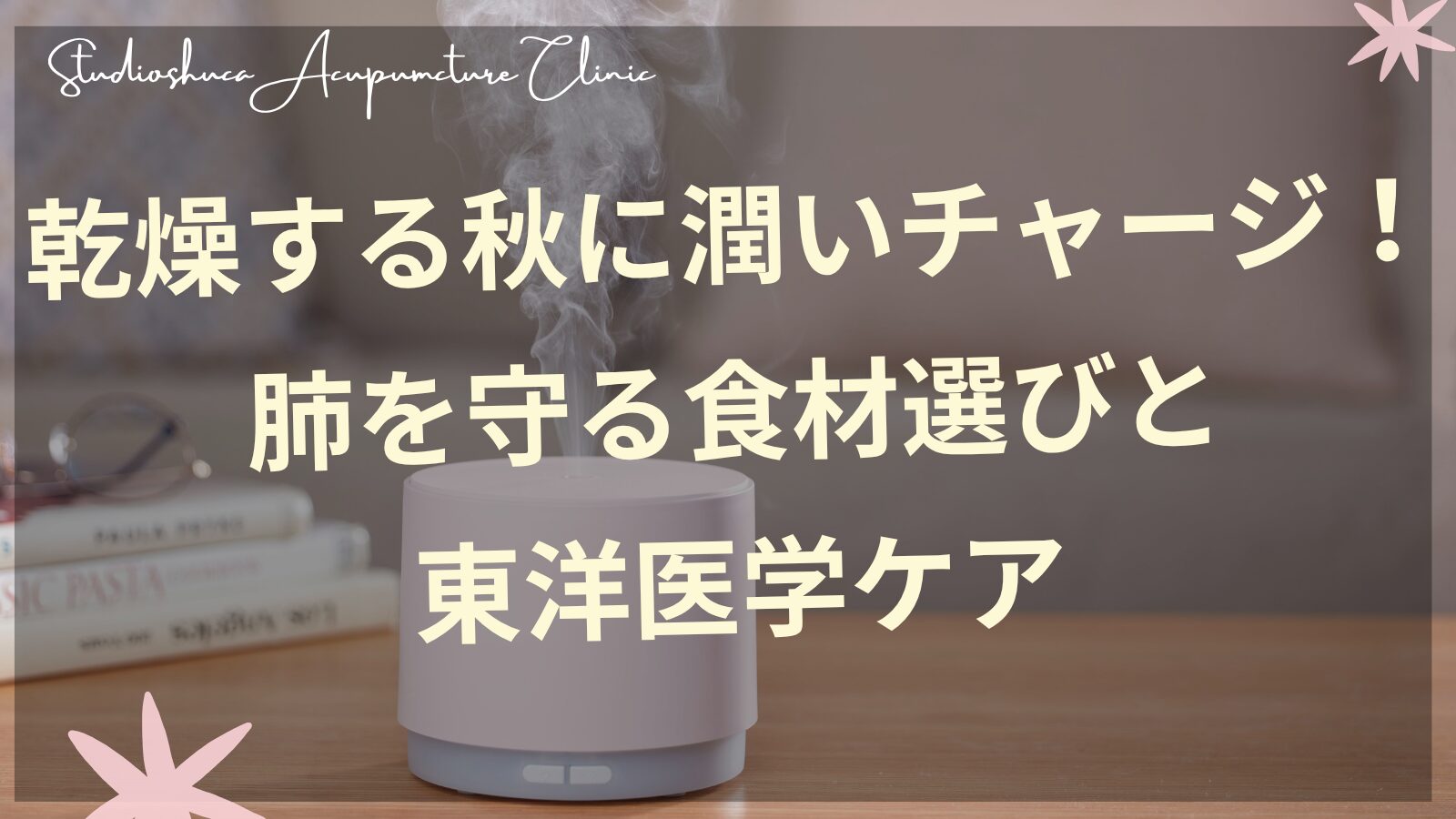
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です
秋になると、肌がカサカサしたり、喉がイガイガしたり、なんとなく体が乾いている感じがしませんか?
「化粧ノリが悪くなった」「空咳が止まらない」「髪がパサついて気になる」…そんなお悩み、実は秋特有の乾燥が原因かもしれません。
実は、秋の乾燥は外側だけでなく、体の内側にも大きく影響を与えているんです!
東洋医学では、秋は「肺」の季節と言われていて、肺を潤すケアがとても大切とされています。
このブログでは、秋の乾燥対策として「肺を守る食材選び」を中心に、東洋医学の視点からのケア方法を詳しくご紹介します。
このブログを読むとわかること
- 東洋医学における「肺」と秋の乾燥の関係
- 肺を潤す「白い食材」の選び方と効果的な取り入れ方
- 秋の養生に役立つ具体的な食事のコツ
- 自宅でできる簡単なセルフケア方法
こんな方におすすめです
- 秋になると肌や喉の乾燥が気になる方
- 体の内側から潤いをサポートしたい方
- 東洋医学の季節養生に興味がある方
- 食事で体質をケアしたいと考えている方
それでは、秋の潤いケアについて一緒に見ていきましょう♪
—
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
—
東洋医学から見た秋と「肺」の関係
秋は「肺」の季節と言われる理由
東洋医学には「五行説」という考え方があります。
この五行説では、自然界のすべてのものを「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類して考えるんです。
そして、秋は「金」の要素に対応し、体の臓器では「肺」と深く関係があるとされています。
東洋医学における「肺」は、単なる呼吸器官だけを指すのではありません。
肺は呼吸だけでなく、皮膚や粘膜、体全体の潤いを管理する役割があると考えられているんです!
だから、秋に肌が乾燥したり、喉がイガイガしたりするのは、「肺の潤いが不足している」サインかもしれません。
秋の気候(涼しさと乾燥)が肺に影響を与えやすいとされ、この時期は特に肺のケアが大切になります。
「燥邪(そうじゃ)」が体に与える影響とは
東洋医学では、秋の乾燥した空気を「燥邪(そうじゃ)」と呼びます。
「邪」というと怖い感じがしますが、体に悪影響を与える外的要因のことを指すんです。
燥邪は、体内の水分を奪い、肺を傷つけやすいと言われています。
空気の乾燥という外的要因と、水分不足という内的要因の両方が重なると、体の不調が出やすくなるんですね。
一般的に、秋から冬にかけては湿度が下がり、空気が乾燥します。
この乾燥が、私たちの体にじわじわと影響を与えていくんです。
肺が乾燥するとどんな不調が出やすいの?
東洋医学で考える「肺」が乾燥すると、以下のような不調が出やすいと言われています。
- 肌のカサつき、化粧ノリの悪さ – 肺は皮膚とつながっているとされる
- 喉の乾燥、空咳、イガイガ感 – 肺の潤い不足が喉に現れやすい
- 鼻やのどの粘膜が弱り、風邪を引きやすくなる – 粘膜のバリア機能が低下しやすい
- 髪のパサつき、爪が割れやすい – 体全体の潤い不足のサイン
- 便秘がちになる – 腸の潤いも不足しやすい
- 気分の落ち込み、憂鬱感 – 秋特有の物悲しさを感じやすい
西洋医学的には、「気道粘膜の乾燥」や「皮膚のバリア機能低下」として説明される現象です。
東洋医学では、これらを「肺の潤い不足」という一つの概念で捉えているんですね。
個人差はありますが、このような不調を感じたら、肺を潤すケアを意識してみることをおすすめします♪
肺を潤す「白い食材」の東洋医学的な意味
なぜ白い食材が肺に良いとされるの?
東洋医学の五行説では、色と臓器にも関係性があると考えられています。
秋の「金」の要素に対応する色が「白」なんです。
だから、白い食材は肺を養うとされ、古くから秋の養生に取り入れられてきました。
白い食材の多くは、水分や粘液質を含み、体を潤す性質があると言われています。
実際に、白い食材の多くは水分や食物繊維が豊富で、粘膜保護に役立つ成分を含むことが知られているんです!
現代栄養学とは異なるアプローチですが、経験的に有効とされてきた知恵なんですね。
五行説から見る「白」と「肺」のつながり
五行説は、紀元前から伝わる東洋思想の一つです。
五行(木・火・土・金・水)と五臓(肝・心・脾・肺・腎)が対応しています。
| 五行 | 季節 | 臓器 | 色 |
|---|---|---|---|
| 金 | 秋 | 肺 | 白 |
このように、「金」の要素が秋・肺・白色に関連すると考えられているんです。
古来から受け継がれてきた知恵として、季節と食材の関係性が重視されてきました。
この伝統的な考え方を、現代の私たちの生活にも活かしていけるといいですよね♪
もっと詳しい東洋医学の考え方について知りたい方は、こちらもご覧ください。
鍼灸の効果とメリット:体の不調を自然治癒力で改善!
おすすめの白い食材7選とその取り入れ方
それでは、具体的にどんな白い食材が肺を潤すとされているのか、7つご紹介していきますね!
大根:辛味で肺の気を巡らせる
大根は、辛味成分が気の巡りをサポートすると言われています。
水分が豊富で、体を潤す働きが期待されるんです。
大根おろしとして摂取すると、消化酵素も活性化すると一般的に言われていますよ。
簡単な取り入れ方:
- 朝の味噌汁に入れる
- サラダに千切りで
- おろしとしてお肉やお魚に添える
- 大根スープで温かく
白きくらげ:肺を潤す代表的な食材
白きくらげは、古来より「肺を潤す」食材として珍重されてきました!
コラーゲンや食物繊維が豊富で、美容にも良いとされています。
デザートやスープで取り入れやすいのも嬉しいポイントです。
簡単な取り入れ方:
- 白きくらげの甘煮(デザートとして)
- 中華スープに入れる
- サラダのトッピングに
- 乾物なので保存がきいて便利
れんこん:粘膜を保護する働きが期待される
れんこんのネバネバ成分(ムチン)が、粘膜保護をサポートすると言われています。
ビタミンCや食物繊維も豊富なんです。
咳を和らげる働きがあるとされ、昔から民間療法としても使われてきました。
簡単な取り入れ方:
- れんこんのきんぴら
- 煮物にして常備菜に
- すりおろしてスープに入れる
- 薄切りにしてチップスに
梨:喉の渇きを潤すと言われる
梨は水分が90%近く含まれていて、自然な潤い補給にぴったりです!
熱を冷まし、喉の不快感を和らげるとされています。
咳止めとして伝統的に用いられてきた果物なんですよ。
簡単な取り入れ方:
- そのまま食べる(一番簡単!)
- すりおろしてジュースに
- 蜂蜜と一緒に煮てコンポートに
- サラダに入れてさっぱりと
山芋:肺と腎を同時にサポート
山芋のネバネバ成分が、体を潤すと考えられています。
消化吸収を助け、体力サポートにも期待できるんです。
免疫機能のサポートに役立つと言われています。
簡単な取り入れ方:
- とろろご飯(定番ですよね!)
- 短冊切りでサラダに
- すりおろして味噌汁に
- お好み焼きに入れてふわふわに
白ごま:良質な脂質で内側から潤いを
白ごまは、不飽和脂肪酸やビタミンEが豊富です。
肌や粘膜の健康維持に役立つと言われているんです。
抗酸化作用が期待され、エイジングケアにも注目されています♪
簡単な取り入れ方:
- ご飯にふりかけとして
- サラダのトッピングに
- すりごまで料理の風味アップ
- ごまドレッシングを手作り
豆腐・豆乳:植物性タンパク質で穏やかに潤す
大豆イソフラボンが、女性の体調サポートに期待されています。
消化に優しく、胃腸に負担をかけにくいのも特徴です。
毎日取り入れやすい食材なので、継続しやすいですよ!
簡単な取り入れ方:
- 冷奴(夏から秋への移行期に)
- 湯豆腐(涼しくなってきたら)
- 豆乳スープ
- 豆乳ラテで朝のリラックスタイムに
これらの食材について、もっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。
卵子の質を上げる!妊娠しやすい体づくりをサポートする食べ物
—
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
—
食材を効果的に取り入れる調理のコツ
温かく調理することの大切さ
秋は気温が下がり始める季節なので、体を冷やさない工夫が大切です。
生の食材より加熱調理の方が、消化吸収が良いとされています。
スープや煮物にすることで、水分と栄養を同時に摂取できるんです!
温かい食事が内臓を温め、代謝サポートにつながると考えられています。
特に朝晩が冷え込む秋は、温かいお料理で体の内側から温めていきましょう♪
朝食に取り入れる習慣づくり
一日の始まりに潤いをチャージすることには、大きな意味があります。
朝の胃腸は吸収力が高いと一般的に言われているんです。
簡単な朝食メニュー例:
- 大根おろし入り味噌汁
- 豆乳スープ
- 梨のコンポート(前日に作り置き)
- とろろご飯
- 白ごまふりかけご飯
継続しやすい簡単レシピを選ぶことがポイントですよ。
無理なく続けられることが、体質ケアには一番大切なんです!
簡単レシピで毎日続けられる工夫
忙しい毎日でも続けられるように、工夫してみましょう。
続けやすくする工夫:
- 作り置きできるメニューを活用する
- 冷凍保存できる食材を準備しておく
- 忙しい日でも取り入れやすい時短レシピを選ぶ
- 週末にまとめて下ごしらえをする
例えば、白きくらげは乾物で保存できますし、山芋は冷凍保存も可能です。
豆腐や豆乳は常備しやすい食材ですよね。
ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく続けていきましょう♪
食事以外でできる秋の潤いケア
食事だけでなく、生活習慣全体で潤いをサポートしていきましょう!
水分補給の上手な方法
秋は空気が乾燥するので、意識的な水分補給が大切です。
ただし、冷たい水より常温や温かいお茶がおすすめなんです。
一度に大量に飲むより、こまめに少しずつ飲む方が効果的と言われています。
おすすめの飲み物:
- 麦茶(ノンカフェインで優しい)
- ルイボスティー(抗酸化作用が期待される)
- 白湯(内臓を温める)
- 生姜湯(体を芯から温める)
水分補給のタイミング:
- 起床時(コップ1杯の白湯がおすすめ)
- 食事前(消化をサポート)
- 入浴前後(脱水予防)
- 就寝前(夜間の乾燥対策)
水分補給について、もっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。
妊娠に役立つ水選びのポイントとおすすめ商品
深い呼吸で肺の働きをサポート
腹式呼吸が、自律神経を整えると言われています。
深い呼吸で肺の機能を活性化させることができるんです!
簡単な呼吸法:
- 鼻から4秒かけてゆっくり息を吸う
- 8秒かけてゆっくり口から息を吐く
- これを5回繰り返す
朝起きた時や就寝前に実践するのがおすすめです。
深い呼吸は、副交感神経を活性化し、リラックス効果が期待されます。
体の約60%は水分で構成されていると言われていますので、呼吸と水分のバランスが大切なんですね。
睡眠時間の確保が肺の回復に大切
東洋医学では、午前3~5時が「肺の時間」とされています。
この時間帯に深い睡眠を取ることが、肺の回復に役立つと考えられているんです。
質の良い睡眠が、免疫力サポートにつながると一般的に言われています。
就寝前のリラックス習慣:
- ラベンダーなどのアロマ(個人差があります)
- 軽いストレッチ
- 温かい飲み物(カフェインレス)
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
22時〜23時頃には就寝できるよう心がけると、肺の時間にぐっすり眠れますよ♪
季節の変わり目の体調管理については、こちらの記事も参考にしてください。
季節の変わり目の気圧変化で崩れる自律神経をリセット!
東洋医学の鍼灸で秋の乾燥をサポート
肺経と関連するツボの紹介
東洋医学では、「経絡」という気の通り道があると考えられています。
肺経に関連するツボを刺激することで、肺の働きをサポートすると言われているんです。
肺経の代表的なツボ:
尺沢(しゃくたく)
場所:肘の内側、肘を曲げたときにできるシワの上
伝統的な意味:咳や喉の不調をサポートすると言われる
太淵(たいえん)
場所:手首の内側、親指側のくぼみ
伝統的な意味:呼吸を整え、肺を潤すとされる
魚際(ぎょさい)
場所:親指の付け根のふくらみ
伝統的な意味:喉の痛みや熱感をサポートすると言われる
その他のサポートツボ:
足三里(あしさんり)
場所:膝のお皿の外側から指4本分下
伝統的な意味:胃腸の働きを整え、全身の気を巡らせる
三陰交(さんいんこう)
場所:内くるぶしから指4本分上
伝統的な意味:女性の体調全般をサポートすると言われる
自宅でこれらのツボを優しく押すセルフケアと、専門的な鍼灸施術では、アプローチの深さが異なります。
個人差がありますので、ご自身に合った方法を見つけていきましょう。
鍼灸施術で期待できる体験
鍼灸施術では、体全体のバランスを整えることをサポートすると言われています。
気血の巡りを促す働きが期待されるんです。
リラックス効果により、自律神経が整いやすいとされています。
一般的に、鍼灸が自律神経系に作用すると考えられているメカニズムがあるんですよ。
ただし、重要な点があります:
- 個人差があります
- 効果を保証するものではありません
- 医療行為の代替ではありません
東洋医学の学術的な背景については、こちらも参考になります。
日本東洋医学会
スタジオシュカでの季節養生サポート
スタジオシュカ鍼灸治療院では、一人ひとりの体質に合わせたケアをご提案しています。
東洋医学では、同じ症状でも体質によってアプローチが変わると考えられているんです。
当院でのサポート内容:
- 体質診断(東洋医学的な「証」の見極め)
- 季節の変わり目に特化した施術メニュー
- 食事や生活習慣のアドバイスも含めたトータルサポート
- 継続的なケアで体質改善のお手伝い
秋の乾燥が気になる方、体の内側から潤いをサポートしたい方は、ぜひご相談ください♪
松戸・流山・我孫子から車で10分とアクセスも便利です。
鍼灸と漢方を組み合わせたケアについては、こちらもご覧ください。
漢方と鍼灸の組み合わせ方
秋の養生について、もっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。
秋の乾燥から肌と体を守る!潤いを保つ東洋医学的ケア法
ホルモンバランスが気になる方はこちらも参考になります。
秋の妊活体質づくり!季節の変わり目のホルモンバランス調整術
まとめ:秋は「潤い」を意識した養生を
ここまで、秋の乾燥対策として「肺を守る食材選び」を中心にお伝えしてきました。
秋の乾燥は、外側だけでなく体の内側からのケアがとても大切なんです!
今日から実践できること:
- 「白い食材」を日々の食事に取り入れる
- 温かく調理して体を冷やさない
- こまめな水分補給を心がける
- 深い呼吸で肺の働きをサポート
- 質の良い睡眠で体を回復させる
食事・水分補給・睡眠・呼吸法など、多角的なアプローチが有効です。
一度にすべてを完璧にする必要はありません。
できることから少しずつ、無理なく続けていくことが大切なんです♪
一人で続けるのが難しいと感じたら、専門家のサポートも検討してみてくださいね。
秋の養生をしっかり行うことで、冬に向けた体づくりの準備ができます。
今から始めれば、冬の寒さにも負けない強い体を作っていけますよ!
スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせた季節養生をサポートしています。
秋を元気に、そして美しく過ごすために、一緒に体づくりを始めませんか?
あなたの体が、潤いに満ちた健やかな状態になることを心から願っています✨
—
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
—
免責事項
※個人の体質により体験には個人差があります。
※施術効果を保証するものではありません。
※鍼灸は医療行為の代替ではありません。気になる症状がある場合は、まず医療機関を受診してください。
—
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
