冬に向けて体力を蓄える!11月の無理しない養生法で元気に冬を迎える【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-11-01 季節の養生法
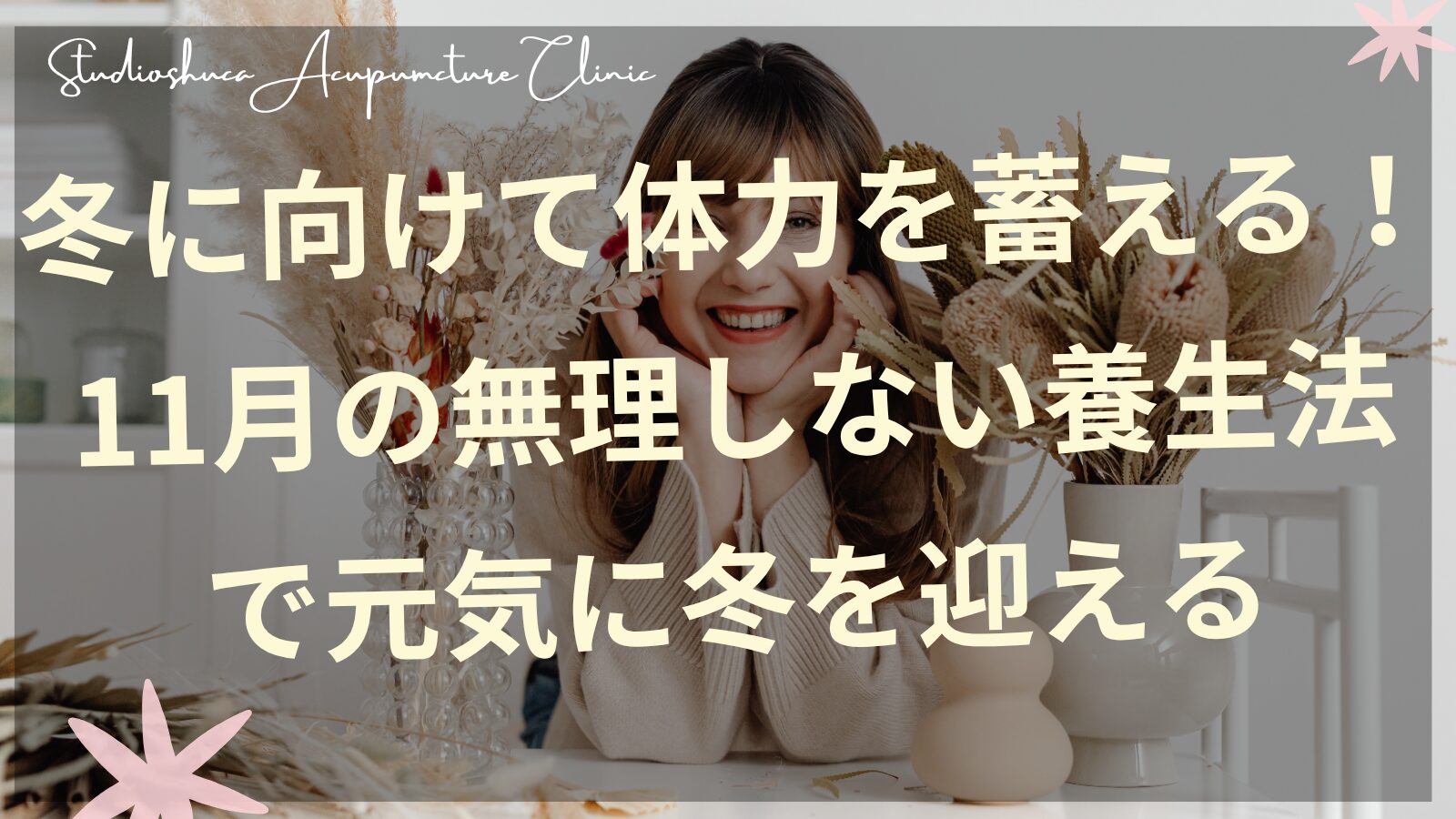
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
11月に入って、なんだか疲れやすくなっていませんか?
朝起きるのがつらかったり、体が重く感じたり…。
それ、実は体が「冬支度」を始めているサインかもしれません!
東洋医学では、冬は「蔵(しまう)」の季節。
動物が冬眠するように、私たち人間も体にエネルギーを蓄えて、春に向けて力を温存する時期なんです。
この記事では、11月から始める「無理しない養生法」をご紹介します。
読み終わる頃には、冬に向けてどう過ごせばいいのかが分かり、自分の体をいたわる方法が見つかりますよ。
こんな方におすすめの記事です:
- 11月になって急に疲れやすくなった方
- 冬が来る前に体調を整えたい方
- 無理せず続けられる養生法を知りたい方
- 季節の変わり目に体調を崩しやすい方
それでは、一緒に冬支度を始めていきましょう!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
東洋医学から見た11月の体と「蔵」の考え方
11月は、秋から冬へと移り変わる大切な時期です。
この時期、体にはどんな変化が起きているのでしょうか?
東洋医学の視点から、11月の体と「蔵(しまう)」という考え方について見ていきましょう。
冬は「腎」の季節、11月はその準備期間
東洋医学には「五行説」という考え方があります。
この考え方では、冬は「腎」の季節とされているんです。
「腎」は、生命力の源であり、成長・発育・生殖に関わるとされています。
現代医学でいう腎臓とは少し違って、もっと広い意味を持つんですよ。
冬に腎のエネルギーが不足すると、こんな症状が現れることがあります:
- 疲労感が抜けない
- 手足の冷えがひどくなる
- 腰が重だるい
- 風邪をひきやすくなる
個人差はありますが、11月から腎のケアを始めることで、冬の健康維持をサポートできると考えられています。
早めの準備が、冬を元気に過ごす鍵なんです!
「動」から「静」へ、自然のリズムに合わせる大切さ
東洋医学には「天人相応」という素敵な言葉があります。
これは「自然界のリズムに合わせることが健康維持に役立つ」という考え方です。
秋から冬にかけては「陰」のエネルギーが増す時期。
日照時間も短くなり、気温も下がっていきますよね。
この時期、自然界の動物たちは冬眠の準備を始めます。
私たち人間も、同じように体が自然と「静」を求めているんです。
無理に活動的になろうとせず、ゆったりとしたペースで過ごすことが大切なんですよ。
秋の「なんとなくだるい」を解消する方法でも詳しくお話ししていますが、この時期の「だるさ」は体からのメッセージかもしれません。
エネルギーを消耗しないための「無理しない」マインド
現代社会は「頑張る」ことを良しとする風潮がありますよね。
でも、東洋医学では「動と静」のバランスがとても大切なんです。
冬に向けて「静」の時間を意識的に増やすことが、体を守ることにつながります。
休むことに罪悪感を感じていませんか?
「みんな頑張っているのに、自分だけ休むなんて…」
そんな風に思ってしまう方も多いかもしれません。
でも、休むことは「悪いこと」じゃないんです。
むしろ、冬に向けてエネルギーを蓄えるための、とても大切な行動なんですよ。
自分の体をいたわることは、自分を大切にすることと同じです。
11月に起こりやすい体の変化と不調のサイン
11月は体にさまざまな変化が起こりやすい時期です。
どんな不調が現れやすいのか、その理由と合わせて見ていきましょう。
疲れやすさ・だるさが増える理由
11月になって、こんな症状はありませんか?
- 朝起きるのがつらい
- 日中もなんとなくだるい
- 夕方になると疲れがどっと出る
- 休んでも疲れが取れない
これには、いくつかの理由があります。
まず、気温が下がることで体温を維持するためのエネルギー消費が増えます。
一般的に、寒冷刺激により基礎代謝が上がると言われているんです。
さらに、夏から秋にかけて頑張りすぎた疲労が、この時期に表面化することも多いんですよ。
東洋医学では、これを「腎虚(じんきょ)」という状態で説明します。
腎虚とは、腎のエネルギーが不足している状態のこと。
疲労感、だるさ、腰痛などの症状が現れることがあります。
個人差はありますが、この時期の疲れは体からの「休んでほしい」というサインかもしれません。
冷えや免疫力低下に注意が必要な時期
11月は気温差が激しい日も多いですよね。
朝晩は冷え込むのに、日中は暖かかったり…。
この気温差が、自律神経の乱れを招くことがあります。
自律神経が乱れると、体温調節がうまくいかなくなり、冷えを感じやすくなるんです。
東洋医学では、「腎」と免疫力に深い関係があるとされています。
腎のエネルギーが不足すると、体を守る力も弱くなってしまうという考え方です。
風邪をひきやすくなるのも、この時期の特徴なんですよ。
秋の温活養生術も参考にしてみてくださいね。
気持ちの落ち込みと「腎」の関係
11月になって、なんだか気持ちが沈みがち…。
そんな経験はありませんか?
実は、これにも理由があるんです。
日照時間が短くなると、セロトニン(幸せホルモン)の分泌が減ることが知られています。
これが気分の落ち込みにつながることがあるんですよ。
東洋医学では、「腎」と「恐れ・不安」という感情に関係があるとされています。
腎のエネルギーが不足すると、不安感や恐れの感情が強くなりやすいという考え方なんです。
季節性の気分の変化は、決してあなただけではありません。
多くの方が経験する自然な反応なんですよ。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
冬に向けてエネルギーを蓄える5つの養生法
それでは、具体的な養生法をご紹介していきます!
どれも今日から始められる簡単な方法ばかりですよ。
① 早寝早起きで「陽気」を温存する
睡眠は、エネルギーを蓄えるための最も基本的な方法です。
特に11月からは、早寝を心がけることが大切なんですよ。
理想的な就寝時間
東洋医学では、夜10時~深夜2時が「腎」のエネルギーが回復する時間帯とされています。
西洋医学的にも、この時間帯に成長ホルモンの分泌が盛んになると言われているんです。
できれば夜10時~11時には就寝するのが理想的ですよ。
良質な睡眠を得るための具体的な方法
- 夕食は就寝3時間前までに済ませる
- 寝る1時間前からスマホ・PCを控える
- 温かいハーブティーで体を温める
- 寝室の温度を18~22度に保つ
- 暗く静かな環境を整える
個人差はありますが、この時間帯の睡眠が体の回復をサポートすると考えられています。
秋の夜長に質の良い睡眠を得る方法も合わせてご覧くださいね。
② 体を温める食材で「腎」をサポートする
食事は、体を内側から温める大切な要素です。
11月からは特に、体を温める食材を意識して摂るようにしましょう!
黒い食材で腎をサポート
東洋医学では「黒色」が「腎」に対応し、黒い食材が腎のエネルギーをサポートするとされています。
- 黒豆
- 黒ごま
- 黒米
- ひじき
- きくらげ
これらを毎日の食事に少しずつ取り入れてみてください。
根菜類で体を温める
根菜類は体を温める「温性」の食材が多く、冬の養生に適していると言われています。
- かぼちゃ
- にんじん
- 大根
- ごぼう
- れんこん
温かいスープや煮込み料理がおすすめ
調理法も大切です。
生野菜サラダよりも、温かいスープや煮込み料理の方が体を温めてくれます。
消化もしやすいので、胃腸への負担も軽くなりますよ。
避けたい食材
この時期は、できるだけ控えめにしたい食材もあります。
- 生もの(刺身など)
- 冷たい飲み物
- アイスクリーム
- 体を冷やす南国のフルーツ(バナナ、パイナップルなど)
あくまで伝統的な考え方であり、個人の体質により効果には個人差があります。
秋の味覚で体を整える薬膳効果も参考にしてみてくださいね。
③ 無理な運動は避け、ゆったりとした動きを心がける
運動は健康に良いものですが、冬に向けては「量」よりも「質」が大切です。
激しい運動は「陽気」を消耗してしまうんですよ。
おすすめの穏やかな運動
- 散歩(1日20~30分)
- ゆったりとしたストレッチ
- ヨガ
- 太極拳
- 気功
これらの運動は、深い呼吸を意識しながらゆったりと行えるのがポイントです。
具体的な実践方法
- 朝起きたら、ベッドの上で軽くストレッチ(5分)
- 午前中に20~30分の散歩
- 夕方、お風呂の前に軽いヨガやストレッチ(10分)
- 汗をかきすぎない程度の運動量を守る
汗をかきすぎると「陽気」を消耗してしまうので、軽く体が温まる程度を目安にしてくださいね。
④ 「腎兪」「太渓」のツボで腎のエネルギーケア
ツボ押しは、自宅で簡単にできるセルフケアです。
特に「腎」に関係するツボをご紹介しますね!
腎兪(じんゆ)
腰の両側、第2腰椎の高さ(へそと同じ高さあたり)に位置します。
東洋医学では、このツボが腎のエネルギーをサポートするとされています。
セルフケア方法:
- カイロや湯たんぽで温める(1回10~15分)
- お風呂で温めながら、軽く手のひらで押す
- 毎日続けることが大切です
太渓(たいけい)
内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみに位置します。
「腎経」の重要なツボとされているんですよ。
セルフケア方法:
- 親指で優しく円を描くように押す(左右各30秒~1分)
- 気持ちいいと感じる程度の強さで
- お風呂上がりや寝る前に行うと効果的です
効果には個人差があります。強く押しすぎず、気持ちいいと感じる程度の刺激を心がけてください。
ツボで体を温める方法も合わせてご覧くださいね。
⑤ 「休むことは悪いことじゃない」というマインドセット
最後は、心の持ち方についてです。
これが実は、一番大切かもしれません!
現代社会の「頑張りすぎ文化」
私たちは、つい「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまいますよね。
でも、東洋医学では「動と静」のバランスがとても大切なんです。
冬に向けて「静」の時間を意識的に増やすことが、体を守ることにつながります。
罪悪感を手放す方法
- 「休むことは、エネルギーを蓄えること」と考える
- 「自分を大切にすることは、周りの人を大切にすることにもつながる」と気づく
- 完璧を求めず、「今日はこれだけできればOK」と自分を認める
- 疲れたら無理せず休む、を習慣にする
自分をいたわる時間の確保
毎日、ほんの少しでいいんです。
- 朝、ゆっくりお茶を飲む時間(5分)
- お風呂でリラックスする時間(15分)
- 寝る前の読書やストレッチの時間(10分)
こんな小さな時間の積み重ねが、体を守ることにつながるんですよ。
季節の変わり目を乗り切る自律神経ケアも参考にしてみてくださいね。
スタジオシュカの季節養生サポート
ここまで、自分でできる養生法をご紹介してきました。
でも、「一人で続けるのは難しい…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
スタジオシュカでは、そんなあなたをサポートさせていただいています。
一人ひとりの体質に合わせた養生指導
東洋医学では、体質を細かく分類します。
- 気虚(ききょ):エネルギー不足タイプ
- 血虚(けっきょ):血の不足タイプ
- 陽虚(ようきょ):体が冷えやすいタイプ
- 陰虚(いんきょ):体の潤いが不足しているタイプ
それぞれの体質によって、適した養生法は変わってくるんです。
当院では、まずあなたの体質を丁寧に診させていただき、最適な養生法をアドバイスさせていただいています。
一般的に言われている方法が、あなたに合うとは限りません。
あなただけの、オーダーメイドの養生プランを一緒に考えていきましょう。
鍼灸で「腎」のエネルギーをサポート
鍼灸施術では、「腎」のエネルギーをサポートするアプローチを行います。
主に使用するツボ:
- 腎兪(じんゆ)
- 太渓(たいけい)
- 関元(かんげん)
- 命門(めいもん)
これらのツボに鍼やお灸でアプローチすることで、体のリラックスや温かさを感じる方が多いです。
施術中に「体がポカポカしてきた」「深いリラックスを感じた」というお声をよくいただきます。
ただし、施術効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。
あくまで、体が本来持っている力をサポートするお手伝いをさせていただくものです。
体の巡りをサポートする東洋医学的アプローチも合わせてご覧ください。
継続しやすい、無理のない養生プラン
「毎日通わないといけないんじゃ…」
そんな心配は不要です!
当院では、あなたのライフスタイルに合わせた、無理のないプランをご提案しています。
忙しい方でも続けられる工夫
- 施術の頻度は、月2回程度からOK
- 自宅でできるセルフケアを丁寧に指導
- LINEで日常の養生についてアドバイス
- 疑問や不安があれば、いつでも相談できる体制
大切なのは「継続すること」。
無理なく、あなたのペースで続けられる方法を一緒に見つけていきましょう。
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:11月は「蓄える」を意識して、冬を元気に迎えよう
ここまで、11月から始める冬に向けた養生法をご紹介してきました。
最後に、大切なポイントをおさらいしましょう!
11月の養生、5つのポイント
- 早寝早起きで「陽気」を温存する
- 体を温める食材で「腎」をサポートする
- 無理な運動は避け、ゆったりとした動きを
- 「腎兪」「太渓」のツボで腎のエネルギーケア
- 「休むことは悪いことじゃない」マインドセット
どれも今日から始められる簡単な方法ばかりです。
全部を完璧にやろうとしなくて大丈夫ですよ。
できることから、少しずつ始めてみてください。
東洋医学では、冬は「蔵(しまう)」の季節。
エネルギーを蓄えて、春に向けて力を温存する大切な時期です。
11月からしっかりと準備を始めることで、寒い冬も元気に乗り越えられますよ。
自分の体を大切にすること。
それは、自分自身を大切にすることと同じです。
無理をせず、自分のペースで、冬支度を始めていきましょう!
もし一人で続けるのが難しいと感じたら、いつでもスタジオシュカにご相談くださいね。
あなたの体質に合わせた養生法を、一緒に見つけていきましょう。
冬を元気に迎えるために、今日から「蓄える養生」を始めませんか?
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。鍼灸施術は医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
参考文献:
厚生労働省「睡眠対策」
日本東洋医学会
