夏バテ防止の水分補給術!体の熱を上手に逃がす飲み物選び【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-08-14 季節の養生法
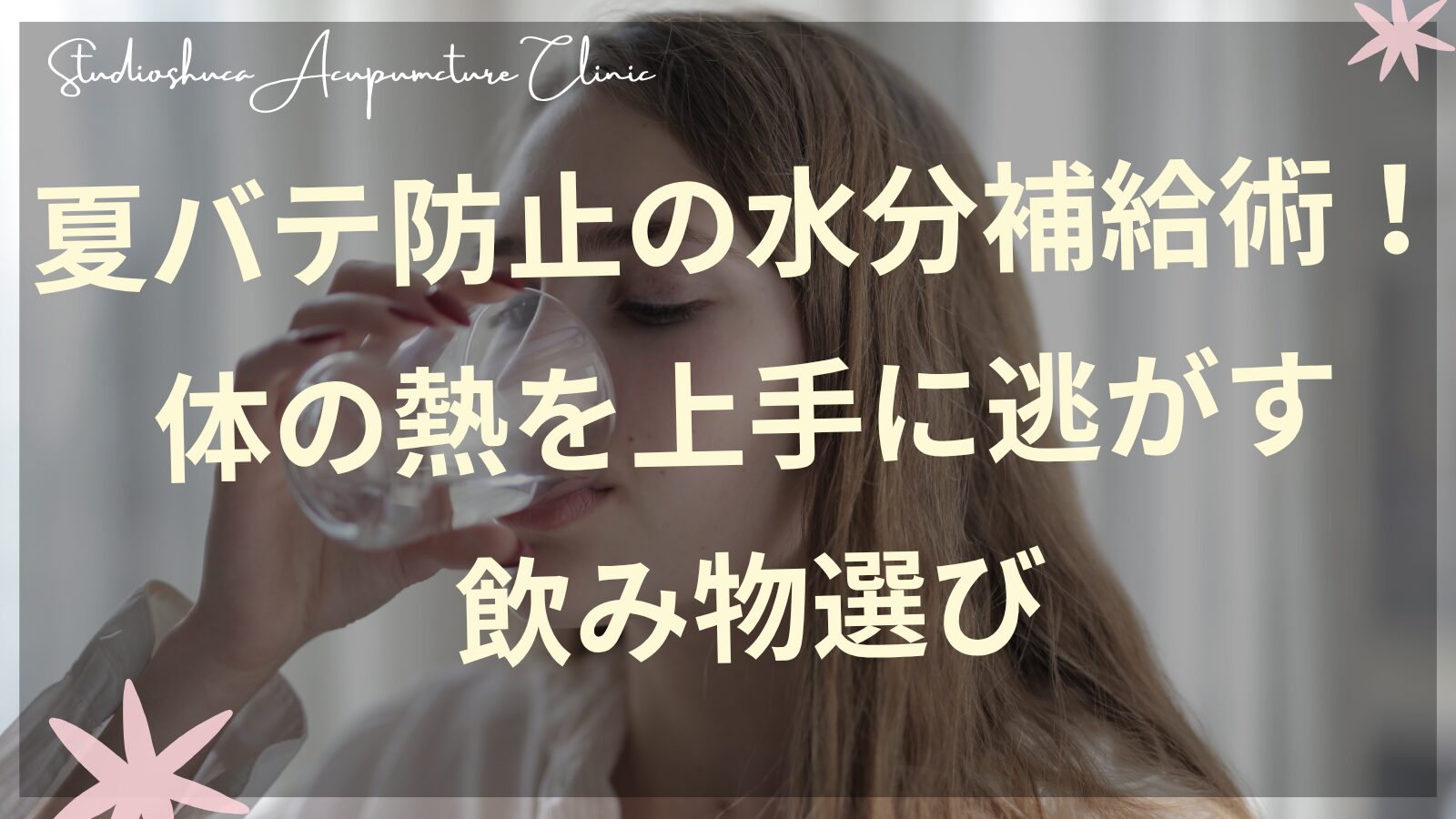
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
「水分はしっかり摂っているのに、なんだかだるさが続く…」
「冷たい飲み物ばかり飲んでいて、お腹の調子が悪い」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
実は、夏バテ防止には水分補給の「量」だけでなく、「質」と「タイミング」がとても大切なんです。
東洋医学の観点から見ると、体の熱を効率的に逃がす水分補給には、ちょっとしたコツがあります。
この記事では、30代・40代・50代の女性の皆さまに向けて、体質に合わせた飲み物選びと、効果的な水分補給のタイミングをご紹介いたします。
正しい知識を身につけて、この夏を元気に乗り切りましょう!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
なぜ水分を摂っても夏バテが続くのか?
「水分はちゃんと摂っているのに、疲れやだるさが取れない」
そんな経験はありませんか?
一般的な水分補給の落とし穴
実は、多くの方が陥りがちな水分補給の落とし穴があります。
- 冷たい飲み物の過剰摂取による胃腸機能の低下
- 一度に大量の水分を摂取することによる体への負担
- 糖分の多い飲み物による血糖値の急激な変化
- 電解質(ミネラル)不足による体内バランスの乱れ
一般的に、冷たい飲み物を摂りすぎると、胃腸が冷えて消化機能が低下するとされています。
すると、せっかく摂った水分や栄養素が、体全体に行き渡りにくくなってしまうんです。
体の熱がこもる仕組みと水分の関係
東洋医学では、体の中に熱がこもる状態を「内熱」と呼びます。
内熱は以下のような原因で起こると考えられています:
- ストレスや睡眠不足による気の巡りの悪化
- 辛い物や油っこい食べ物の摂りすぎ
- 水分代謝の低下
- 血の巡りの停滞
この状態では、いくら水分を摂っても体の熱が効率的に放出されず、夏バテの症状が続いてしまうのです。
東洋医学から見た夏の水分補給の背景
東洋医学において、夏は「心(しん)」の季節とされています。
心は、血液循環や精神活動を司る重要な臓器です。
「心」の季節における水分代謝のサポート
夏の暑さは、心に負担をかけやすいと考えられています。
一般的に、以下のような影響があるとされています:
- 血液循環への負担増加
- 精神的な不安定さ(イライラ、不眠など)
- 汗による体液の消耗
- 体温調節機能への負荷
そのため、心をサポートする水分補給が重要になってくるんです。
気・血・水のバランスと夏の不調
東洋医学では、体内を巡る「気・血・水」のバランスが健康の鍵とされています。
気の巡り:エネルギーの流れ
夏の暑さによって気の巡りが乱れると、疲労感や集中力の低下が起こりやすくなります。
血の巡り:栄養と酸素の運搬
暑さによる血管の拡張や発汗で、血の巡りに影響が出ることがあります。
水の巡り:体液の代謝
発汗量の増加により、体内の水分バランスが崩れやすくなります。
体質別に見る水分補給の違い
東洋医学では、一人ひとりの体質に合わせたアプローチを大切にします。
水分補給においても、体質による違いがあるとされています。
熱がこもりやすい体質の方:
- のぼせやすい
- 汗をかきやすい
- イライラしやすい
冷えやすい体質の方:
- 手足が冷たくなりやすい
- 胃腸が弱い
- 疲れやすい
それぞれの体質に合わせた水分補給法をお伝えしていきますね。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
体の熱を上手に逃がす飲み物選び
いよいよ、具体的な飲み物選びのコツをご紹介します!
温度や成分を意識することで、より効果的な水分補給ができるようになります。
温度別水分補給法(常温・温・冷の使い分け)
【常温(20-25℃)】基本の水分補給
胃腸に負担をかけにくく、吸収されやすいとされています。
- 起床時の1杯
- 食事の30分前
- 運動前後
【温かい飲み物(40-60℃)】内臓を労わる
胃腸を温めて、消化機能をサポートします。
- 朝の白湯
- 食後の温かいお茶
- 就寝前のハーブティー
【冷たい飲み物(5-15℃)】体温調節のサポート
体の熱を取る効果が期待できますが、適量が大切です。
- 運動直後の短時間
- 体が非常に熱くなった時
- 1日1-2回程度に留める
東洋医学的に体を冷やすとされる食材を使った飲み物
東洋医学では、食材にはそれぞれ「性質」があるとされています。
体の熱を冷ますとされる食材を使った飲み物をご紹介します。
きゅうり水
きゅうりは体を冷やす性質があるとされています。
- きゅうり 1/2本をスライス
- 水 500mlに一晩漬ける
- レモンを加えるとさらに爽やか
緑茶
緑茶に含まれるカテキンは、体の熱を取る効果があるとされています。
- 70-80℃のお湯で淹れる
- カフェインが気になる方は薄めに
- 1日2-3杯が目安
麦茶
ノンカフェインで体を冷やす性質があります。
- 水出しで作る
- ミネラルが豊富
- お子様にも安心
時間帯別最適水分補給スケジュール
効果的な水分補給には、タイミングも重要です。
【朝(6:00-9:00)】
- 起床時:白湯 コップ1杯
- 朝食前:常温の水 コップ1杯
- 朝食時:温かいお茶 適量
【昼(9:00-15:00)】
- 午前中:常温の水を少しずつ
- 昼食前:常温の水 コップ1杯
- 午後:緑茶や麦茶 適量
【夕方(15:00-18:00)】
- おやつ時間:ハーブティー
- 夕食前:常温の水 コップ1杯
【夜(18:00-22:00)】
- 夕食時:温かいお茶 適量
- 就寝1時間前:白湯 コップ半分
詳しい自律神経の整え方については、夏の自律神経を整える方法の記事も参考にしてくださいね。
夏バテ防止をサポートする薬膳的水分補給
続いて、あなたの体質に合わせた水分補給法をご紹介します。
まずは簡単な体質チェックから始めてみましょう!
体質チェック:あなたは熱がこもりやすい?冷えやすい?
以下の項目で、当てはまるものにチェックを入れてみてください。
【Aタイプ:熱がこもりやすい体質】
【Bタイプ:冷えやすい体質】
Aタイプの項目が多い方は「熱がこもりやすい体質」、Bタイプが多い方は「冷えやすい体質」の可能性があります。
ただし、個人差がありますので、参考程度にお考えくださいね。
体質別おすすめ飲み物レシピ
【熱がこもりやすい体質の方向け】
✨ スイカジュース
- スイカ 200g
- レモン汁 小さじ1
- ミントの葉 2-3枚
スイカは体の熱を取るとされる代表的な食材です。
✨ トマトとセロリのジュース
- トマト 1個
- セロリ 1/2本
- 塩 少々
どちらも体を冷やす性質があるとされています。
【冷えやすい体質の方向け】
✨ 生姜はちみつ湯
- 生姜 薄切り2-3枚
- はちみつ 小さじ1
- お湯 200ml
生姜は体を温める性質があり、胃腸をサポートします。
✨ ナツメとクコの実茶
- ナツメ 2-3個
- クコの実 大さじ1
- お湯 300ml
どちらも気血を補うとされる薬膳素材です。
ミネラル・電解質の効果的な補給方法
汗とともに失われるミネラルの補給も大切です。
自家製スポーツドリンク
- 水 500ml
- 塩 小さじ1/4
- 砂糖 大さじ2
- レモン汁 大さじ1
天然塩を使った水分補給
- 常温の水に天然塩をひとつまみ
- 梅干しと一緒に水分補給
- 昆布茶で自然なミネラル補給
冷房による冷えが気になる方は、冷房冷えを防ぐ温活習慣の記事も併せてご覧ください。
鍼灸でサポートする夏の水分代謝ケア
ここからは、鍼灸師の視点から水分代謝のサポートについてお話しします。
セルフケアと合わせて、より効果的な体調管理を目指しましょう。
水分代謝に関わるとされる経絡とツボ
東洋医学では、体内の水分代謝には特定の経絡とツボが関わっているとされています。
【三陰交(さんいんこう)】
内くるぶしから指4本分上の、骨の内側
- 水分代謝のサポートに期待
- 女性特有の不調にも関連するとされる
- 優しく押して刺激
【太谿(たいけい)】
内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ
- 腎の働きをサポートするとされる
- 水分代謝に関連
- ゆっくりと深く押す
【湧泉(ゆうせん)】
足の裏、土踏まずの上の方のくぼみ
- 全身のエネルギーのサポート
- 体の熱を下に流すとされる
- 青竹踏みなどでも刺激可能
詳しいツボの刺激方法については、関元ツボで妊活サポートの記事も参考にしてくださいね。
スタジオシュカでの夏の季節養生サポート
当院では、一人ひとりの体質に合わせた季節養生のサポートを行っています。
体質診断とカウンセリング
- 詳しい問診で体質を把握
- 生活習慣のヒアリング
- 個別の養生プランをご提案
鍼灸による体質改善サポート
- 水分代謝に関わるツボへのアプローチ
- 自律神経のバランス調整をサポート
- 体の巡りを整えるお手伝い
セルフケア指導
- 体質に合った水分補給法
- 効果的なツボ刺激の方法
- 日常生活での注意点
夜中に目が覚めてしまう方は、夏の不眠対策の記事もチェックしてみてください。
セルフケアと専門ケアの組み合わせ
セルフケアと専門的なケアを組み合わせることで、より効果的な体調管理が期待できます。
セルフケアの範囲
- 日常的な水分補給
- 軽いツボ刺激
- 生活習慣の改善
専門ケアが適している場合
- 症状が長期間続く時
- 体質改善をしっかりと行いたい時
- 個別のアドバイスが必要な時
内臓の冷えが気になる方は、内臓冷え改善法の記事も参考にしてください。
厚生労働省でも熱中症予防について詳しい情報を提供していますので、厚生労働省 熱中症予防情報も併せてご確認ください。
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:この夏を元気に乗り切るために
今回は、夏バテ防止のための水分補給術についてお話ししました。
大切なポイントをもう一度おさらいしましょう:
- 水分補給は「量」だけでなく「質」と「タイミング」が重要
- 体質に合わせた飲み物選びを心がける
- 温度を使い分けて効果的な水分補給を
- ミネラル補給も忘れずに
- セルフケアと専門ケアを上手に組み合わせる
正しい水分補給法を身につけることで、夏バテ知らずの元気な毎日を過ごすことができます。
でも、一人で続けるのはなかなか難しいもの…
そんな時は、遠慮なく専門家にご相談くださいね。
あなたの体質に合わせた、オーダーメイドの季節養生プランをご提案いたします。
この夏を、健やかで快適に過ごしていただけるよう、心から応援しています!
※個人の体質により体験には個人差があります
※施術効果を保証するものではありません
※医療行為の代替ではありません
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
