下半身の巡りを整える東洋医学ケア!冬の冷え対策は11月から【柏駅からバスで5分、徒歩10分の鍼灸院】
2025-11-20 季節の養生法
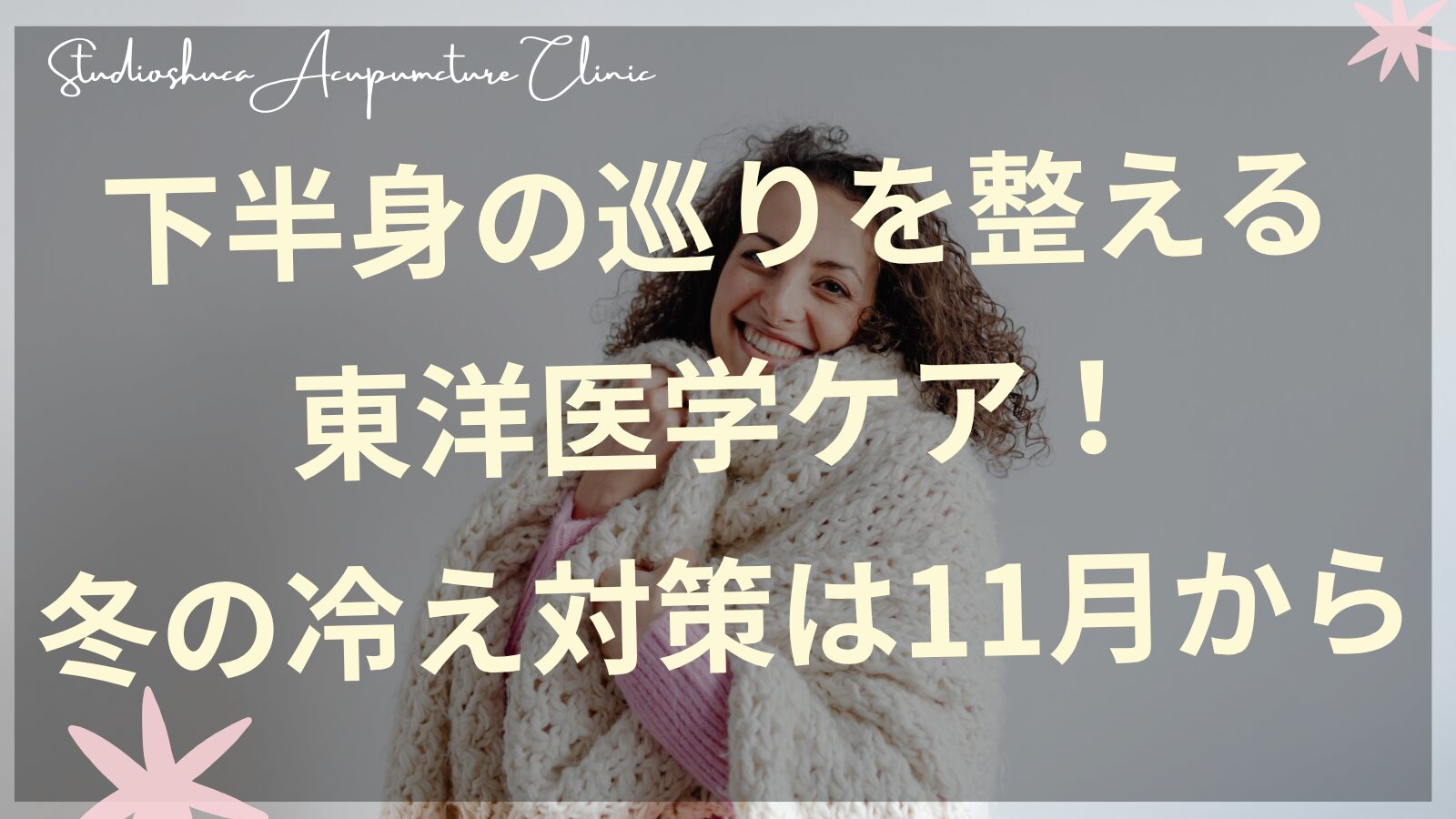
東洋医学から見た下半身の冷えの背景
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
11月に入り、朝晩の冷え込みが増してきましたね。この時期になると「足先が冷たくて眠れない」「夕方になると足がむくんでパンパン」といったお悩みをよく伺います。
実は、冬本番になってから慌てて対策するよりも、今のうちに下半身の巡りを整えておくことが、冷えに負けない体づくりのポイントなんです!
「気血水」の巡りと下半身の関係
東洋医学では、体を巡る3つの要素「気(き)・血(けつ)・水(すい)」のバランスが健康の鍵と考えます。
下半身は体の末端にあるため、この3つの巡りが届きにくい部位なんですよ。
特に重力の影響を受けやすく:
- 血液や水分が溜まりやすい
- むくみと冷えが同時に起こりやすい
- 心臓から遠いため温かい血液が届きにくい
東洋医学では、「腎(じん)」と「脾(ひ)」のエネルギー不足が、下半身の冷えにつながると言われています。腎は生命力や生殖機能を、脾は消化吸収と水分代謝をサポートすると考えられているんです。
気・血・水から見る妊娠力!体の巡りをサポートする東洋医学的アプローチ
11月に下半身ケアを始める理由
11月は秋から冬への大切な切り替え時期です!
東洋医学の五行説では、冬は「腎」の季節とされています。腎のエネルギーは生命力の源であり、冷えに最も影響を受けやすいと言われているんですよ。
11月から始める3つのメリット:
- 体が「蓄える」モードに切り替わる時期だから効果的
- 冬本番の厳しい冷えに備えられる
- 早めのケアで根本的な体質サポートにつながる
予防医学の観点からも、症状が強くなる前のケアがとても大切なんです♪
下半身の冷えが全身に与える影響
「足が冷たいだけ」と思っていませんか?実は下半身の冷えは、全身にさまざまな影響を与えることが知られています。
下半身の冷えと関連する不調:
- 婦人科系の悩み:生理痛、生理不順、妊活への影響
- 睡眠の質:足が冷たくて寝付けない、夜中に目が覚める
- 免疫力:風邪をひきやすくなる、膀胱炎になりやすい
- 疲労感:全身のだるさ、朝起きるのがつらい
下半身を温めることは、全身の健康をサポートする第一歩なんですよ✨
下半身の冷えでお悩みの方へ
足先の冷えや下半身のむくみでお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質をみながら、下半身の巡りをサポートする施術を行っています。
お灸やツボ刺激で、冬に向けた体づくりのお手伝いをさせていただきます。
下半身の巡りを整える3つの重要なツボ
ここからは、自宅でケアできる下半身の巡りをサポートする代表的なツボをご紹介しますね!
三陰交(さんいんこう)- 婦人科系ケアの代表的なツボ
ツボの位置:
内くるぶしの頂点から、指4本分上がったところ。骨の後ろ側のくぼみです。
東洋医学的な意味:
三陰交は、脾経・肝経・腎経という3つの重要な経絡が交わる特別なツボなんです✨
この3つの経絡は、女性の体にとってとても大切な役割を持っています:
- 脾経:消化吸収と水分代謝をサポート
- 肝経:血液の貯蔵と巡りをサポート
- 腎経:生命力と生殖機能をサポート
そのため、婦人科系の不調、下半身の冷え、むくみのケアに広く用いられているんですよ。
⚠️ 注意点:妊娠中の方は、このツボへの刺激を控えてください。妊活中の方は問題ありませんが、妊娠が確定したら専門家にご相談くださいね。
太谿(たいけい)- 腎のエネルギーをサポート
ツボの位置:
内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみです。押すと脈を感じることができますよ。
東洋医学的な意味:
太谿は腎経の「原穴(げんけつ)」と呼ばれる特別なツボなんです。
原穴とは、その経絡の根本的なエネルギーが集まる場所のこと。腎のエネルギーを補うために重要とされています。
期待されるサポート:
- 下半身の冷え
- 腰のだるさや痛み
- 頻尿や夜間頻尿
- 疲労感
- 生命力のサポート
冬に向けて腎のエネルギーを蓄えるのに、とても適したツボなんですよ♪
湧泉(ゆうせん)- 生命力の源
ツボの位置:
足裏の土踏まずより少し指側、足の指を曲げた時にできるくぼみです。
東洋医学的な意味:
「生命の泉が湧く」という素敵な名前を持つツボなんです✨
湧泉は腎経の始まりのツボで、全身のエネルギー循環をサポートすると言われています。
期待されるサポート:
- 全身の疲労回復
- 不眠の改善サポート
- 足の冷え
- ストレス軽減
- 気力の充実
足裏なので、台座灸を使ったお灸がおすすめですよ!
子宮を温める関元ツボの正しい刺激法!妊娠力アップのセルフケア術
冷えやむくみ解消に!自宅で簡単にできるツボ押し&鍼灸で血行促進
自宅でできるお灸の正しい使い方
「お灸って難しそう…」と思っていませんか?実は、最近のお灸はとても簡単で安全なんですよ😊
初心者でも安心な台座灸の選び方
ドラッグストアで購入できる台座灸は、初心者の方にぴったりです!
台座灸の種類と選び方:
温度レベル
- ソフトタイプ:温度が低く、お灸初心者の方におすすめ
- レギュラータイプ:程よい温かさ、慣れてきたらこちら
- ハードタイプ:しっかり温まりたい方向け
最初はソフトタイプから始めて、徐々に慣れていくのがおすすめですよ♪
その他の選択肢:
- 煙の出ないタイプ:マンションやアパートでも安心
- 香り付き:ラベンダーなどのアロマ効果も
- 火を使わないタイプ:貼るだけで温まる、外出先でも使える
市販のお灸と専門家が使うお灸の違い:
市販のお灸は安全性を重視して作られているため、専門家が使うお灸よりも温度が低めに設定されています。その分、継続的に使うことで体質サポートにつながっていきますよ。
お灸を据える最適なタイミング
お灸の効果を最大限に感じるために、タイミングも大切なんです!
おすすめのタイミング:
① 入浴後(最もおすすめ!)
- 体が温まって血行が良くなっている
- リラックスしているので効果的
- 入浴後30分以内がベスト
② 朝起きた時
- 1日の始まりに体を温める
- 習慣化しやすい
- 朝の冷えを和らげる
③ 就寝前
- 体を温めて安眠をサポート
- 1日の疲れをリセット
避けた方が良いタイミング:
- 食後すぐ(消化にエネルギーが必要なため)
- 飲酒後(血行が促進されすぎる)
- 発熱時や体調が悪い時
リラックスできる環境を整えて、ゆったりとした気持ちで行うことが大切ですよ✨
お灸の温度と時間の目安
基本的な使い方:
温度の感じ方
- じんわりと温かさを感じる程度が適切
- 熱すぎると感じたらすぐに外してOK
- 我慢する必要はありません
時間の目安
- 台座灸は通常5〜10分で自然に消える
- 1つのツボに1個ずつでOK
- 1日1回、継続することが大切
効果的な使い方のコツ:
- 最初は三陰交だけでもOK
- 慣れてきたら2〜3か所に増やす
- 左右両方のツボに据える
- 週3〜4回から始めて、習慣化する
⚠️ 安全に使うための注意点:
- 顔や粘膜の近くには使わない
- 同じ場所に連続して据えない(最低2時間空ける)
- 火傷の跡が残ったら使用を中止
- 不安な場合は専門家に相談
詳しい使い方は、各製品の説明書もよく読んでくださいね😊
お灸について詳しく知りたい方は、厚生労働省の統合医療情報発信サイトもご参考になりますよ。
一人ひとりに合わせた下半身ケアを
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたの体質に合わせた下半身の巡りケアをご提案いたします。
セルフケアと併用することで、より効果的に冷え対策ができます。
下半身の巡りをサポートする生活習慣
お灸と合わせて、日々の生活習慣を見直すことで、より効果的に下半身の巡りをサポートできますよ!
朝の白湯習慣で内臓から温める
朝起きてすぐの白湯は、東洋医学でも推奨されている温活習慣なんです✨
白湯の作り方:
- 水を沸騰させる(やかんで5分程度)
- 50度くらいまで冷ます
- すするようにゆっくり飲む
なぜ白湯が良いの?
東洋医学では、「脾胃(ひい)」と呼ばれる消化器系を温めることが、全身の巡りの鍵と考えられています。
- 内臓を優しく温める
- 1日の気血の巡りをサポート
- 消化機能の活性化
- 老廃物の排出を促す
飲むタイミングとコツ:
- 起床後、歯磨きの前がベスト
- コップ1杯(150〜200ml)をゆっくりと
- 5〜10分かけて飲む
- 体が温まるのを感じながら
冷たい水ではなく温かい白湯を飲むことで、内臓を冷やさずに体を目覚めさせることができるんですよ♪
寝る前の足湯で1日の疲れをリセット
足湯は、手軽にできて効果的な温活方法です!
効果的な足湯のやり方:
温度
- 38〜40度のぬるめのお湯
- 熱すぎると体が疲れる
- じんわり温まる程度がベスト
時間
- 10〜15分が目安
- 額に汗がうっすら出るくらい
- 長すぎると逆効果
足湯の深さ
- くるぶしまで浸かる
- ふくらはぎまで浸かるとさらに効果的
アレンジで効果アップ:
- 生姜:すりおろしたものを入れる(体を温める)
- 塩:天然塩をひとつまみ(発汗を促す)
- ラベンダー精油:2〜3滴(リラックス効果)
足湯後は、すぐに靴下を履いて保温することも忘れずに!
腰回りを冷やさない服装のコツ
どんなに温めても、服装で冷やしていては効果が半減してしまいます💦
3つの「首」を温める:
東洋医学では、「首・手首・足首」を温めることが冷え対策の基本と言われています。
① 腹巻き
- 仙骨周りを温めることで下半身全体が温まる
- 薄手のものなら服の下に着けても目立たない
- 就寝時も着用OK
② レッグウォーマー
- 足首を温めると全身が温まる
- ふくらはぎまであるものがおすすめ
- 締め付けないものを選ぶ
③ 靴下の重ね履き
- シルク→綿→ウールの順がおすすめ
- 締め付けすぎは逆効果
- 就寝時は緩めのものを
インナーの素材選び:
- 天然繊維(綿・シルク・ウール)がおすすめ
- 化繊は静電気で体を冷やすことも
- 肌に直接触れるものは特に重要
避けたい服装:
- タイトすぎるボトムス(血行を妨げる)
- 素足にパンプス
- 薄手のストッキングのみ
重ね着よりも、首・手首・足首を温めることを意識してみてくださいね😊
下半身の巡りを整える食材選び
体を内側から温めるには、食事もとても大切なんですよ!
体を温める根菜類と黒い食材
東洋医学では、食材にも「温める性質」と「冷やす性質」があると考えられています。
積極的に摂りたい温める食材:
根菜類
- 大根:消化をサポート、体を温める
- ごぼう:腸内環境を整える
- 人参:血を補うとされる
- かぼちゃ:脾胃を温める
- れんこん:肺を潤す
土の中で育つ根菜類は、体を温める性質があると言われているんですよ✨
黒い食材(腎を補う)
- 黒豆:腎のエネルギーを補う
- 黒ごま:血を補い、腸を潤す
- ひじき:ミネラル豊富
- 黒米:栄養価が高い
- 黒きくらげ:血液サラサラに
東洋医学では、黒い食材は「腎」を補うと言われ、冬に特におすすめなんです。
温性の食材・スパイス
- 生姜:体を芯から温める代表選手
- ネギ:発汗を促し、体を温める
- ニンニク:気を巡らせる
- シナモン:腎陽を補う
- 八角:体を温め、気の巡りをサポート
避けたい体を冷やす食べ物・飲み物
せっかく温めても、体を冷やす食べ物を摂っていては台無しです💦
控えめにしたい食べ物・飲み物:
冷たいもの
- 冷たい飲み物(アイスコーヒー、冷たい水)
- 生野菜(特に冬は温野菜がおすすめ)
- アイスクリーム、氷菓子
南国のフルーツ
- バナナ、マンゴー、パイナップル
- グレープフルーツ、キウイ
- 体を冷やす性質があると言われる
精製された糖質
- 白砂糖たっぷりのお菓子
- 清涼飲料水
- 血糖値の乱れで体が冷える
その他
- アルコールの飲みすぎ(一時的に温まるが後で冷える)
- カフェインの摂りすぎ(体を冷やす)
- 小麦製品の摂りすぎ(体を冷やすと言われる)
完全に避ける必要はありませんが、摂りすぎには注意してくださいね。
簡単に作れる温活レシピ
忙しい毎日でも作れる、簡単な温活レシピをご紹介します!
① 根菜たっぷりの豚汁
- 大根、人参、ごぼう、里芋などの根菜をたっぷり
- 豚肉でたんぱく質も補給
- 味噌で体を温める
- 生姜をすりおろして入れるとさらに◎
② 黒ごまと生姜の温豆乳
- 豆乳を温める(沸騰させない)
- 黒ごまペーストを大さじ1
- すりおろし生姜を少々
- ハチミツで味を調える
③ かぼちゃとひじきの煮物
- かぼちゃの甘みとひじきの旨み
- 作り置きOK
- お弁当にも
④ れんこんのきんぴら
- 食物繊維たっぷり
- ごま油で炒めて香ばしく
- 唐辛子を少し入れると体が温まる
調理法も、「煮る・蒸す・焼く」など、火を通す方法がおすすめです♪
ふくらはぎと股関節のセルフケア
食事や生活習慣と合わせて、セルフマッサージも取り入れましょう!
ふくらはぎマッサージの具体的な方法
ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれるほど、血液循環にとって重要な部位なんですよ。
基本のマッサージ方法:
準備
- お風呂上がりなど、体が温まっている時に
- オイルやクリームを使うとスムーズ
- リラックスできる姿勢で座る
手順
- アキレス腱をほぐす:親指と人差し指でつまむように
- ふくらはぎの中央を押す:両手で包み込むように、足首からひざ裏へ
- ひざ裏のリンパを流す:軽く押すように
- 全体を揉みほぐす:痛気持ちいい程度の強さで
時間の目安
- 片足3〜5分ずつ
- 左右とも行う
- 毎日続けることが大切
ポイント
- 必ず下から上へ(心臓に向かって)
- 強く押しすぎない
- 呼吸を止めない
- 痛みがある場合は無理しない
ふくらはぎの筋肉を動かすことで、下半身に溜まった血液や水分を心臓に戻すサポートができるんです✨
股関節ストレッチで巡りをサポート
股関節周りが硬いと、下半身の巡りが滞りやすくなると言われています。
基本の股関節ストレッチ:
① あぐらストレッチ
- 床に座り、両足の裏を合わせる
- かかとをできるだけ体に近づける
- 膝を床に近づけるように優しく押す
- 背筋を伸ばしたまま30秒キープ
- 深呼吸を忘れずに
② 開脚ストレッチ(無理のない範囲で)
- 足を開いて座る
- 片方の足に体を倒す
- 反対側も同様に
- 最後に中央に倒す
③ 仰向けで膝倒し
- 仰向けに寝て膝を立てる
- 両膝を左右にゆっくり倒す
- 腰をひねるイメージで
- 左右10回ずつ
注意点:
- 無理に伸ばさない(痛気持ちいい程度)
- 反動をつけない
- 呼吸を止めない
- 毎日少しずつ続ける
股関節が柔らかくなると、下半身全体の巡りがスムーズになりますよ♪
デスクワーク中にできる簡単エクササイズ
座りっぱなしは下半身の巡りを滞らせる大きな原因です💦
オフィスでできる簡単エクササイズ:
① かかと上げ下げ
- 座ったまま、かかとを上げ下げ
- ふくらはぎの筋肉を意識して
- 20回を1セット、1時間に1回
② 足首回し
- 足首をゆっくり回す
- 時計回り10回、反時計回り10回
- 両足行う
③ 足指グーパー
- 足の指をぎゅっと握る(グー)
- 大きく広げる(パー)
- 10回繰り返す
④ 立ち上がって歩く
- 1時間に1回は立ち上がる
- トイレ休憩を活用
- コピー機まで歩く
- 階段を使う
⑤ 椅子に座ったままストレッチ
- 片足を伸ばして足首を曲げる
- ふくらはぎが伸びるのを感じる
- 左右15秒ずつ
こまめに動くことで、下半身の巡りを維持できますよ😊
妊活中の冷え性を根本改善!足首から始める血流アップの温めテクニック
鍼灸院での下半身の巡りケア
セルフケアだけでは限界を感じている方へ、鍼灸院でのサポート内容をご紹介しますね。
体質診断に基づいたツボ選び
鍼灸院では、東洋医学独自の診断方法で、一人ひとりの体質を見極めます。
東洋医学の問診方法:
① 舌診(ぜっしん)
- 舌の色、形、苔の状態を見る
- 体内の水分バランスや熱の状態が分かる
② 脈診(みゃくしん)
- 手首の脈を触れて診る
- 気血の状態、臓器の働きを診断
③ 腹診(ふくしん)
- お腹の状態を触診
- 冷えや張り、硬さをチェック
④ 問診
- 生活習慣、食事、睡眠
- 症状の詳細
- 既往歴
冷えのタイプ別アプローチ:
東洋医学では、同じ「冷え」でも原因によってアプローチが変わります。
- 気虚タイプ:エネルギー不足で体が温まらない
- 血虚タイプ:血が不足して栄養が届かない
- 陽虚タイプ:体を温める力が弱い
- 気滞タイプ:巡りが滞って冷える
このように体質を見極めて、最適なツボを選ぶことが専門家の役割なんです✨
お灸と鍼を組み合わせた施術
鍼灸院では、お灸と鍼を組み合わせることで、より効果的なサポートが可能です。
鍼の役割:
- 気の流れをサポート
- 滞った経絡を通す
- 深部の筋肉にアプローチ
- 即効性が期待できる
お灸の役割:
- 体を温める
- 陽気を補う
- じんわりと深部まで温める
- 継続的な効果
市販のお灸と専門的なお灸の違い:
市販のお灸
- 安全性重視
- 温度が一定
- セルフケア向け
鍼灸院のお灸
- 種類が豊富(棒灸、箱灸、透熱灸など)
- 温度調整が細かくできる
- 体質に合わせて使い分け
- より深部まで温められる
全身のバランスを整える:
下半身の冷えだけでなく、全身のバランスを見ながら施術を行います。
- 自律神経のバランス調整
- ホルモンバランスのサポート
- 睡眠の質の向上
- ストレス軽減
リラックス効果で、心身ともに整っていくことが期待できますよ😊
鍼灸について詳しく知りたい方は、公益社団法人 日本鍼灸師会のサイトもご参考になります。
セルフケアとの併用で期待できること
鍼灸院での施術とセルフケアを併用することで、より良い結果が期待できます!
併用のメリット:
① 定期的な施術で体質の土台づくり
- 月2〜4回の施術で体質をサポート
- プロの目で体の変化をチェック
- その時の状態に合わせた施術
② 日々のセルフケアで維持・向上
- 習ったツボを自宅でケア
- 生活習慣の改善を継続
- 自分の体と向き合う時間
③ 季節の変わり目の集中ケア
- 11月は特に重要な時期
- 冬に向けた体づくりのサポート
- 不調が出る前の予防ケア
継続的なサポートの重要性:
体質改善は一朝一夕にはいきません。でも、継続することで少しずつ変化を感じられるようになります。
- 最初の1〜2か月:体が慣れる期間
- 3〜6か月:変化を実感し始める
- 6か月以上:体質が安定してくる
「個人差があります」が、多くの方が2〜4週間程度で何らかの変化を感じられていますよ♪
よくあるご質問
ここまで読んでいただいて、疑問に思われることもあるかと思います。よくあるご質問にお答えしますね!
どのくらいの期間で変化を感じられますか?
個人差がありますが、目安をお伝えします:
セルフケアの場合
- 1〜2週間:足が少し温かくなってきた感じ
- 1か月:寝つきが良くなった、朝の冷えが和らいだ
- 2〜3か月:体質の変化を実感、冷えにくくなった
鍼灸院での施術を併用した場合
- 施術直後:体がポカポカする、リラックス感
- 2〜4週間:冷えが和らぐ、むくみが減る
- 2〜3か月:体質が変わってきたと実感
大切なポイント:
- 即効性よりも根本的なケアを重視
- 継続することが何より大切
- 焦らず、ゆっくりと体と向き合う
- 小さな変化を喜ぶ心の余裕を
「効果を保証するものではありません」が、継続することで多くの方が変化を感じられています😊
妊活中でもお灸は大丈夫ですか?
基本的には問題ありません!
むしろ、妊活中の方にこそお灸をおすすめしたいんです✨
妊活中のお灸のメリット:
- 体を温めて妊娠しやすい環境づくりをサポート
- 子宮や卵巣周りの巡りをサポート
- リラックス効果でストレス軽減
- ホルモンバランスをサポート
⚠️ 注意点:
妊娠前(妊活中)
- 基本的にどのツボも使用OK
- 三陰交、太谿、湧泉など積極的に
妊娠が確定したら
- 三陰交は避ける(陣痛を促すツボ)
- 強い刺激は避ける
- 専門家に相談してから
こんな時は控えめに:
- 体調が悪い時
- 出血がある時
- 医師から安静を指示されている時
心配な場合は、妊活に詳しい鍼灸師に相談してくださいね♪
市販のお灸と鍼灸院のお灸の違いは?
どちらにも良さがあります!
市販のお灸(セルフケア用)
メリット
- 自宅で手軽にできる
- 安全性が高い
- コストが安い
- 自分のペースで続けられる
デメリット
- 温度が低めに設定されている
- 種類が限られる
- 正しいツボの位置が分かりにくい
- 効果の実感に時間がかかることも
鍼灸院のお灸(専門的)
メリット
- 体質に合わせたツボ選び
- 種類が豊富(棒灸、箱灸、透熱灸など)
- 温度調整が細かい
- 深部まで温められる
- プロの技術と知識
デメリット
- 通院の手間
- コストがかかる
- 予約が必要
おすすめの使い分け:
- 普段のケア:市販のお灸でセルフケア
- 集中ケア:月2〜4回、鍼灸院で本格的な施術
- 体質診断:最初は鍼灸院で自分の体質を知る
- 継続:鍼灸院で習ったツボを自宅でもケア
両方を上手に組み合わせることで、効果的なケアができますよ😊
専門家と一緒に冬の冷え対策を始めませんか?
下半身の冷え対策は、早めのケアが大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた冷え対策プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:冬に向けた下半身ケアは今から
ここまで、下半身の巡りを整える方法についてお伝えしてきました。最後にポイントをまとめますね!
下半身の巡りケア 7つのポイント:
- 11月は体づくりの大切な時期:冬本番前に体質の土台を整える
- お灸で温める:三陰交、太谿、湧泉の3つのツボを中心に
- 朝の白湯習慣:内臓から温めて1日の巡りをサポート
- 寝る前の足湯:1日の疲れをリセット
- 服装の工夫:首・手首・足首を温める
- 食事の見直し:根菜類と黒い食材を積極的に
- セルフマッサージ:ふくらはぎと股関節のケア
大切にしたい心がまえ:
体質改善は、一朝一夕にはいきません。でも、毎日少しずつケアを続けることで、確実に体は応えてくれます✨
- 焦らず、ゆっくりと
- 完璧を目指さず、できることから
- 小さな変化を喜ぶ
- 自分の体と向き合う時間を大切に
セルフケアと専門的なサポートの両輪で:
日々のセルフケアで体を整えながら、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、より効果的に冷え対策ができます。
一人で頑張りすぎないでくださいね。困った時は、いつでも相談してください😊
冬はもうすぐそこ!
今から下半身の巡りを整えて、寒い冬も温かく快適に過ごしましょう♪
あなたの体が、本来の温かさを取り戻せますように。応援しています✨
※ 個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。鍼灸は医療行為の代替ではありません。体調に不安がある場合は、医療機関を受診してください。
下半身の巡りケアを実践されている方の声もご紹介しております。
