冬の風邪予防は11月から!免疫力をサポートする東洋医学的養生法【柏市の鍼灸院】
2025-11-27 季節の養生法
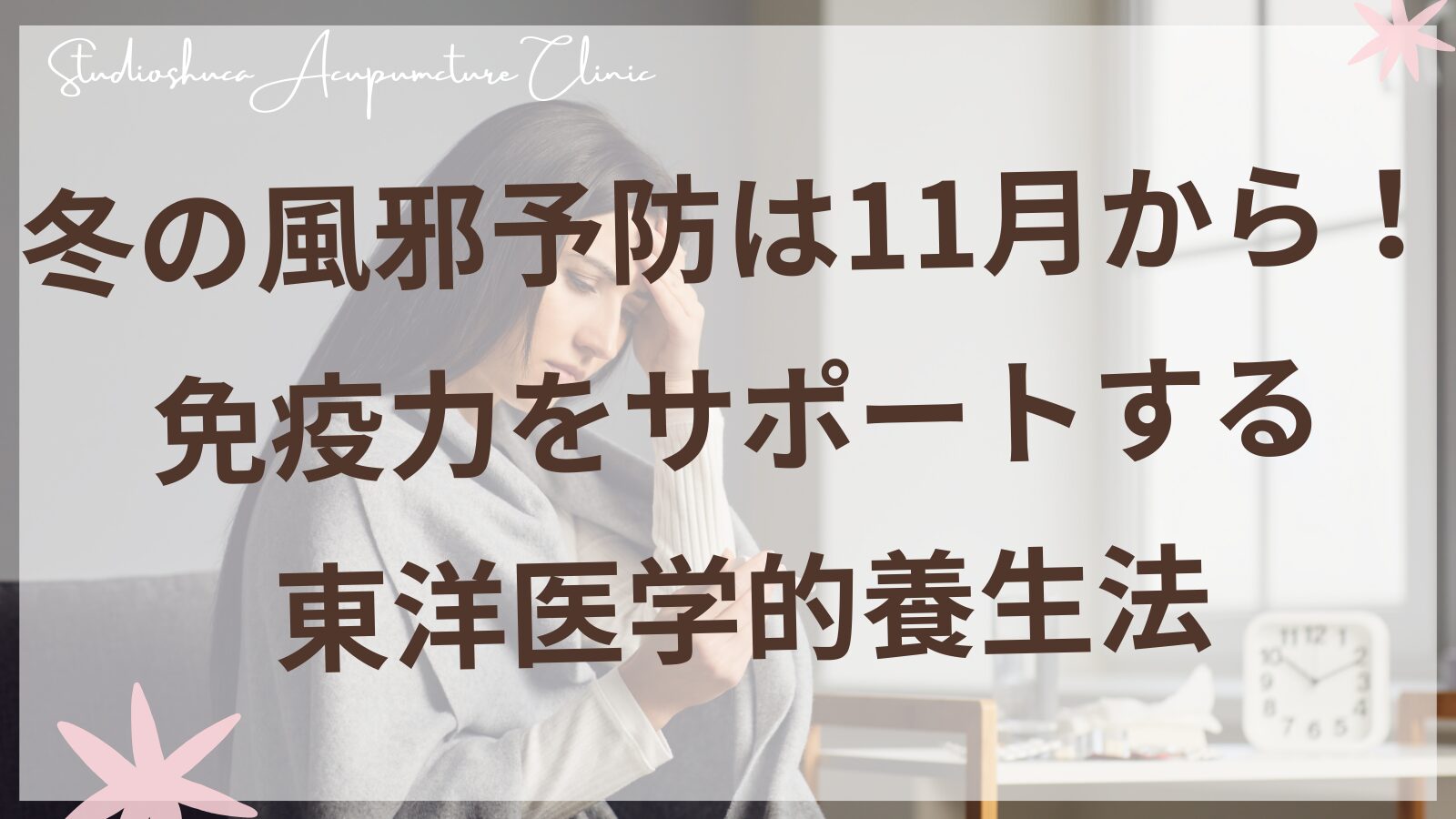 こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
「毎年冬になると風邪をひいてしまう…」
「季節の変わり目はいつも体調を崩しがち…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
実は、冬の風邪予防は寒くなってからでは遅いと言われています。東洋医学では、11月のうちから体を整えておくことが大切だと考えられているんです✨
この記事では、東洋医学の「肺の養生」という考え方をもとに、冬に向けた体づくりの方法をお伝えしますね。
この記事でわかること:
- なぜ11月からの準備が大切なのか
- 東洋医学でいう「肺」と免疫の関係
- 今日からできる具体的な養生法
- 鍼灸での季節養生サポート
こんな方におすすめ:
- 毎年冬に風邪をひきやすい方
- 季節の変わり目に体調を崩しやすい方
- 薬に頼らず自然な方法で体調管理したい方
- 東洋医学の養生法に興味がある方
11月の養生についてはこちらの記事もおすすめです。
冬に向けて体力を蓄える!11月の無理しない養生法で元気に冬を迎える
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質のケアをサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
なぜ冬の風邪予防は11月から始めるべき?
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期
11月は朝晩の寒暖差が大きくなる時期ですよね。この気温差が体に負担をかけやすいと言われています。
さらに、空気の乾燥が進むことで、喉や鼻の粘膜も影響を受けやすくなります。
「なんとなくだるい」「疲れが取れない」と感じている方も多いのではないでしょうか?
秋の疲れが蓄積したまま冬を迎えると、体調を崩しやすくなってしまいます。だからこそ、11月のケアが大切なんです。
秋の疲れについてはこちらもご参考に。
秋バテを予防する体づくり!気の巡りを整える生活習慣とセルフケア
東洋医学が教える「先手のケア」という考え方
東洋医学には「未病を治す」という考え方があります。これは、病気になる前の段階でケアすることを大切にする考え方です。
風邪をひいてから対処するのではなく、ひく前に体を整えておく。この「先手のケア」が東洋医学の知恵なんですね😊
冬本番を迎える前の11月は、まさに準備に最適な時期。体を整えておくことで、寒さへの適応力をサポートできると考えられています。
厚生労働省も風邪やインフルエンザの予防について情報を発信しています。
厚生労働省「インフルエンザ(総合ページ)」
東洋医学から見た免疫力と「肺」の関係
東洋医学でいう「肺」とは?
東洋医学でいう「肺」は、西洋医学の肺(臓器)とは少し違う概念です。
呼吸器系全体に加えて、皮膚や体表のバリア機能も含むと考えられています。「気」を全身に巡らせる働きがあるとも言われているんですよ。
五行説では「肺」は「金」に属し、秋と深く関連するとされています。だから秋〜冬にかけては、特に肺のケアが大切と考えられているんです。
また、「肺は皮毛を主る」という古くからの教えがあります。肌や体表を守る働きと関係しているという意味ですね。
「衛気(えき)」─体を守るバリア機能
東洋医学では、体表を守る気を「衛気(えき)」と呼びます。
この衛気は肺の働きと深く関連すると言われています。衛気がしっかりしていると、外からの邪気(病気の原因となるもの)を防ぐと考えられているんです。
冷えや乾燥は衛気を弱める要因とされています。だからこそ、体を温めて潤いを保つケアが大切なんですね。
秋の乾燥が「肺」に与える影響
東洋医学では「燥邪(そうじゃ)」という概念があります。これは乾燥した空気が体に与える影響のことです。
乾燥した空気は肺に影響を与えやすいと考えられています。喉のイガイガ、鼻の乾燥、肌荒れなどの不調につながりやすいんです。
だから、潤いを補うケアがとても大切になってきます✨
秋の乾燥対策についてはこちらもどうぞ。
乾燥する秋に潤いチャージ!肺を守る食材選びと東洋医学ケア
今日からできる「肺の養生」5つの方法
ここからは、今日から始められる具体的な養生法をご紹介しますね!
①白い食材で潤いを補う
東洋医学では、白い食材が肺を潤すと言われています。
おすすめの食材:
- れんこん
- 大根
- 白きくらげ
- 梨
- はちみつ
これらの食材を温かいスープや煮物で取り入れるのがポイントです。れんこんと大根の味噌汁や、梨のコンポートなどがおすすめですよ😊
薬膳レシピについてはこちらも参考にしてみてください。
冬支度は食事から!旬の食材で作る体を温める薬膳レシピ
②深呼吸で肺に新鮮な空気を届ける
朝起きたときに深呼吸を5回行う習慣をつけてみませんか?
おすすめの呼吸法:
- 鼻からゆっくり4秒吸う
- 口から8秒かけてゆっくり吐く
- 肺に新鮮な空気を届けるイメージで
深呼吸は自律神経を整えるサポートにもなると言われています。朝の習慣にぜひ取り入れてみてくださいね。
③首元・背中を冷やさない習慣
東洋医学では、首〜背中の上部に「風門(ふうもん)」というツボがあります。ここは邪気の入り口と考えられているんです。
だから、この部分を冷やさないことがとても大切!
おすすめの習慣:
- マフラーやストールで首元を守る
- 入浴時に首〜背中をしっかり温める
- 薄手のネックウォーマーを活用する
秋の温活についてはこちらもご覧ください。
朝晩の冷え込みで体調を崩さない!秋の温活養生術
④じんわり温まる適度な運動
激しい運動よりも、ウォーキングやストレッチがおすすめです。
汗をかきすぎると、体の潤いが逃げてしまうと言われています。じんわり温まる程度の運動を心がけてみてください。
おすすめの運動:
- 朝の散歩(15〜20分程度)
- ゆったりとしたストレッチ
- 深呼吸を意識したヨガ
新鮮な空気を取り入れながら、ゆったりと体を動かすのがポイントです✨
⑤早寝早起きで体を休める
秋は「早寝早起き」が養生の基本と言われています。
夜更かしを避けて、23時までには就寝を心がけてみてください。質の良い睡眠が体の回復をサポートしてくれます。
寝る前のスマホは控えめにするのも大切なポイントですよ😊
睡眠養生についてはこちらの記事もおすすめです。
秋の夜長こそ早寝が大切!冬に備える睡眠養生と心身を整える夜習慣
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な季節のケアをご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
セルフケアで使えるツボのご紹介
ご自宅で手軽にできるツボ押しもご紹介しますね。
合谷(ごうこく)─手軽に押せる万能ツボ
位置:手の甲、親指と人差し指の骨が交わる部分のくぼみ
押し方:
- 反対の手の親指で押す
- 痛気持ちいい程度の強さで
- 3秒押して離す×5回
伝統的に体の巡りをサポートするツボとして知られています。いつでもどこでも手軽にできるセルフケアですよ✨
※個人差があります
風門(ふうもん)─邪気の入り口をガード
位置:首を前に倒したときに出っ張る骨から指2本分下、背骨の両脇
セルフケア方法:
- カイロを当てる
- ドライヤーで温める
- 蒸しタオルを当てる
東洋医学では邪気が入りやすい場所とされています。冷やさないことが何より大切です!
※温めすぎに注意。低温やけどにご注意ください
鍼灸で季節養生をサポート
体質に合わせたオーダーメイドのケア
セルフケアを続けていても、なかなか変化を感じられないこともありますよね。
そんなときは、専門家によるサポートを受けるのも一つの選択肢です。
鍼灸では、体質診断に基づいた施術プランをご提案できます。肺兪、風門、合谷などのツボへのアプローチや、冷えや乾燥など個別のお悩みへの対応が可能です。
※施術の体験には個人差があります
冷えのタイプ別ケアについてはこちらもどうぞ。
あなたの冷えはどこから?足先・お腹・手先タイプ別の東洋医学的ケア法
スタジオシュカ鍼灸治療院でできること
スタジオシュカでは、以下のようなサポートをさせていただいています。
- 東洋医学の観点からの体質チェック
- 季節に合わせた養生アドバイス
- お一人おひとりに合わせた施術
- 継続的なサポート体制
鍼灸についてもっと知りたい方は、日本鍼灸師会のサイトもご参考にしてください。
公益社団法人 日本鍼灸師会
まとめ:11月の養生で冬を元気に乗り越えよう
今回は、冬の風邪予防のために11月から始める東洋医学的養生法についてお伝えしました。
ポイントをおさらい:
- 冬の風邪予防は11月からの準備が大切
- 東洋医学の「肺の養生」で体のバリア機能をサポート
- 白い食材、深呼吸、首元の保温、適度な運動、早寝早起きの5つの習慣
- 合谷・風門のツボでセルフケア
- セルフケアで難しい場合は専門家のサポートも選択肢に
季節の養生は、毎日の小さな積み重ねが大切です。完璧にやろうとせず、できることから少しずつ始めてみてくださいね😊
あなたの体は、ちゃんとケアに応えてくれます。この冬を元気に乗り越えられるよう、心から応援しています✨
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
個人の体質により体験には個人差があります。
施術効果を保証するものではありません。
医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
