冬支度は食事から!旬の食材で作る体を温める薬膳レシピ【千葉県柏市の女性の悩み専門の鍼灸院】
2025-11-03 季節の養生法
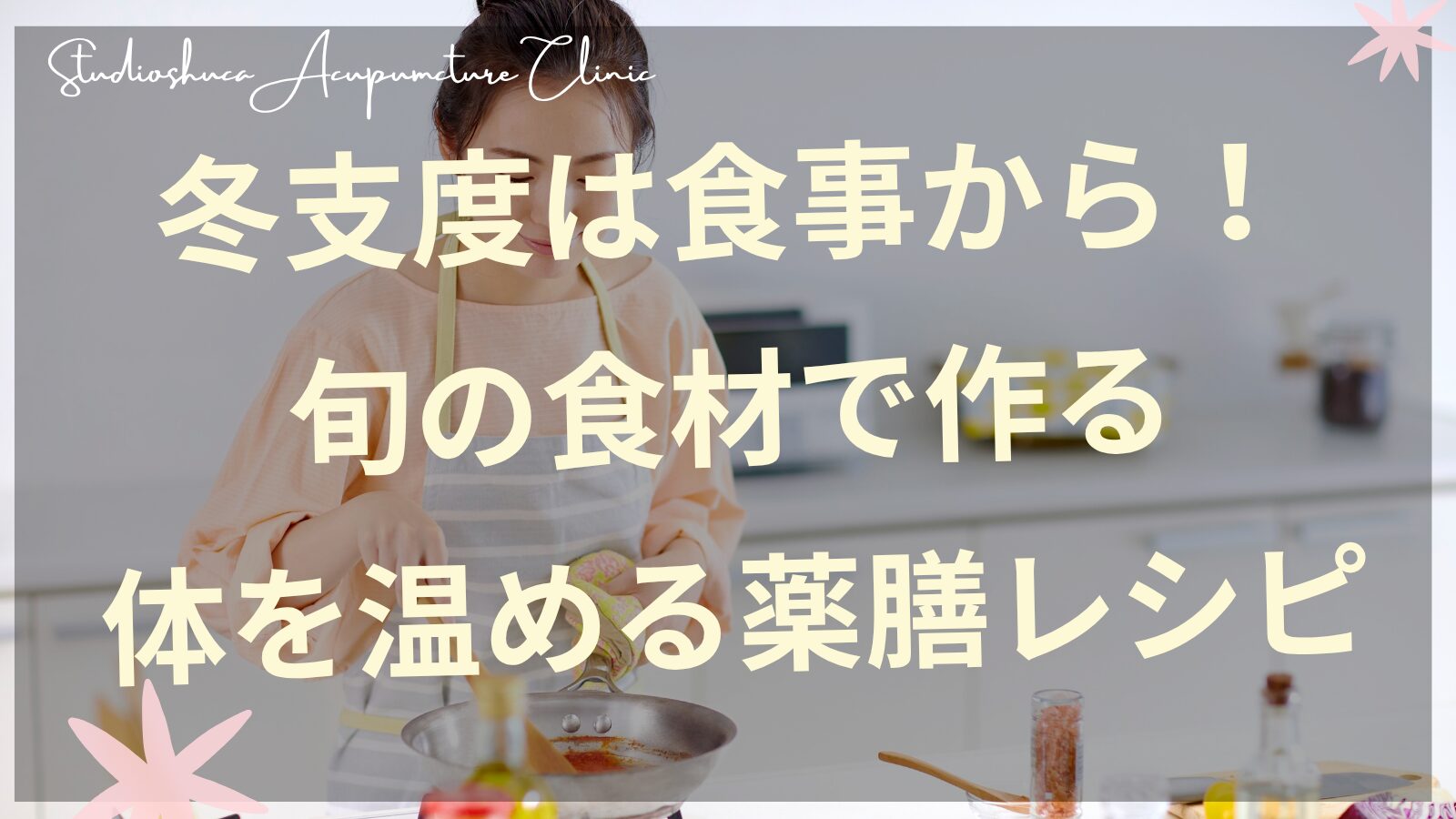
冬の入り口に起こりやすい体の変化
秋から冬への移行期の体調変化
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
11月に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。「最近、手足が冷えやすくなった」「体が温まりにくい」と感じていませんか?
実は、秋から冬への移行期は、東洋医学では「陽気が衰え、陰気が盛んになる時期」と考えられています。この時期に体を温める食事を取り入れることで、冬本番の冷えや不調を予防できると言われているんです。
この記事では、スーパーで手に入る旬の食材を使った、簡単な薬膳スープレシピをご紹介しますね。白ねぎやしょうがなど、身近な食材の温め効果や、東洋医学的な視点からの食材選びのコツもお伝えします。
この記事を読むとわかること:
- 体を温める旬の食材とその効果
- 簡単に作れる薬膳スープの具体的なレシピ
- 東洋医学から見た冬支度の食養生
- 体質別の食材アレンジ方法
こんな方におすすめです:
- 秋の終わりから手足の冷えが気になる方
- 食事で体を温めたいと考えている方
- 薬膳に興味があるけれど難しそうと感じている方
- 冬に向けて体調を整えたい30代、40代、50代の女性
それでは、一緒に冬支度を始めていきましょう!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
秋の終わりから冬の入り口にかけて、私たちの体には様々な変化が起こります。日照時間が短くなり、気温が下がることで、体は自然とエネルギーを温存するモードに切り替わっていくと言われているんです。
この時期によく聞かれる症状として:
- 手足の末端が冷えやすくなる
- 朝起きるのがつらくなる
- 肩や首のこりを感じやすい
- 疲れが取れにくい
これらは、体が冬に向けて準備を始めているサインなんです。決して悪いことではありませんが、この変化に上手に対応していくことが大切ですよ。
東洋医学から見た「冷え」のメカニズム
東洋医学では、冬の入り口は「陽気(体を温めるエネルギー)」が衰え始め、「陰気(冷えの要素)」が盛んになる時期と考えられています。
特に注目したいのが「腎」の働きです。東洋医学における「腎」は、生命エネルギーを蓄える臓腑とされ、冬の季節と深く関わっているんです。この「腎」の働きをサポートすることが、冬を元気に過ごすための鍵と言われています。
冬に向けて「腎」を養うには、体を温める食材を取り入れることが大切です。温かい食事は、体の深部から温めて、冷えを防ぐサポートをしてくれるんですよ。
また、秋の温活養生術も合わせて実践すると、より効果的に冬支度ができますね。
体を温める旬の食材とその効果
白ねぎの温め効果と選び方
白ねぎは、東洋医学で「辛温解表(しんおんげひょう)」の性質を持つとされ、体を温めて発汗を促す食材として知られています。
白ねぎの特徴:
- 硫化アリルという成分が血行をサポートすると言われています
- 体の表面の冷えを発散させる働きが期待されます
- 風邪の予防にも用いられてきた伝統的な食材です
選び方のポイント:
- 白い部分が長く、ハリがあるもの
- 葉先までピンとしているもの
- 11月から2月が最も美味しい旬の時期
スーパーで選ぶ際は、持ってみてずっしりと重みを感じるものがおすすめです。新鮮な白ねぎは、切った時の香りも良く、温め効果もより期待できるんですよ!
しょうがのパワーと使い方のコツ
しょうがは「温性食材の王様」とも言える存在です。東洋医学では、生のしょうが(生姜:しょうきょう)と、蒸して乾燥させたしょうが(乾姜:かんきょう)で効能が異なると考えられています。
しょうがの働き:
- 体の芯から温める作用があると言われています
- 消化をサポートする働きが期待されます
- 血の巡りを良くすると考えられています
使い方のコツ:
- 生のまま使うと、発汗作用が期待できます
- 加熱すると、体の深部を温める作用が高まると言われています
- 皮ごと使うことで、より温め効果が期待できます
今回ご紹介するスープレシピでは、加熱したしょうがを使用するので、体の深部からじんわり温まる感覚を味わえますよ♪
体を温める食材選びについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧くださいね。
その他の温性食材(鶏肉・大根・にんじん)
白ねぎとしょうが以外にも、今回のスープには体を整える食材をたっぷり使います。
鶏肉:
- 「気」を補う食材として知られています
- 胃腸の働きをサポートすると言われています
- タンパク質が豊富で体力維持に役立ちます
大根:
- 消化をサポートする働きがあると言われています
- 「気」の巡りを整えると考えられています
- 特に冬の大根は甘みが増して美味しくなります
にんじん:
- 「血」を補う食材とされています
- 体を滋養する働きが期待されます
- β-カロテンが豊富で免疫サポートにも良いとされています
これらの食材を組み合わせることで、体を温めながら、栄養もしっかり摂れるんです。しかも、どれもスーパーで手に入る身近な食材ばかりですよね!
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
基本の薬膳スープレシピ
材料と下準備
それでは、実際にスープを作ってみましょう!材料はとてもシンプルです。
【材料(4人分)】
- 白ねぎ:2本(白い部分を多めに)
- しょうが:1片(親指大)
- 鶏もも肉:300g
- 大根:1/4本(約200g)
- にんじん:1本
- 水:800ml
- 塩:小さじ1
- 醤油:大さじ1
- 酒:大さじ2(お好みで)
【下準備】
- 白ねぎは斜め切りに(約1cm幅)
- しょうがは皮ごと薄切りに
- 鶏もも肉は一口大にカット
- 大根は1cm厚さのいちょう切り
- にんじんは乱切り
ポイント:
しょうがは皮ごと使うことで、より温め効果が期待できます。よく洗って、そのまま薄切りにしてくださいね。
白ねぎの白い部分は特に温める作用が強いと言われています。緑の部分も美味しいのですが、今回は白い部分を中心に使いましょう。
野菜は大きめに切ることで、栄養素が流れ出にくくなります。また、食べ応えもアップしますよ♪
調理手順
下準備ができたら、いよいよ調理です!とっても簡単なので、お料理が苦手な方でも大丈夫ですよ。
【作り方】
1. 鍋に水を入れ、しょうがを加える
水を沸騰させながら、しょうがの香りを引き出します。この段階で部屋中に良い香りが広がって、気分も上がりますよ!
2. 鶏肉を加えてアクを取る
鶏肉を入れたら、丁寧にアクを取り除きます。アクを取ることで、スープがすっきりとした味わいになります。ここは少し手間ですが、美味しく仕上げるための大切なポイントです。
3. 大根、にんじんを加えて中火で15分煮る
蓋をして、野菜が柔らかくなるまで煮込みます。時々アクが出たら取り除いてください。野菜に火が通ると、甘みが出てきて、スープ全体が優しい味になっていきます。
4. 白ねぎを加えてさらに5分煮込む
白ねぎは煮込みすぎると香りが飛んでしまうので、最後に加えます。とろっとするまで煮込むのがポイントです。白ねぎの甘みがスープに溶け込んで、とっても美味しくなりますよ。
5. 塩、醤油で味を整える
味見をしながら、お好みの味に調整してください。酒を加えると、さらに風味が良くなります。仕上げに七味唐辛子を振りかけても美味しいですよ!
美味しく作るポイント
【温め効果を高めるコツ】
しょうがを多めに入れると、より体が温まります。辛いのが苦手でなければ、しょうが1.5片くらいに増やしてみてください。体がポカポカしてきますよ♪
煮込む時間を長くすることで、食材の温め効果が高まると言われています。時間がある時は、弱火でコトコト30分ほど煮込むのもおすすめです。
仕上げに七味唐辛子や柚子胡椒を加えるのもおすすめです。さらに体が温まる感覚が得られますよ。
【保存と作り置き】
粗熱を取ってから冷蔵庫で保存してください(2~3日以内に消費)。温め直す際は、しっかり沸騰させることが大切です。
冷凍保存も可能です(2週間程度)。1食分ずつ小分けにして冷凍しておくと、忙しい日でもすぐに食べられて便利ですよ。
【アレンジのヒント】
きのこ類を加えると、免疫サポートの効果も期待できます。しいたけやまいたけがおすすめです。
豆腐を加えると、タンパク質がさらに補えます。絹ごし豆腐をやさしく加えて、温めるだけでOKです。
お好みで春雨を加えても美味しくいただけます。ボリュームもアップして、満足感が増しますよ!
東洋医学から見た薬膳スープの効果
「温裏散寒」とは?
「温裏散寒(おんりさんかん)」とは、東洋医学の用語で「体の内側(裏)を温めて、冷え(寒)を散らす」という意味です。
このスープは、まさにこの「温裏散寒」の働きが期待できる組み合わせなんです。
具体的には:
- しょうがと白ねぎが体表の冷えを発散
- 鶏肉が体の内側からエネルギーを補う
- 大根とにんじんが消化をサポートし、栄養の吸収を助ける
このように、それぞれの食材が協力し合って、体全体を温める働きが期待されています。単に熱いものを食べるのではなく、食材の持つ性質を活かして、体の内側から温めていくのが薬膳の考え方なんですよ。
農林水産省の食育サイトでも、旬の食材を活かした食事の大切さが紹介されていますね。
気・血・水の観点から見た食材の組み合わせ
東洋医学では、体を構成する基本要素として「気・血・水」という考え方があります。この3つのバランスが整っていることが、健康な状態とされているんです。
このスープの気・血・水サポート:
気のサポート:
鶏肉は「気」を補い、体力をサポートする食材として知られています。疲れやすい方や、元気が出ない時にぴったりです。
白ねぎは「気」の巡りを良くすると言われています。滞りがちなエネルギーをスムーズに流す働きが期待されるんですよ。
血のサポート:
にんじんは「血」を補う働きが期待される食材です。顔色が悪い時や、貧血気味の方にもおすすめです。
鶏肉は血を生み出すもととなるタンパク質が豊富に含まれています。良質なタンパク質は、血を作るためにとても大切なんです。
水のサポート:
大根は体内の水分代謝をサポートする働きがあると言われています。むくみが気になる方にも良いとされているんですよ。
スープ全体として、適度な水分補給にもなります。冬は乾燥しやすい季節なので、温かいスープで水分を摂ることも大切です。
このバランスの良い組み合わせが、冬の冷えから体を守るサポートをしてくれるんです。
自律神経を整えることも、気・血・水のバランスを保つために大切ですよ。
五行説から見た冬の食養生
五行説では、冬は「水」の要素に属し、「腎」と深く関わっているとされています。
冬の食養生のポイント:
黒い食材(黒ごま、黒豆など)が腎をサポートすると言われています。このスープに黒ごまをトッピングするのもおすすめですよ。
塩味は腎に入ると考えられています。ただし、適量が大切です。塩分を摂りすぎると、かえって体に負担がかかってしまいます。
温かい食事で体の深部を温めることが重要とされています。まさに今回のスープは、この考え方にぴったりなんです。
このスープに黒ごまや黒きくらげを加えると、さらに冬の養生効果が高まると言われています。黒きくらげは食感も良く、見た目も華やかになりますよ♪
また、カルシウムを摂取することも、冬の健康維持には大切です。牛乳や小魚なども合わせて食べると良いですね。
体質別アレンジ方法
冷えが強い方向けのアレンジ
手足の冷えが特に強い方、寒がりな方には、さらに温め効果を高めるアレンジがおすすめです。
追加すると良い食材:
ニンニク1片:体を強く温める作用があると言われています。薄切りにして、しょうがと一緒に最初から加えましょう。
唐辛子少々:血行をサポートする働きが期待されます。辛いのが苦手な方は、ごく少量から試してみてください。
シナモンスティック1本:体の深部を温めると考えられています。煮込む時に一緒に入れると、香りも良くなりますよ。
しょうがを倍量に:温め効果がさらに高まります。辛みが気にならなければ、思い切って増やしてみましょう!
食べ方のコツ:
温かいうちに、ゆっくりいただきましょう。急いで食べると、せっかくの温め効果が半減してしまいます。
食後に温かいお茶を飲むと、さらに体が温まります。ほうじ茶や番茶がおすすめですよ。
就寝1時間前に食べると、寝る時の冷えが和らぐと言われています。ただし、食べ過ぎは消化に負担がかかるので、量は控えめにしてくださいね。
冷え性改善の温活と合わせて実践すると、より効果的ですよ。
疲れやすい方向けのアレンジ
疲労感が抜けない方、体力が落ちていると感じる方には、「気」を補う食材を追加しましょう。
追加すると良い食材:
きのこ類(しいたけ、まいたけなど):免疫サポートと気を補う働きが期待されます。しいたけは特におすすめです。
鶏肉を増量:タンパク質とエネルギー補給になります。鶏もも肉を400gくらいに増やしてみてください。
山芋:消化をサポートしながら気を補うと言われています。すりおろして最後に加えると、とろみもついて美味しいですよ。
なつめ3~4個:気と血を補う伝統的な食材です。煮込む時に一緒に入れると、優しい甘みが出ます。
ポイント:
朝食にこのスープを食べると、一日のエネルギー補給になります。朝から体が温まって、元気に活動できますよ。
よく噛んで、ゆっくり食べることが大切です。消化をサポートし、栄養の吸収も良くなります。
毎日続けることで、徐々に体力がサポートされると言われています。焦らず、2週間を目標に続けてみてください。
胃腸が弱い方向けのアレンジ
消化不良を起こしやすい方、胃腸が弱い方には、消化をサポートする食材を中心にアレンジしましょう。
追加すると良い食材:
大根を増量:消化酵素が豊富で、消化をサポートします。1/2本くらいに増やしても大丈夫です。
キャベツ:胃の粘膜を保護する働きがあると言われています。ざく切りにして加えてください。
長芋:胃腸の働きを整えると考えられています。すりおろして加えると、スープがまろやかになります。
生姜は控えめに:刺激が強すぎる場合は量を調整してください。半片くらいから始めてみましょう。
調理のコツ:
野菜は柔らかくなるまで、しっかり煮込みましょう。箸で簡単に切れるくらいが目安です。
鶏肉は皮を取り除くと、さらに消化しやすくなります。脂が気になる方は、皮なしの鶏むね肉を使うのもおすすめです。
薄味にして、胃腸への負担を減らします。塩は少なめにして、物足りなければ食べる時に調整してくださいね。
食べ方:
一度に大量に食べず、少量ずつ何回かに分けていただきましょう。お茶碗1杯分くらいから始めてみてください。
よく噛んで、ゆっくりいただきます。一口30回噛むことを意識してみてくださいね。
食後すぐに横にならず、しばらく座って過ごします。消化をサポートするためにも、食後は安静に過ごしましょう。
日常への取り入れ方と継続のコツ
週3~4回の習慣化
薬膳スープの効果を実感するには、継続することが大切です。無理なく続けられる習慣づくりをご提案しますね。
おすすめのスケジュール:
月・水・金・日の週4回パターン:
週末に多めに作って、平日の食事に取り入れる方法です。1回の調理で2~3日分を作り置きすれば、忙しい日でも温めるだけで食べられます。
続けるためのコツ:
カレンダーに「スープの日」を記入してみましょう。予定として書いておくと、習慣化しやすくなりますよ。
家族と一緒に食べることで、楽しみながら継続できます。「今日はスープの日だね♪」と声をかけ合うのも良いですね。
SNSに記録をつけるのもモチベーション維持に効果的です。「今日もスープ飲みました!」と写真付きで投稿してみてください。
期待される変化:
一般的に、2週間程度続けると「なんとなく体が温まりやすくなった」と感じる方が多いと言われています。
1ヶ月続けると、冷えに対する体の対応力がサポートされることが期待されます。朝の目覚めが良くなったり、手足の冷えが気にならなくなったりする方もいらっしゃいますよ。
ただし、効果の感じ方には個人差があります。焦らず、自分のペースで続けていくことが何より大切です。
作り置きと保存方法
忙しい方でも続けられる、作り置きのコツをご紹介します。
作り置きのポイント:
調理のタイミング:
週末(土曜日や日曜日)にまとめて調理するのがおすすめです。時間のある時に作っておけば、平日が楽になりますよ。
1回で2~3日分を作りましょう。あまり大量に作ると、食べきれなくなる可能性があります。
小分けにして保存すると、使いやすくなります。1食分ずつ分けておくと、温める時も便利です。
保存方法:
冷蔵保存(2~3日):
粗熱を取ってから、清潔な容器に移してください。熱いまま冷蔵庫に入れると、庫内の温度が上がってしまいます。
しっかり蓋をして冷蔵庫へ入れましょう。密閉容器を使うと、匂い移りも防げます。
温め直す際は、必ず沸騰させてください。鍋に移して、ぐつぐつと沸騰させることが大切です。
冷凍保存(2週間程度):
1食分ずつジップロックなどに入れて冷凍しましょう。袋に日付を書いておくと、管理しやすいですよ。
平らにして冷凍すると、解凍しやすくなります。袋の空気をしっかり抜いて、平らにして冷凍してくださいね。
前日に冷蔵庫に移して自然解凍すると、時短になります。朝食べたい時は、前の晩から移しておきましょう。
衛生管理:
清潔な容器と清潔な箸を使用してください。取り分ける際は、直接口をつけた箸を使わないようにしましょう。
少しでも異臭がしたら、食べずに処分してください。もったいないと思っても、体調を崩しては元も子もありません。
朝食・夕食での活用法
時間帯によって、スープの取り入れ方を変えると、より効果的ですよ。
朝食での活用:
タイミング:起床後30分以内に食べるのがおすすめです。
期待される効果:一日の始まりに体を温め、活動のサポートをしてくれます。朝から体が温まると、活動的に過ごせますよ。
おすすめの組み合わせ:
- 雑穀ご飯と一緒に
- 納豆や卵などのタンパク質を追加
- 漬物や梅干しで食欲増進
朝は時間がないという方も、温めるだけで食べられるので、忙しい朝にぴったりです!
夕食での活用:
タイミング:就寝2~3時間前に食べましょう。
期待される効果:体を温めて、質の良い睡眠をサポートしてくれます。体が温まった状態で眠ると、ぐっすり眠れますよ。
おすすめの組み合わせ:
- 白米や玄米と一緒に
- 温野菜のサラダを添えて
- 軽めの量で胃腸への負担を減らす
夜は消化に時間がかかるので、食べ過ぎには注意してくださいね。
間食としても:
午後3時頃、小腹が空いた時に温かいスープを飲むのもおすすめです。体が温まり、夕方の冷えを予防できると言われています。
甘いおやつの代わりに、このスープを飲むのも良いですよ。栄養もしっかり摂れて、体も温まります♪
厚生労働省の健康日本21でも、バランスの良い食事の大切さが説明されていますね。
鍼灸で体を温める・冬支度のサポート
温活をサポートする経絡とツボ
東洋医学では、体を温めるために特定の経絡やツボを刺激することが伝統的に行われてきました。
主な経絡:
腎経(じんけい):
足の内側を通る経絡です。生命エネルギーと関わりが深いとされています。冬の養生において重要な経絡と考えられているんですよ。
脾経(ひけい):
消化吸収と関わる経絡です。栄養を全身に届ける働きがあると言われています。食養生との相性が良いとされているんです。
温めの代表的なツボ:
関元(かんげん):
おへそから指4本分下にあります。体の深部を温めるツボとして知られています。セルフケアでは、カイロを貼る場所としてもおすすめですよ。
気海(きかい):
おへそから指2本分下にあります。気を補うツボと言われています。温灸(おんきゅう)でじんわり温めると心地よいです。
三陰交(さんいんこう):
内くるぶしから指4本分上にあります。婦人科系のお悩みに用いられることが多いツボです。自分でも押しやすい場所なので、セルフケアにぴったりですよ。
セルフケアの方法:
- 指の腹で優しく押す(5秒×3回)
- 温かいタオルで温める
- カイロを当てる(低温やけどに注意)
ただし、これらは伝統的な考え方であり、個人差があります。専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
関元ツボの詳しい刺激法は、こちらの記事でもご紹介していますよ。
スタジオシュカでの季節養生ケア
スタジオシュカ鍼灸治療院では、東洋医学の観点から、お一人おひとりの体質に合わせた季節養生のサポートをさせていただいています。
当院の季節養生アプローチ:
体質診断:
舌診、脈診などの東洋医学的な診察を行います。生活習慣やお悩みをじっくりヒアリングして、あなたの体質タイプを判断させていただきます。
施術内容:
体質に合わせたツボを選んで、鍼やお灸による経絡への働きかけを行います。リラックスできる施術環境で、心も体もほぐしていただけますよ。
生活アドバイス:
季節に応じた食材の選び方や、日常生活での温活のコツをお伝えします。セルフケアの方法もお教えしますので、ご自宅でも継続していただけます。
当院の特徴:
スタジオシュカは、千葉県柏市にある女性の悩みに特化した鍼灸院です。婦人科系のお悩みから、冷えや疲労、季節の不調まで、幅広くサポートさせていただいています。
一人ひとりに寄り添った丁寧なケアを心がけています。初めての方でも、安心してご来院いただけますよ。
お気軽にLINEからご相談ください。体質や症状についてのご相談も承っています。
食養生と鍼灸の相乗効果
食養生と鍼灸を組み合わせることで、より体質改善のサポートが期待できると言われています。
食養生の役割:
毎日続けることで、体の内側から変化をサポートします。栄養面からのアプローチで、じっくりと体質を整えていきます。自宅で手軽に実践できるのも魅力ですね。
鍼灸の役割:
経絡の流れを整えると考えられています。深部から体を温める働きが期待されます。プロの視点からの体質診断とケアで、より効果的なサポートが可能です。
組み合わせることで:
食養生で体の土台を整えながら、鍼灸で経絡の流れをサポートすることで、より冬を元気に過ごせる体づくりが期待できます。
まるで、内側と外側から同時にアプローチするイメージですね。相乗効果で、より実感しやすくなると言われています。
実際のケアの流れ:
- 当院で体質診断と施術を受ける
- 体質に合った食養生のアドバイスを受け取る
- 自宅で薬膳スープなどを実践
- 定期的に来院して経過を確認
- 季節の変化に応じてケア方法を調整
このように、継続的なサポート体制で、あなたの冬支度をお手伝いさせていただいています。
個人差について:
体質や生活習慣は人それぞれです。効果の感じ方にも個人差がありますので、焦らず、ご自身のペースで続けていくことが大切です。
一人で続けるのが不安な方は、ぜひ当院にご相談くださいね。一緒に、あなたに合った冬支度を考えていきましょう!
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:食事から始める冬支度で健やかな冬を
ここまで、旬の食材を使った薬膳スープのレシピと、東洋医学の視点から見た冬支度の食養生についてお伝えしてきました。
今日からできること:
スーパーで白ねぎとしょうがを購入してみましょう。基本の薬膳スープを作って、温かいうちにゆっくりいただいてくださいね。
1週間後:
週3~4回の習慣として定着させましょう。体の変化に気づき始めるかもしれません。体質に合わせたアレンジも試してみてください。
1ヶ月後:
冷えに対する体の対応力がサポートされることを期待できます。冬本番を迎えても元気に過ごせる体づくりの土台ができますよ。鍼灸との組み合わせも検討してみましょう。
大切なこと:
冬支度は、寒くなってからではなく、今の時期から始めることが重要です。体は急には変わりませんが、毎日の積み重ねが、やがて大きな変化につながっていきます。
薬膳と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は身近な食材で、誰でも簡単に始められるんです。まずは今日、このスープを作ってみませんか?
体が温まると、心もほっと落ち着きますよ。寒い冬も、元気に笑顔で過ごせますように!
もし一人で続けるのが不安な方は:
スタジオシュカ鍼灸治療院では、食養生のアドバイスも含めた、トータルな季節養生のサポートをさせていただいています。お気軽にご相談くださいね。
皆さまの冬が、温かく健やかなものになりますように。最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
免責事項
※個人の体質により体験には個人差があります。
※本記事で紹介する内容は、東洋医学の伝統的な考え方に基づくものであり、施術効果を保証するものではありません。
※鍼灸は医療行為の代替ではありません。体調に不安がある場合は、医療機関を受診してください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
