10月の気温差による頭痛・めまいをケア!気圧変化に負けない体づくりの養生法【柏市の鍼灸院】
2025-10-09 季節の養生法
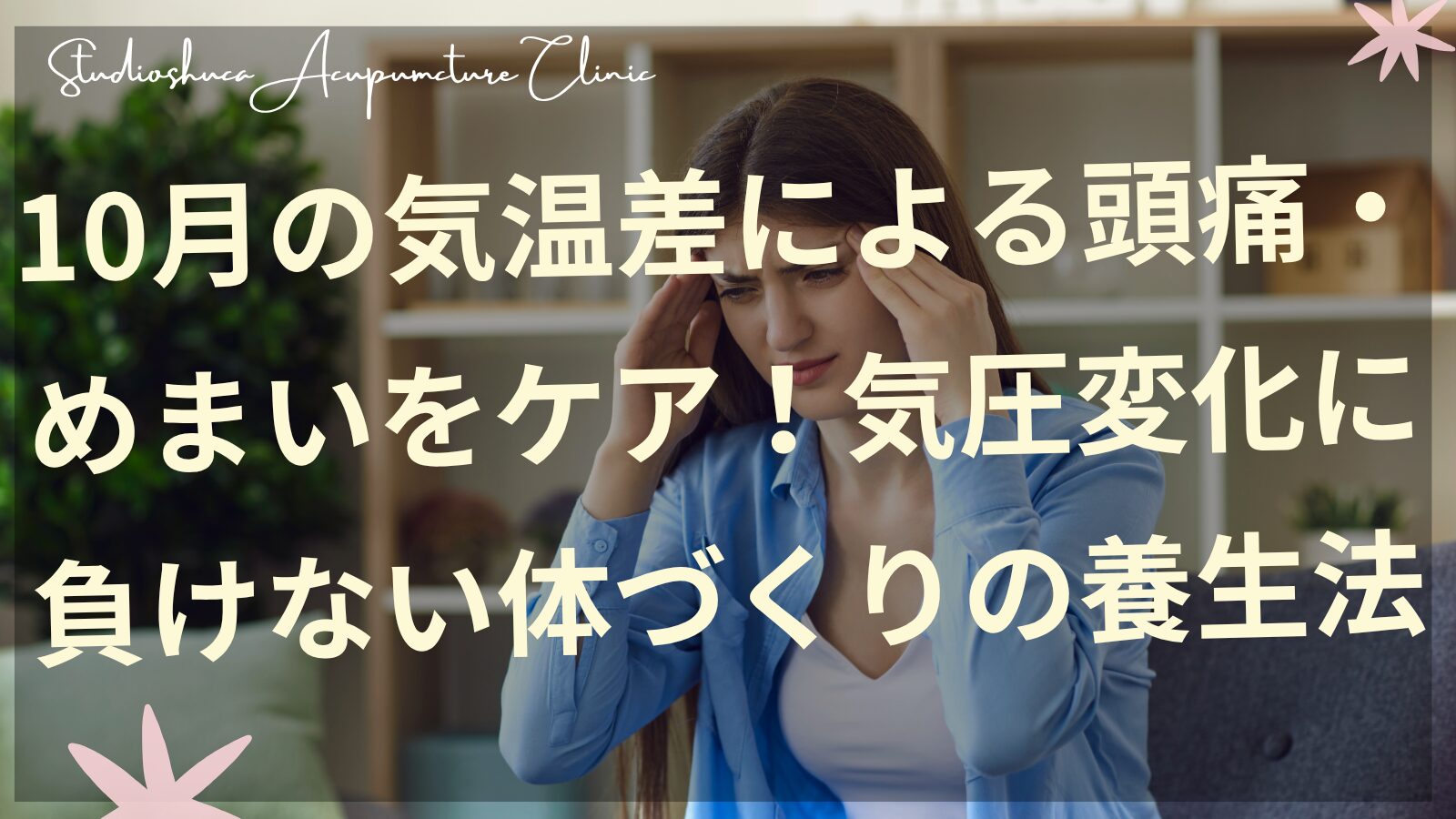
10月の気圧変化が体に与える影響とは?
10月になると、朝晩の寒暖差が大きくなり、天気も変わりやすくなりますよね。
「雨が降る前に頭が痛くなる」「天気が悪いとめまいがする」こんな経験はありませんか?
実は、気圧の変化は体にさまざまな影響を与えることが知られているんです。
気圧が下がると起こる体の変化
一般的に、気圧が下がると体内の血管が拡張しやすくなると言われています。
拡張した血管が周囲の神経を刺激することで、頭痛を引き起こす可能性があります。
また、内耳には気圧を感知するセンサーがあり、急激な気圧変化に反応してめまいやふらつきを感じることもあるんです。
特に女性は、ホルモンバランスの影響も受けやすく、気圧変化による不調を感じやすい傾向にあります。
秋特有の寒暖差が自律神経に与える影響
10月は、朝晩の気温差が10度以上になることも珍しくありません。
この寒暖差は、自律神経にとって大きなストレスとなります。
自律神経は、体温調節や血流コントロール、内臓の働きなど、私たちの体を無意識にコントロールしている大切な神経です。
気温差が激しいと、交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、頭痛やめまいだけでなく、疲労感や不眠といった症状も現れやすくなるんですよ。
詳しくは季節の変わり目に揺らぐ自律神経を整える!五月病予防の東洋医学的アプローチでもご紹介しています。
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
東洋医学から見た気圧変化による頭痛・めまいの背景
東洋医学では、気圧変化による頭痛やめまいを「気の巡りの滞り」や「水の停滞」が関係していると考えます。
少し専門的なお話になりますが、わかりやすくご説明していきますね!
気の巡りの滞りと頭痛の関係
東洋医学では、私たちの体を巡る「気」というエネルギーがあると考えられています。
気圧が下がると、この気の流れが滞りやすくなり、特に頭部に気が溜まってしまうことがあるんです。
頭部に気が滞ると、頭痛や頭重感として現れやすくなります。
特に関連が深いとされるのが「肝経(かんけい)」と「胆経(たんけい)」という経絡です。
これらはストレスや緊張とも関係が深く、季節の変わり目に乱れやすいと言われているんですよ。
水の停滞(水滞)とめまいの関係
東洋医学では、体内の水分バランスも重要視します。
体内に余分な水分(湿・しつ)が溜まると、めまいやふらつきが起こりやすいと考えられています。
特に湿度が高い夏から秋への移行期は、体内に湿が残りやすい時期なんです。
この湿が気圧変化によってさらに動きにくくなると、めまいや体の重だるさとして感じられることがあります。
関連する経絡は「脾経(ひけい)」と「腎経(じんけい)」で、これらは水分代謝に関わるとされています。
秋は「肺」の季節!乾燥と気圧変化のダブルパンチ
東洋医学の五行説では、秋は「肺」の季節とされています。
肺は呼吸だけでなく、気の巡りや水分代謝にも深く関わると考えられているんです。
秋は空気が乾燥し、肺が影響を受けやすくなります。
肺が弱ると気の巡りが悪くなり、頭痛やめまいが起こりやすくなると言われています。
さらに気圧変化が加わることで、体調不良が起きやすくなるんですね。
秋の乾燥から肌と体を守る!潤いを保つ東洋医学的ケア法も参考にしてみてください。
気圧変化に負けない体づくりの養生法
ここからは、ご自宅でできる具体的な養生法をご紹介していきます!
毎日の生活に少しずつ取り入れることで、気圧変化に負けない体づくりをサポートできますよ。
①自律神経を整える「朝の習慣」3選
自律神経は、朝の過ごし方で一日のリズムが決まると言われています。
以下の3つの習慣を取り入れてみてください!
1. 起床後すぐに朝日を浴びる(5分程度)
- 体内時計がリセットされ、自律神経が整いやすくなると言われています
- セロトニン(幸せホルモン)の分泌をサポートし、気分も明るくなります
- カーテンを開けて、窓辺で深呼吸するだけでもOKです!
2. 白湯を一杯飲む
- 内臓を温め、気・血・水の巡りをサポートすると考えられています
- 消化器系が活性化し、一日の代謝が上がりやすくなります
- 起きてすぐ、ゆっくり飲むのがポイントです
3. 軽いストレッチや深呼吸
- 気の巡りを促し、頭部の気の滞りを解消すると言われています
- 特に首や肩周りをほぐすことで、頭への血流もサポートされます
- 無理のない範囲で、体を伸ばす気持ちよさを感じてください
朝の習慣について詳しくは寒暖差で崩れる自律神経をサポート!季節の変わり目を乗り切る体づくりもご覧ください。
②気の巡りを良くする「ツボ押し」セルフケア
東洋医学では、特定のツボを刺激することで気の巡りを整えると考えられています。
以下の3つのツボは、頭痛やめまいのケアに用いられることが多いツボです。
百会(ひゃくえ)
- 位置:頭頂部の中心、両耳を結んだ線と鼻の中心線が交わる点
- 伝統的な意味:気の巡りを整え、頭痛・めまいのケアに用いられます
- 押し方:中指で3~5秒ずつ、心地よい強さで押します
風池(ふうち)
- 位置:後頭部の髪の生え際、首の骨の両側のくぼみ
- 伝統的な意味:頭痛や首こりに関連するとされています
- 押し方:両手の親指で、頭を支えるようにして押します
合谷(ごうこく)
- 位置:手の甲、親指と人差し指の骨が交わる部分
- 伝統的な意味:万能のツボとして知られ、頭痛ケアにも活用されます
- 押し方:反対の手の親指で、3~5秒ずつ押します
実践のポイント
- 各ツボを1日2~3回、朝・昼・夜に行うと良いでしょう
- 深呼吸をしながらゆっくりと行うことで、リラックス効果も期待できます
- ※効果には個人差があります
気圧変化で悪化する頭痛・めまいを和らげる!秋の体調管理法でも詳しくご紹介しています。
③水の巡りを整える「食事の工夫」
東洋医学では、体内の余分な水分(湿)が溜まると、めまいや頭重感が起こりやすくなると考えられています。
食事で水の巡りを整えることも大切なケアの一つです。
水の巡りをサポートする食材
- 小豆:利尿作用があり、体内の余分な水分を排出すると言われています
- とうもろこし:湿を取り除く作用があるとされています
- 生姜:体を温め、気・血・水の巡りをサポート
- きのこ類(しいたけ、まいたけ):気を補い、体内の水分バランスを整えると考えられています
避けたい食材
- 冷たい飲み物や生もの(体を冷やし、水の巡りを悪くする可能性があります)
- 油っこいもの、甘いもの(湿を生みやすいとされています)
簡単レシピ例
- 小豆粥:小豆と米を一緒に炊くだけの簡単レシピ
- 生姜紅茶:紅茶にすりおろし生姜を入れて温活
- きのこの味噌汁:しいたけやまいたけをたっぷり入れて
※食事は体質により合う合わないがあります。体調に合わせて調整してください。
④夜の過ごし方で副交感神経を優位にする
夜は副交感神経を優位にし、リラックスすることが大切です。
質の良い睡眠は、気圧変化に負けない体づくりの基本なんですよ!
1. 38~40℃のぬるめのお風呂にゆっくり浸かる(15~20分)
- 体を芯から温め、気・血の巡りをサポートすると言われています
- 副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなります
- 入浴剤を使うとさらにリラックス効果が高まります
2. 就寝1時間前にはスマホやパソコンを見ない
- ブルーライトが交感神経を刺激し、睡眠の質を下げる可能性があります
- 代わりに読書やストレッチなど、リラックスできる時間を過ごしましょう
3. 腹式呼吸を5分間行う
- 鼻から4秒吸って、口から8秒かけてゆっくり吐きます
- 副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できます
- ベッドの中で行うと、そのまま眠りにつきやすくなりますよ
気象庁の天気予報で翌日の気圧をチェックし、気圧が下がる日は特に意識して夜のケアを行うと良いでしょう。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
鍼灸で気圧変化による不調をケアする方法
セルフケアも大切ですが、一人で続けるのが難しいこともありますよね。
そんなときは、鍼灸でのサポートも選択肢の一つです。
鍼灸が気の巡りをサポートする仕組み
鍼灸は、気の巡りを整え、自律神経のバランスをサポートすることが期待される施術です。
頭部や首、肩周りのツボに鍼やお灸を施すことで、気の滞りをケアすると考えられています。
鍼灸施術で期待される体験
- 施術中はリラックスでき、副交感神経が優位になりやすいとされています
- 施術後は体が軽くなったり、頭がすっきりする感覚を得られることがあります
- 個人の体質に合わせた施術が可能です
厚生労働省の健康情報でも、東洋医学の活用について紹介されています。
※効果には個人差があり、医療行為の代替ではありません。
スタジオシュカでの季節養生アプローチ
当院では、東洋医学の観点から一人ひとりの体質を見極め、季節に合わせた養生法をご提案しています。
気圧変化による頭痛・めまいでお悩みの方には、以下のようなアプローチを行います。
スタジオシュカでのサポート内容
- 気の巡りを整えるツボと、水の巡りをサポートするツボを組み合わせた施術
- 体質診断を行い、あなたに合った食事や生活習慣のアドバイス
- セルフケアの方法を丁寧にお伝えし、ご自宅でも継続できるようサポート
- 季節の変わり目に合わせた定期的なケアのご提案
具体的なサポート事例
40代女性Aさん:季節の変わり目に必ず頭痛が起こっていましたが、定期的な鍼灸と生活習慣の見直しで、頭痛の頻度が減少したとのお声をいただきました。
30代女性Bさん:気圧が下がるとめまいがひどかったのですが、水の巡りを整える食事とツボケアで、体調が安定してきたと感じているそうです。
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。
低気圧で悪化する頭痛・めまいをケア!妊活中の女性におすすめの体調管理術も参考にしてください。
まとめ:10月を元気に過ごすための養生のポイント
10月の気温差や気圧変化による頭痛・めまいは、東洋医学の視点から見ると「気の巡りの滞り」や「水の停滞」が関係していると考えられています。
でも、毎日の生活にちょっとした工夫を取り入れることで、体はちゃんと応えてくれるんですよ!
今日からできる養生法のポイント
- 朝の習慣で自律神経を整える(朝日・白湯・ストレッチ)
- ツボ押しで気の巡りをサポート(百会・風池・合谷)
- 食事で水の巡りを整える(小豆・とうもろこし・生姜)
- 夜の過ごし方で副交感神経を優位に(ぬるめのお風呂・腹式呼吸)
一人で続けるのが難しい場合は、鍼灸でのサポートも選択肢の一つです。
気圧変化に負けない体づくりは、一日にしてならず。
でも、毎日コツコツ続けることで、必ず体は変わっていきます!
あなたの体質に合わせた季節養生を、ぜひ一緒に始めていきましょう。
季節の変わり目も、笑顔で元気に過ごせる日々を応援しています!
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。体調に不安がある場合は、医療機関にご相談ください。鍼灸は医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
