二度寝が増える秋の朝をスッキリ解消!自律神経を整える起き方のコツ【千葉県柏市の女性の悩み専門の鍼灸院】
2025-10-25 季節の養生法
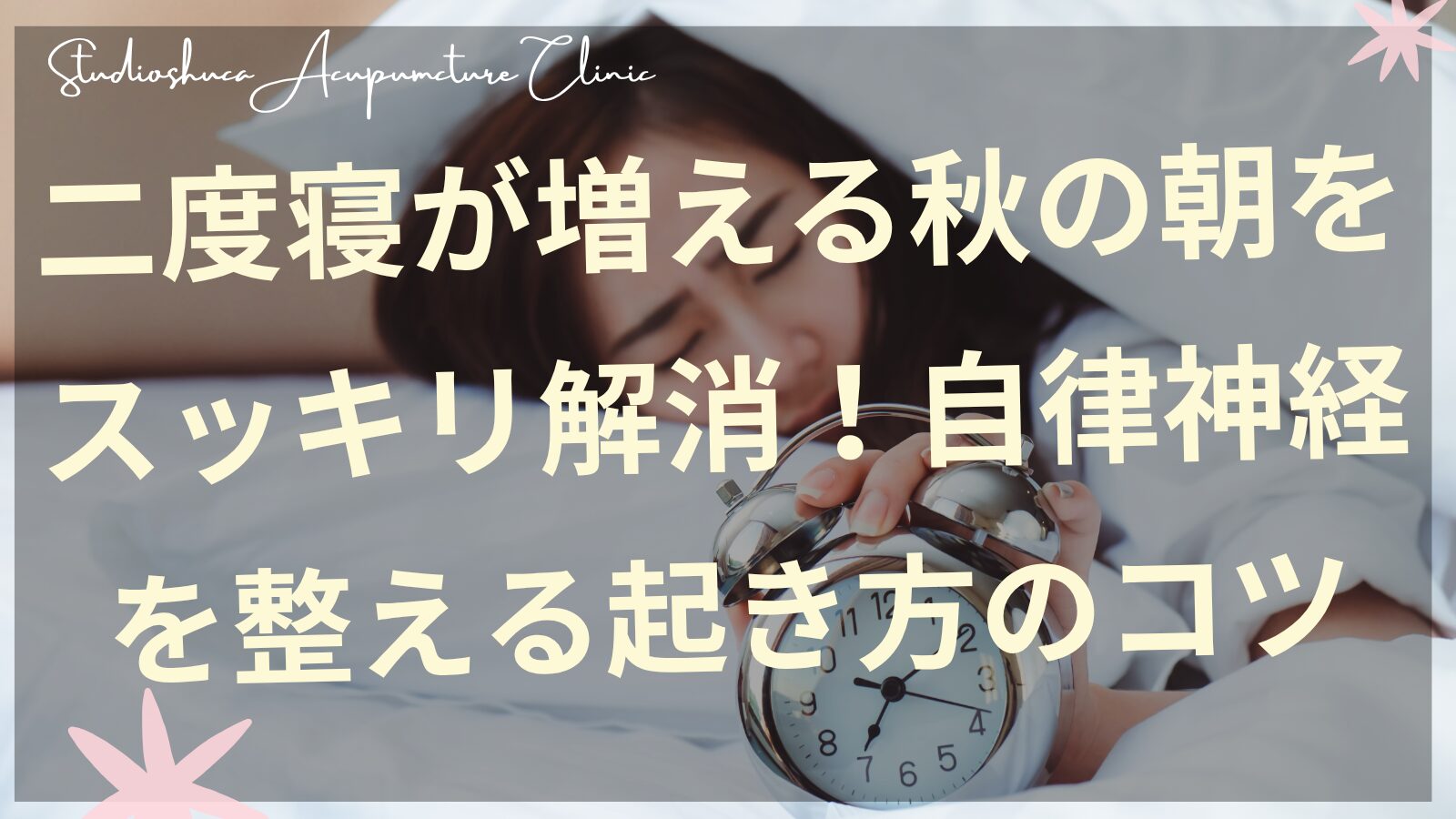
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
秋になると、なぜか朝起きるのが辛くなってきませんか?
アラームを何度もスヌーズしてしまったり、目が覚めても体が重くてベッドから出られなかったり…。
「夏はスッキリ起きられていたのに、どうして秋になると二度寝が増えるんだろう?」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、秋の朝の目覚めの悪さは、あなたの意志の弱さではないんです。
季節の変わり目特有の寒暖差や日照時間の減少が、自律神経のバランスに影響を与えていることが一般的に言われています。
東洋医学では、秋は「肺」の季節とされ、呼吸や気の巡りが乱れやすい時期なんですよ。
このブログでは、秋の朝にスッキリ目覚めるための具体的な5ステップをご紹介します!
東洋医学の知恵と現代の生活習慣を組み合わせた方法なので、今日から実践できますよ。
この記事はこんな方におすすめです
- 秋になると朝起きるのが辛くなる方
- 二度寝を繰り返してしまう方
- 朝から疲れが取れず、一日中だるい方
- 寒暖差で体調を崩しやすい方
- 自律神経を整えて健やかな毎日を過ごしたい方
秋の朝の不調でお悩みの方へ
秋になると朝起きるのが辛くなる、二度寝が増えてしまう…そんなお悩みはありませんか?
当院では、東洋医学の観点から自律神経のバランスをサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
秋の朝に二度寝が増える3つの理由
まず、なぜ秋になると朝起きるのが辛くなるのか、その理由を見ていきましょう。
実は、秋特有の環境変化が、私たちの体に大きな影響を与えているんです。
気温の寒暖差が自律神経に与える影響
秋は昼と夜の気温差が10度以上になることも珍しくありません。
体温調節は自律神経が担っているため、寒暖差が激しいと、体温調節のために自律神経がフル稼働することになります。
その結果、自律神経が疲弊しやすくなり、朝の目覚めにも影響が出ることが考えられます。
また、朝の冷え込みで布団が心地よく感じられ、心理的にも布団から出にくくなってしまうんですね。
日照時間の減少とセロトニン不足
秋になると、日の出の時刻が遅くなり、日照時間が短くなります。
日光を浴びる時間が減ると、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌が減少することが知られています。
セロトニンは、睡眠ホルモン「メラトニン」の原料でもあるため、睡眠の質にも影響を与えるんです。
朝の光を十分に浴びられないと、体内時計が乱れ、スッキリ目覚められなくなることがあります。
夏の疲れの蓄積と秋バテ
夏の暑さや冷房による疲労が、秋になって表面化することも多いんです。
これがいわゆる「秋バテ」と呼ばれる状態ですね。
免疫力が低下し、体が重く感じやすくなります。
東洋医学では、これは「気」のエネルギーが不足している状態と考えられています。
夏の間に消耗したエネルギーを、秋のうちにしっかり補充することが大切なんですよ。
東洋医学から見た秋の朝の不調の背景
では、東洋医学の視点から、秋の朝の不調をどう捉えているのか見ていきましょう。
季節と体の関係を理解することで、より効果的な対策ができるようになります!
秋は「肺」の季節〜呼吸と気の巡りの関係
東洋医学では、秋は五臓の「肺」に対応する季節とされています。
肺は呼吸器系だけでなく、皮膚や免疫機能とも深く関わっているんです。
また、肺は「気」を全身に巡らせる役割を担うとされています。
秋の乾燥は肺を傷つけやすく、呼吸が浅くなりがちです。
呼吸が浅いと、目覚めに必要な酸素供給が不足し、スッキリ起きられないことが考えられるんですね。
陽気が減少する秋の体の変化
陰陽論では、秋は陽気(活動的なエネルギー)が減少し、陰気(静かなエネルギー)が増える時期とされています。
夏の「陽」のエネルギーから秋の「陰」のエネルギーへの移行期なんです。
体が自然と休息モードに入りやすくなるため、朝起きるのが辛くなることがあります。
この自然な変化に体がうまく適応できないと、二度寝が増えてしまうんですね。
気・血・水のバランスが乱れやすい理由
東洋医学では、体の健康は「気・血・水」のバランスで保たれると考えられています。
気の不足:エネルギー不足で疲れやすく、朝起きるのが辛い
血の滞り:血流が悪くなり、目覚めが悪く、頭がぼんやりする
水の停滞:体内の水分代謝が悪くなり、むくみやだるさが出やすい
秋はこの3つのバランスが乱れやすく、朝の目覚めに影響を与えることがあるんです。
季節の変わり目を乗り切る自律神経ケアも参考にしてください。
一人ひとりに合わせた秋の養生を
朝の目覚めの悩みは、体質や生活環境によって原因が異なります。
当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な秋の養生法をご提案いたします。
自律神経を整える体づくりについて詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
自律神経を整える朝の起き方5ステップ
それでは、秋の朝にスッキリ目覚めるための具体的な5ステップをご紹介します!
東洋医学の知恵と現代の生活習慣を組み合わせた方法ですよ。
ステップ1:起床30分前に光を取り入れる準備
まず、起床時間の30分前に自然光が入るように準備しましょう。
スマートカーテンや光目覚まし時計を活用するのがおすすめです。
光が網膜を刺激することで、体内時計がリセットされ、覚醒モードへの切り替えをサポートすることが期待されます。
秋は日の出が遅くなるため、光目覚まし時計などの補助的なツールも効果的ですよ。
自然に目が覚めやすい環境を整えることが、スッキリした朝への第一歩なんです。
ステップ2:布団の中で深呼吸3回
目が覚めたら、すぐに起き上がらず、まずは布団の中で深呼吸をしましょう。
仰向けのまま、鼻からゆっくり4秒吸って、口から8秒かけて吐く深呼吸を3回繰り返します。
東洋医学では「肺」が呼吸を司り、秋の養生で最も大切な臓器とされているんです。
深呼吸により、副交感神経から交感神経への切り替えが穏やかになり、急激な血圧上昇を防ぐことが期待されます。
呼吸を意識することで、心も体も穏やかに目覚めることができますよ。
自律神経を整える呼吸法も参考にしてくださいね。
ステップ3:手足の指先から動かす「末端覚醒法」
次に、布団の中で手足の指先から動かし始めましょう。
まず足の指をグー・パーと10回開閉します。
次に手の指も同様に10回開閉してください。
東洋医学では、手足の末端には重要な経絡の起点があるとされています。
ここを刺激することで、血流が末端から中心に向かって動き出し、全身が目覚めやすくなると言われているんです。
簡単な動きですが、体全体のスイッチを入れる効果が期待できますよ!
ステップ4:起き上がる前に「肺経」のツボを刺激
起き上がる前に、秋に大切な「肺経」のツボを刺激しましょう。
中府(ちゅうふ):鎖骨の下、肩の付け根から指1本分下にあるツボです。
太淵(たいえん):手首の親指側、脈を感じる部分にあるツボです。
それぞれのツボを優しく5秒×3回押してください。
秋の養生で重要な「肺経」を刺激することで、呼吸が深くなり、気の巡りをサポートすることが期待されます。
※効果には個人差があります。
ステップ5:起床後すぐに白湯を一杯飲む
起き上がったら、まず白湯を一杯飲みましょう。
40〜50度程度の白湯を150ml、ゆっくり5分かけて飲むのがおすすめです。
東洋医学では、温かい飲み物が内臓を温め、気血の巡りをサポートすると考えられているんです。
秋の乾燥対策として、体の内側から潤いを補うことも期待できますよ。
レモンやはちみつを少量加えると、肺を潤す効果がさらに高まると言われています。
一日の始まりを、体に優しい白湯でスタートしてくださいね!
秋の温活で体を整える方法もチェックしてみてください。
秋の朝をサポートする東洋医学のツボと経絡
ここでは、秋の朝の目覚めをサポートするツボについて、もう少し詳しくご紹介します。
自宅で簡単にできるセルフケアとして、ぜひ取り入れてみてくださいね!
中府(ちゅうふ)〜肺の気を巡らせるツボ
中府は、鎖骨の下、肩の付け根から指1本分下にあるツボです。
伝統的に、呼吸を深くし、気の巡りをサポートするとされています。
優しく円を描くように、5秒×3回刺激してみてください。
深呼吸をしながら刺激すると、より効果的と言われていますよ。
朝だけでなく、日中に呼吸が浅いと感じた時にも試してみてくださいね。
太淵(たいえん)〜呼吸を深めるツボ
太淵は、手首の親指側、脈を感じる部分にあるツボです。
肺経の重要なツボとされ、呼吸器系のサポートに期待されています。
親指で優しく押し込むように刺激してください。
このツボは「脈診」でも使われる重要なポイントなんですよ。
秋の乾燥で喉が気になる時にも、このツボを刺激するといいと言われています。
自宅でできるセルフケアのポイント
ツボを刺激する際は、無理に強く押さず、心地よい程度の刺激を心がけてください。
朝だけでなく、夜寝る前にも実践すると、より効果的と言われています。
継続することで、体質のサポートが期待できますよ。
ただし、効果には個人差があることをご理解ください。
もし自分でやるのが難しい場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
秋の夜長に質の良い睡眠を取るためのケアも併せてご覧ください。
スタジオシュカの鍼灸でできる秋の養生サポート
セルフケアも大切ですが、一人で続けるのが難しい場合もありますよね。
スタジオシュカでは、東洋医学の観点から、あなたの体質に合わせた秋の養生をサポートさせていただいています。
自律神経のバランスをサポートする施術
当院では、一人ひとりの体質や症状に合わせたツボを選び、施術を行っています。
肺経だけでなく、全身の経絡バランスを整えるアプローチで、自律神経のバランスをサポートします。
リラックスした環境での施術が、副交感神経の働きをサポートすることが期待されるんです。
秋特有の体の変化に合わせて、最適な施術をご提案させていただきます。
※施術効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。
体質に合わせた季節養生のご提案
施術だけでなく、食事や生活習慣のアドバイスもさせていただいています。
季節ごとの体調変化に合わせたケア方法をお伝えし、ご自宅でも実践できるようサポートします。
セルフケアと専門施術を組み合わせることで、より効果的な体づくりが期待できますよ。
あなたの体質や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる方法をご提案します。
寒暖差で崩れる自律神経のケアについても、お気軽にご相談ください。
継続的なケアで秋を快適に過ごすために
定期的な施術により、体質の変化を実感しやすくなることが期待されます。
秋だけでなく、年間を通じた健康管理のお手伝いをさせていただいています。
一人で続けるのが難しい方も、専門家のサポートがあれば継続しやすくなりますよ。
あなたのペースに合わせて、無理なく体づくりを進めていきましょう。
秋の疲労回復術と併せて、総合的なケアをご提案します。
さらに詳しい情報は、厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~でもご確認いただけます。
専門家と一緒に秋の養生を始めませんか?
朝の目覚めを整えることは、一日の質を高める第一歩です。
一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。
スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた秋の養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:秋の朝を味方につけて、元気な一日を
いかがでしたか?
秋の朝の二度寝は、あなたの意志の弱さではなく、季節特有の体の変化によるものなんです。
今日ご紹介した5ステップの起き方を実践することで、自律神経のバランスをサポートすることが期待できますよ。
もう一度おさらいしましょう!
ステップ1:起床30分前に光を取り入れる
ステップ2:布団の中で深呼吸3回
ステップ3:手足の指先から動かす
ステップ4:肺経のツボを刺激
ステップ5:起床後に白湯を飲む
東洋医学のツボと経絡ケアを日常に取り入れることで、秋の朝がもっと快適になります。
まずはできることから、無理なく始めてみてくださいね。
一人で続けるのが難しいと感じたら、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。
スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせた季節養生をサポートさせていただいています。
秋の朝を味方につけて、元気な一日をスタートしましょう!
あなたの健やかな毎日を、心から応援しています。
季節の変わり目の憂鬱感をサポートする方法も、ぜひチェックしてみてくださいね。
※個人の体質により体験には個人差があります。
※施術効果を保証するものではありません。
※鍼灸施術は医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
