秋の味付け見直しで冬支度!塩分バランスと質で巡りをサポートする食事法【松戸・流山・我孫子から10分の女性の悩み専門の鍼灸】
2025-11-24 季節の養生法
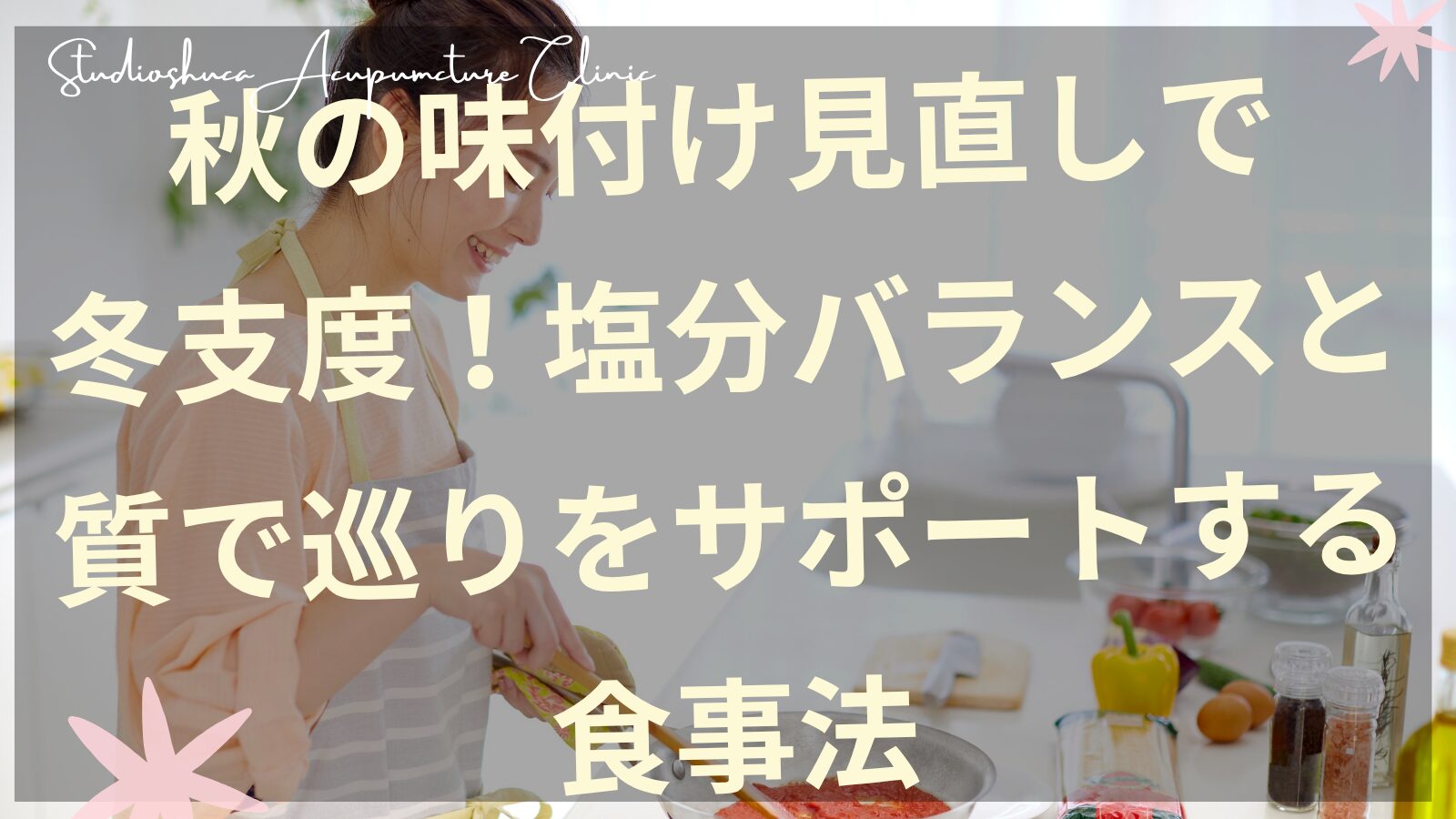
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
11月に入り、朝晩の冷え込みが増してきましたね。「なんだか体がだるい」「むくみやすくなった」「冬が来る前に体を整えたい」そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか?
実は、冬に向けた体づくりは「塩の選び方」から始まるんです!
東洋医学では、塩は「腎」を養う大切な食材とされています。腎は冬に最も活発に働く臓腑であり、生命エネルギーの貯蔵庫とも言われているんですよ。質の良い塩を適量摂ることで、冬の冷えやむくみ、疲労感などのケアが期待できます。
この記事を読むとわかること
- 天然塩と精製塩の違いと体への影響
- 冬に向けた体づくりのための塩の選び方
- 東洋医学的な塩の使い方と食養生のコツ
- 腎を養う食材の組み合わせ方
この記事はこんな方におすすめ
- 冬になると冷えやむくみが気になる方
- 疲れやすさやだるさが抜けない方
- 東洋医学の食養生に興味がある方
- 家族の健康を考えた調味料選びをしたい方
それでは、今日から実践できる塩選びと食養生のポイントをお伝えしていきますね!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
なぜ冬前の塩選びが大切なのか?東洋医学から見る塩と腎の関係
冬の体調を左右する「腎」という臓腑。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、東洋医学ではとても重要な存在なんです。
そして、この腎を養うのに欠かせないのが「塩」なんですよ✨
東洋医学における「腎」の役割
東洋医学における「腎」は、西洋医学の腎臓とは少し異なる概念です。
腎は私たちの生命エネルギー、いわゆる「精(せい)」を蓄える臓腑と言われています。具体的には以下のような働きがあると考えられているんです。
- 水分代謝のバランスを保つ
- 骨や歯の健康を維持する
- ホルモンバランスに関わる
- 生殖機能をサポートする
- 体温調節に関与する
特に冬は腎が最も活発に働く季節。だからこそ、秋のうちから腎を養う準備が大切なんですね。
塩が腎を養うメカニズム
東洋医学では、味にも五つの種類があると考えられています。これを「五味(ごみ)」と呼びます。
その中で塩の「鹹味(かんみ)」は、腎に作用すると言われているんです。
鹹味には以下のような働きが期待されています。
- 体の深部まで栄養を届ける
- 硬くなったものを柔らかくする
- 体内の余分な熱を冷ます
- 腎の働きをサポートする
ただし、これは適量の良質な塩を摂った場合のお話。摂りすぎや質の悪い塩では、逆に体に負担をかけてしまうこともあるので注意が必要です。(個人差があります)
秋から冬にかけての体の変化
秋から冬にかけて、私たちの体には大きな変化が起こります。
気温が下がることで、体は自然とエネルギーを内側に蓄えようとするんです。これは冬を乗り切るための体の知恵なんですよ。
でも、この時期に体が弱っていると…
- 手足の冷えが強くなる
- むくみやすくなる
- 疲れが取れにくい
- 腰がだるい、重い
- トイレが近くなる
こんな症状が出やすくなると言われています。
だからこそ、秋のうちから塩の質を見直し、腎を養う食養生を始めることが大切なんです!
冬に向けた体づくりについては、こちらの記事もご参考にしてくださいね。
冬に向けて体力を蓄える!11月の無理しない養生法で元気に冬を迎える
天然塩と精製塩の違い|体への影響を知ろう
「塩なんてどれも同じでしょ?」そう思っていませんか?
実は、塩の種類によって体への影響は大きく変わってくるんです。まずは天然塩と精製塩の違いを見ていきましょう。
精製塩(食卓塩)の特徴と問題点
スーパーで「食卓塩」として売られている白い塩。これが精製塩です。
精製塩は、海水から塩化ナトリウムだけを取り出して作られています。製造過程で、本来海水に含まれていたミネラル分がほとんど失われてしまうんです。
精製塩の特徴
- 成分のほぼ99%が塩化ナトリウム
- マグネシウム、カリウムなどのミネラルがほぼゼロ
- 価格が安い
- 真っ白でサラサラしている
精製塩ばかりを使っていると、ミネラル不足になりやすいと言われています。また、塩化ナトリウムだけの塩分摂取は、体内のミネラルバランスを崩す原因になることがあるんです。
天然塩に含まれるミネラルの働き
一方、天然塩には海のミネラルがたっぷり含まれています✨
特に重要なミネラルとその働きを見てみましょう。
マグネシウム
- 筋肉の緊張をほぐすサポート
- エネルギー代謝に関わる
- 骨の健康維持をサポート
カリウム
- 体内の余分な水分排出をサポート
- むくみケアに役立つと言われている
- ナトリウムとのバランスを保つ
カルシウム
- 骨や歯の健康維持
- 神経伝達のサポート
- 筋肉の収縮に関わる
これらのミネラルは、一般的に体の様々な機能をサポートすると言われています。(個人差があります)
ミネラルバランスと体の巡りの関係
東洋医学では、体の中を「気・血・水」が巡っていると考えます。
この巡りがスムーズだと、私たちは元気で健康でいられるんですね。逆に巡りが滞ると、冷えやむくみ、疲労感などが現れやすくなると言われています。
ミネラルバランスの取れた塩は、体の「水」の巡りをサポートすると考えられているんです。
特に冬は水分代謝が滞りやすい季節。だからこそ、ミネラル豊富な天然塩で体の巡りを整えることが大切なんですよ!
体を温める食材についても、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。
冬に向けた体づくりのための塩の選び方
「天然塩がいいのは分かったけど、どうやって選べばいいの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いはず。ここからは、具体的な塩の選び方をお伝えしていきますね。
天日干し・平釜製法の海塩を選ぶ
天然塩にもいろいろな製法があります。その中でも特におすすめなのが、天日干しや平釜製法で作られた海塩です。
天日干し製法
太陽と風の力だけで海水を濃縮し、結晶化させる伝統的な製法。時間はかかりますが、ミネラルバランスが良く、まろやかな味わいになると言われています。
平釜製法
海水を平らな釜でゆっくり煮詰めて作る製法。職人さんが火加減を調整しながら丁寧に作り上げます。こちらもミネラルが豊富で、甘みや旨みを感じられる塩になるんです。
パッケージに「粗塩」「自然塩」「天日塩」などの表示があるものを選ぶといいですよ。
産地や製法を確認する
塩を選ぶ時は、パッケージの裏側をよく見てみましょう。
チェックポイント
- 産地が明記されているか
- 製法が書かれているか
- 添加物が入っていないか
- 成分表示にミネラルが含まれているか
国内産の塩なら、沖縄、瀬戸内、能登などが有名ですね。それぞれの産地で、海水の成分や気候が異なるため、塩の味わいも変わってくるんですよ。
添加物については、固結防止剤などが入っていないものを選ぶのがおすすめです。
厚生労働省の食事摂取基準も参考にしながら、適切な塩分量を心がけましょう。
自分の体に合う塩を見つける
塩選びで大切なのは、「自分の体に合うかどうか」なんです。
同じ天然塩でも、産地や製法によって味わいは様々。まずは少量から試してみて、体の反応を観察してみましょう。
こんな風に観察してみてください
- 味がまろやかで美味しく感じるか
- その塩を使った後、体がどう感じるか
- むくみや冷えに変化はあるか
- 続けられそうな価格か
また、料理によって塩を使い分けるのもおすすめです。例えば、煮物には甘みのある塩、焼き物にはシンプルな塩など。自分なりの使い分けを楽しんでみてくださいね!
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な食養生をご提案いたします。
塩の選び方や日々の食事について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
東洋医学的な塩の使い方と食養生のコツ
良い塩を選んだら、次は使い方です!東洋医学の知恵を活かした塩の使い方をご紹介しますね。
朝の味噌汁で1日の気の巡りをサポート
東洋医学では、朝は陽気が上がり始める大切な時間帯と考えられています。
この時間帯に適量の塩分を摂ることで、1日の気の巡りをサポートすると言われているんです。
おすすめの朝食メニュー
- 天然塩と味噌を使った具だくさん味噌汁
- わかめや昆布などの海藻類をたっぷり入れる
- 根菜類(大根、ごぼう、人参)も加える
- 豆腐や油揚げでタンパク質もプラス
味噌自体も発酵食品で体に優しいですし、天然塩との相性も抜群なんですよ✨
朝にしっかり塩分を摂ることで、日中の活動をサポートできると考えられています。(個人差があります)
シンプルな味付けで素材の味を活かす
良質な天然塩を使うなら、シンプルな味付けがおすすめです。
余計な調味料を使わず、塩だけで味付けすることで、素材本来の美味しさを楽しめますし、添加物も避けられます。
シンプル塩レシピ例
塩むすび
炊きたてご飯に天然塩をまぶすだけ。お米の甘みと塩のまろやかさが絶品です。
塩焼き
魚や野菜に塩を振って焼くだけ。素材の旨みが際立ちます。
塩茹で
野菜を天然塩入りのお湯で茹でる。野菜の甘みが引き出されます。
シンプルだからこそ、塩の質が味を左右します。ぜひ美味しい天然塩で試してみてくださいね。
薬膳レシピについては、こちらの記事も参考にしてください。
塩分摂取量の目安と注意点
良質な天然塩でも、摂りすぎは禁物です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」によると、成人女性の1日の塩分摂取量の目標値は6.5g未満とされています。
塩分摂取のポイント
- 加工食品には塩分が多く含まれているので要注意
- 外食時は塩分が多めになりがち
- 自宅での調理では、天然塩を使って適量を心がける
- 水分補給も忘れずに(1日1.5〜2リットルが目安)
また、持病のある方や医師から塩分制限を指示されている方は、必ず医師の指導に従ってくださいね。
天然塩だから大丈夫、というわけではありません。あくまでも適量を守ることが大切です。
腎を養う食材と天然塩の組み合わせ方
天然塩の力を最大限に活かすには、腎を養う食材との組み合わせがポイントです!
冬に向けた体づくりにぴったりの食材をご紹介しますね。
黒い食材(黒豆・黒ごま)との相性
東洋医学では、「黒い食材は腎を養う」と言われています。
五行説では、色にもそれぞれ対応する臓腑があり、黒色は腎に対応するんです。だから、黒い食材と天然塩を組み合わせることで、より腎のサポートが期待できるんですよ。
おすすめの黒い食材
黒豆
- タンパク質、ミネラルが豊富
- イソフラボンも含まれる
- 煮物に天然塩を少し加えると美味しい
黒ごま
- カルシウム、鉄分が豊富
- 抗酸化作用が期待される成分を含む
- 天然塩と混ぜて「黒ごま塩」に
黒ごま塩の作り方
黒ごまを炒って香りを出し、天然塩と混ぜるだけ。ご飯にかけたり、おひたしにかけたり、いろいろ使えて便利ですよ!
黒きくらげ、黒米なども腎を養う食材として知られています。(個人差があります)
海藻類と根菜類で巡りをサポート
海藻類も腎を養う食材として優秀なんです。
海藻類にはもともと海のミネラルがたっぷり。天然塩との相性も抜群です。
おすすめの海藻類
- わかめ:カリウム、マグネシウムが豊富
- 昆布:ヨウ素、カルシウムが豊富
- ひじき:鉄分、カルシウムが豊富
そして、根菜類も冬の体づくりには欠かせません。
おすすめの根菜類
- 大根:消化をサポートする
- ごぼう:食物繊維が豊富
- れんこん:ビタミンCが豊富
- 人参:βカロテンが豊富
これらの根菜類は、体を温める性質があると言われています。天然塩で味付けして、じっくり煮込むのがおすすめです。
簡単レシピ:根菜の煮物
- 大根、ごぼう、れんこん、人参を食べやすい大きさに切る
- 鍋に入れて、ひたひたの水を加える
- 天然塩、醤油、みりんで味付け
- 弱火でコトコト煮込む
シンプルですが、体が温まる優しい味わいです✨
温かい調理法で体を温める
秋から冬にかけては、調理法も大切なポイントです。
生野菜サラダよりも、加熱した野菜の方が体を温めると言われています。
おすすめの調理法
煮る
じっくり煮込むことで、食材が柔らかくなり、消化もしやすくなります。煮汁にも栄養が溶け出すので、スープごと食べましょう。
蒸す
蒸し料理は、食材の栄養を逃さず調理できます。野菜を蒸して天然塩をかけるだけでも美味しいです。
炒める
油を使って炒めることで、体を温める効果が期待できます。ごま油と天然塩で炒めものはいかがですか?
おすすめメニュー:具だくさん鍋
鍋料理は、これからの季節にぴったりですね。海藻、根菜、黒い食材を入れた鍋に、天然塩ベースのスープ。体の芯から温まりますよ。
発酵食品との組み合わせについても、こちらの記事で詳しく解説しています。
冬に向けた腸活養生!発酵食品で体の巡りをサポートする東洋医学的アプローチ
スタジオシュカ鍼灸治療院での季節養生サポート
ここまで、塩の選び方や食養生についてお伝えしてきました。
でも、「自分の体質に合っているか分からない」「一人で続けられるか不安」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな時は、ぜひ専門家を頼ってください。スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせた季節養生をサポートさせていただいています。
体質に合わせた食養生アドバイス
東洋医学では、一人ひとりの体質を丁寧に見極めることを大切にしています。
当院では、まずあなたの体質をチェック。その上で、あなたに合った食養生のアドバイスをさせていただきます。
体質チェックの内容
- 舌の状態を見る(舌診)
- 脈の状態を確認(脈診)
- お腹の状態をチェック(腹診)
- 日常の症状や体調をヒアリング
これらの情報をもとに、あなたに最適な塩の使い方、食材の選び方をお伝えします。
例えば、「冷えが強い方」と「むくみが強い方」では、おすすめする食材や塩の量が変わってくるんですよ。(個人差があります)
鍼灸で腎の働きをサポート
食養生に加えて、鍼灸施術でも腎の働きをサポートすることができます。
東洋医学では、体表面にある「ツボ(経穴)」を刺激することで、体のバランスを整えると考えられています。
腎に関連する代表的なツボ
腎兪(じんゆ)
腰の辺りにあるツボ。腎の働きをサポートすると伝統的に言われています。
関元(かんげん)
おへその下にあるツボ。生命エネルギーを養うと考えられています。
太渓(たいけい)
足首の内側にあるツボ。腎経の重要なポイントとされています。
これらのツボに鍼やお灸でアプローチすることで、冷えやむくみ、疲労感などのケアをサポートします。(効果には個人差があります)
鍼灸は医療行為の代替ではありませんが、体質改善のサポートとして活用していただけます。
腎のケアについては、こちらの記事も参考になりますよ。
35歳以降の妊活に必要な”腎”のケア!更年期予防にもつながる補腎生活習慣
冬に向けた体づくりの継続サポート
季節養生で大切なのは「継続」です。
でも、一人で続けるのはなかなか難しいもの。だからこそ、定期的にサポートを受けることをおすすめしています。
継続サポートの内容
- 定期的な体質チェック
- 季節に応じた食養生アドバイスの更新
- 生活習慣の見直しサポート
- 鍼灸施術による体調管理
松戸、流山、我孫子方面からもアクセスしやすい立地にあります。お仕事帰りやお休みの日に、気軽にお立ち寄りいただけますよ。
一緒に、冬に負けない体づくりを始めませんか?
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ|塩の質を見直して冬に負けない体づくりを
ここまで、塩の選び方と冬に向けた食養生についてお伝えしてきました。
最後にもう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。
塩選びのポイント
- 天然塩(天日干し・平釜製法)を選ぶ
- ミネラルバランスが大切
- 産地や製法を確認する
- 自分の体に合う塩を見つける
東洋医学的な塩の使い方
- 朝の味噌汁で気の巡りをサポート
- シンプルな味付けで素材を活かす
- 適量を守る(女性は6.5g未満が目安)
腎を養う食材との組み合わせ
- 黒い食材(黒豆、黒ごま)
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじき)
- 根菜類(大根、ごぼう、れんこん)
- 温かい調理法を心がける
冬はもうすぐそこまで来ています。今から準備を始めれば、きっと元気に冬を迎えられますよ✨
塩の質を見直すことは、毎日の食事を見直すこと。そして、自分の体を大切にすることにつながります。
小さな一歩から始めてみませんか?
まずは、いつも使っている塩を天然塩に変えてみる。朝の味噌汁に海藻や根菜を加えてみる。そんな小さな変化でも、体は必ず応えてくれるはずです。
あなたの体が、この冬も元気で過ごせますように。心から応援しています!
もし、体質改善や季節養生についてもっと知りたいと思われたら、いつでもスタジオシュカにご相談くださいね。
一緒に、冬に負けない体づくりを始めましょう😊
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
栄養に関する専門的な情報については、国立健康・栄養研究所のサイトも参考にしてください。
