風邪をひきやすい季節の変わり目に!体を守る東洋医学的セルフケア【松戸・流山・我孫子から10分の女性の悩み専門の鍼灸】
2025-11-06 季節の養生法
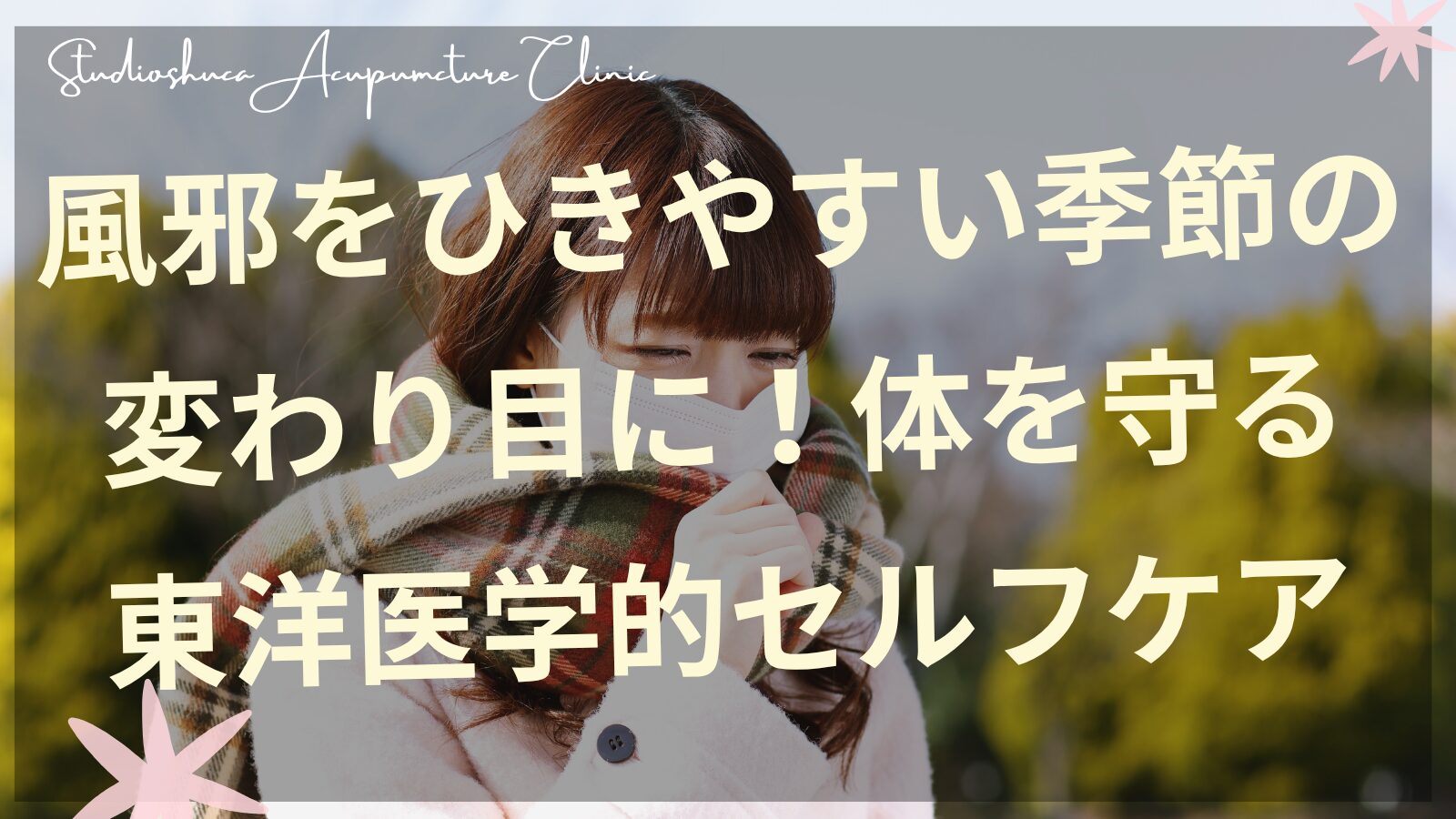
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
季節の変わり目になると、必ず風邪をひいてしまう…そんなお悩みはありませんか?
朝晩の寒暖差が大きくなるこの時期、喉がイガイガしたり、鼻水が出たり、体がだるくて重い…そんな症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
実は、季節の変わり目に体調を崩しやすいのには、東洋医学的な理由があるんです!
この記事では、東洋医学の視点から見た風邪をひきやすい理由と、自宅で今日から実践できるセルフケア方法をご紹介します。
この記事を読むとわかること:
- 季節の変わり目に風邪をひきやすい東洋医学的な理由
- 体を守る力「衛気」を高める具体的な方法
- 免疫力をサポートする食材と生活習慣
- 自宅でできる簡単なツボ押しと呼吸法
こんな方におすすめ:
- 季節の変わり目に必ず体調を崩してしまう方
- 薬に頼らず自然な方法で風邪予防をしたい方
- 東洋医学に興味がある30代~50代の女性
- 家族の健康も守りたいと考えている方
それでは、季節の変わり目を元気に乗り越えるための東洋医学の知恵を見ていきましょう♪
季節の変わり目の不調でお悩みの方へ
寒暖差で体調を崩しやすいこの時期、東洋医学の視点からあなたの体質に合わせた養生法をご提案いたします。
もし季節の変わり目を元気に乗り切りたいとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
季節の変わり目に風邪をひきやすいのはなぜ?
寒暖差が体に与える影響
10月は朝晩の気温差が10度以上になることも珍しくありません。
この寒暖差は、私たちの体に大きな負担をかけるんです。
一般的に、急激な温度変化は自律神経のバランスを乱すと言われています。自律神経は体温調節や免疫機能を司る大切な役割を持っているため、そのバランスが崩れると体調を崩しやすくなるのです。
特に朝は気温が低く、日中は暖かくなり、夜はまた冷え込む…この繰り返しで体が疲れてしまうんですね。
東洋医学から見た「衛気」の役割
東洋医学では、体を外敵から守る力を「衛気(えき)」と呼びます。
衛気とは、体の表面を巡ってバリアのように働くエネルギーのことです。この衛気がしっかりと体を守っていると、風邪の邪気(外から侵入してくる悪いもの)を跳ね返すことができると考えられています。
しかし、季節の変わり目で疲れが溜まったり、寒暖差で体が冷えたりすると、衛気が弱くなってしまうんです。
衛気が弱まると、風邪の邪気が体内に侵入しやすくなり、風邪をひきやすい状態になってしまいます。
秋は「肺」の季節
東洋医学の五行説では、秋は「肺」の季節とされています。
肺は呼吸を司るだけでなく、衛気を全身に巡らせる役割も担っていると考えられているんです!
秋になると空気が乾燥し、肺はダメージを受けやすくなります。肺が弱ると衛気の働きも低下し、風邪をひきやすくなるという仕組みです。
つまり、秋の養生では「肺を守り、潤す」ことが風邪予防の鍵となるんですね。
秋の乾燥対策については、こちらの記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
東洋医学から見た風邪予防の考え方
「肺」と免疫力の関係
東洋医学では、肺は「皮膚」と深く関係していると考えられています。
これを「肺主皮毛(はいしゅひもう)」と言います。肺の機能が正常であれば、皮膚も健やかに保たれ、外からの邪気を防ぐバリア機能が働くとされているんです。
逆に、肺が弱ると皮膚も弱くなり、風邪をひきやすくなったり、肌荒れしやすくなったりします。
一般的にも、呼吸器系と免疫機能には関連があるとされており、東洋医学の考え方と通じるものがありますね。
気・血・水のバランスと体調
東洋医学では、体を構成する基本要素として「気・血・水」という概念があります。
- 気:体を動かすエネルギー
- 血:栄養を運ぶもの
- 水:体を潤すもの
この3つがバランスよく巡っていると、体は健やかに保たれます。
しかし、季節の変わり目で気候が不安定になると、このバランスが崩れやすくなるんです。特に「気」が不足すると疲れやすくなり、「水」が不足すると乾燥症状が現れます。
風邪予防には、この気・血・水のバランスを整えることが大切だと考えられています。
五行説から見る秋の養生
東洋医学の五行説では、秋は「金」に属します。
金の臓器は「肺」と「大腸」。この時期はこれらの臓器を労わることが養生の基本です。
秋の特徴は「乾燥」。この乾燥が肺を傷つけやすいため、潤いを保つ食材を積極的に取り入れることが勧められています。
また、秋は夏の暑さで消耗した体を回復させる大切な時期でもあります。無理をせず、ゆったりと過ごすことも重要な養生法なんですよ♪
季節の変わり目の自律神経ケアについては、こちらの記事も参考になります。
体を守る力をサポートする5つの生活習慣
ここからは、具体的に自宅でできる風邪予防の方法をご紹介します!
どれも今日から始められる簡単なものばかりですので、ぜひ試してみてくださいね。
1. 体を温める習慣づくり
朝の白湯の習慣
朝起きたら、まず一杯の白湯を飲む習慣をつけましょう。
東洋医学では、温かい飲み物は内臓を温め、気の巡りをサポートすると言われています。朝は体温が低く、体も冷えがちです。白湯で体の中から温めることで、一日を元気にスタートできます!
作り方は簡単。水を沸騰させて、50度くらいまで冷ましたものをゆっくり飲むだけです。
「三首」を冷やさないポイント
東洋医学では、首・手首・足首の「三首」は衛気の出入り口とされています。
ここを冷やすと、体全体が冷えやすくなり、風邪をひきやすくなると考えられているんです。
- 首:スカーフやストールで保護
- 手首:長袖の服を着る、手首ウォーマーを使う
- 足首:靴下やレッグウォーマーで温める
特に朝晩の冷え込みが厳しい日は、しっかりガードしましょう!
入浴で体の芯から温める方法
シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣をつけることが大切です。
理想的な入浴方法は以下の通りです:
- 温度:38~40度のぬるめのお湯
- 時間:15~20分程度
- タイミング:就寝の1~2時間前
熱すぎるお湯は体に負担がかかりますし、長時間の入浴は逆に疲れてしまいます。ゆったりとリラックスできる温度と時間を心がけましょう。
入浴剤に生姜やゆずを入れると、さらに体が温まりますよ♪
腹巻きやレッグウォーマーの活用
就寝時も体を冷やさないよう、腹巻きやレッグウォーマーを活用しましょう。
お腹には大切な臓器が集まっています。ここを温めることで、内臓の働きがサポートされ、全身の巡りも良くなると言われています。
2. 肺を潤す食材の選び方
東洋医学では、肺は乾燥を嫌う臓器とされています。
秋の乾燥から肺を守るために、潤いをもたらす食材を積極的に取り入れましょう!
白い食材の効果
五行説では、白い食材は肺を潤すと考えられています。
- 大根:消化をサポートし、潤いをもたらす
- 白菜:水分が豊富で体を潤す
- れんこん:粘り成分が喉や肺を保護
- 山芋:滋養強壮に良いとされる
- 梨:喉の乾燥に良いとされる果物
- 白きくらげ:美容と潤いの食材
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、体の内側から潤いをキープできます。
潤いをもたらす食材
- はちみつ:喉を潤し、咳を和らげるとされています。温かい飲み物に混ぜて飲むのがおすすめです。
- ゆり根:精神を安定させ、肺を潤すとされる食材です。茶碗蒸しやスープに入れて食べましょう。
- 杏仁:咳や喉の不調に良いとされています。杏仁豆腐として楽しむのも良いですね。
具体的な献立例
朝食:白湯 + 山芋のすりおろし + 梅干し
昼食:大根と鶏肉のスープ + ごはん
夕食:れんこんとしいたけの炊き込みご飯 + 白菜と豆腐の味噌汁
間食:はちみつ入りのホットレモン、梨
このように、白い食材や潤いをもたらす食材を組み合わせた献立を意識してみてください♪
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な風邪予防の養生法をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
3. 免疫力をサポートするツボ押し
東洋医学では、特定のツボを刺激することで体の巡りを整え、体を守る力をサポートすると考えられています。
ここでは、風邪予防に役立つとされる3つのツボをご紹介します。1日2~3回、各3~5分程度優しく刺激してみてください。
足三里(あしさんり)
位置:膝のお皿の外側、指4本分下のくぼみ
効果:元気を補い、体全体の巡りをサポートすると言われています。胃腸の働きを整える作用も期待されています。
押し方:親指でゆっくりと円を描くように押しましょう。少し痛いけど気持ちいいくらいの強さがちょうど良いです。
合谷(ごうこく)
位置:手の甲、親指と人差し指の骨が交わるくぼみ
効果:万能のツボとして知られ、風邪の初期症状のケアに用いられます。頭痛や喉の痛みにも良いとされています。
押し方:反対の手の親指と人差し指で挟むように押します。3~5秒押して、ゆっくり離すを繰り返しましょう。
大椎(だいつい)
位置:首を前に倒したときに最も出っ張る骨の下のくぼみ
効果:風邪の邪気が入る場所とされ、ここを温めることが風邪予防につながると考えられています。
押し方・温め方:指で優しく押すか、ドライヤーの温風を30秒~1分当てる、使い捨てカイロを貼るなどの方法があります。
※ツボ押しは個人の体質により体験に個人差があります。気分が悪くなった場合はすぐに中止してください。
4. 呼吸法で肺の働きをサポート
深い呼吸は、肺の機能を高め、気の巡りを整えるとされています。
忙しい日々の中で、私たちはつい浅い呼吸になりがちです。意識的に深呼吸を行うことで、自律神経のバランスも整いやすくなります。
腹式呼吸の実践方法
- 背筋を伸ばして楽な姿勢で座る
- 鼻からゆっくり4秒かけて息を吸う(お腹を膨らませる)
- 2秒息を止める
- 口からゆっくり8秒かけて息を吐く(お腹をへこませる)
- これを5~10回繰り返す
実践のタイミング
- 朝起きた時:一日を元気に始めるために
- 就寝前:リラックスして質の良い睡眠へ
- 仕事の合間:リフレッシュに
深い呼吸を続けることで、体の緊張がほぐれ、心も落ち着いてきます。ぜひ習慣にしてみてくださいね!
5. 質の良い睡眠を取る
東洋医学では、夜の10時~深夜2時は「気血」が作られる大切な時間とされています。
この時間帯に質の良い睡眠を取ることで、体を守る力が高まると考えられているんです。
一般的にも、睡眠中に成長ホルモンが分泌され、免疫機能が整うことが知られています。十分な睡眠は風邪予防の基本ですね!
睡眠の質を高める生活習慣
- 就寝2時間前には食事を済ませる:消化活動が落ち着いてから眠る
- 寝る1時間前にはスマホやパソコンの使用を控える:ブルーライトが睡眠を妨げます
- 寝室を暗く、静かに保つ:遮光カーテンや耳栓の活用も
- 寝具を清潔に保つ:週に一度はシーツを洗濯
- 室温を適温に保つ:18~20度が理想的
アロマの活用
ラベンダーやカモミールの香りは、リラックス効果があると言われています。アロマディフューザーや枕元にアロマスプレーを使うのもおすすめです。
睡眠については、厚生労働省の健康づくりのための睡眠ガイドも参考になります。
秋の温活については、こちらの記事もご覧ください。
鍼灸で体を守る力をサポート
鍼灸が体にもたらす期待される体験
鍼灸施術では、体の特定のポイント(ツボ)に鍼やお灸で刺激を与えます。
伝統的に、この刺激が気の巡りを整え、体のバランスを整えるサポートをすると考えられてきました。
施術中は、多くの方が以下のような体験をされます:
- 体が温かくなる感覚
- 筋肉の緊張がほぐれる
- リラックスして眠くなる
- 呼吸が深くなる
※個人の体質により体験には個人差があります。効果を保証するものではありません。
スタジオシュカの季節養生アプローチ
スタジオシュカでは、東洋医学の考え方に基づき、季節に合わせた養生のお手伝いをしています。
秋の季節には、以下のようなアプローチでサポートさせていただいています:
- 肺経・大腸経のツボを中心とした施術
- 体質診断に基づいた個別のアドバイス
- 自宅でできるセルフケアのご提案
- 食事や生活習慣のサポート
一人ひとりの体質や生活環境に合わせて、最適な養生法をご提案いたします。
自宅ケアと鍼灸の組み合わせ
自宅でのセルフケアは毎日の積み重ねが大切です。
そこに定期的な鍼灸施術を組み合わせることで、より深いレベルでのケアが期待できます。
例えば:
- 月に2~4回の鍼灸施術で体の土台を整える
- 日々のセルフケアでその状態を維持する
- 季節の変わり目には特に集中してケアする
このような組み合わせで、一年を通じて元気に過ごせる体づくりをサポートいたします。
※鍼灸は医療行為の代替ではありません。体調が優れない場合は医療機関を受診してください。
よくあるご質問
Q1: 風邪の引き始めにできることはありますか?
A:風邪の引き始めかな?と感じたら、早めの対応が大切です。
以下のことを試してみてください:
- すぐに休む:無理をせず、早めに帰宅して休息を取りましょう
- 大椎のツボを温める:ドライヤーの温風を30秒~1分当てる、または使い捨てカイロを貼る
- 温かいスープを飲む:生姜入りのスープや大根のスープがおすすめです
- 早めに就寝:いつもより早く寝て、体を休めましょう
- 首元を温める:タオルやマフラーで首を保護
ただし、症状がひどい場合や長引く場合は、必ず医療機関を受診してください。
Q2: 食事以外で気をつけることはありますか?
A:食事以外にも、日常生活で気をつけたいポイントがあります。
適度な運動
激しい運動は逆効果ですが、軽いウォーキングやストレッチは気の巡りを整えるとされています。1日20~30分程度の散歩がおすすめです。
秋の運動については、こちらの記事も参考にしてください。
ストレス管理
ストレスは免疫機能に影響を与えると言われています。好きなことをする時間を作ったり、深呼吸やヨガでリラックスしたりすることが大切です。
室内の湿度管理
エアコンや暖房で室内が乾燥すると、喉や鼻の粘膜が乾燥して風邪をひきやすくなります。加湿器を使って湿度50~60%を保ちましょう。
気象庁の季節予報で気温の変化をチェックして、服装を調整するのも良いですね。
Q3: 鍼灸はどのくらいの頻度で受けると良いですか?
A:個人の体質や状態によって異なりますので、一概には言えません。
一般的な目安としては:
- 体調維持:月に2~4回
- 季節の変わり目:週に1回程度
- 体調が優れない時:週に1~2回
スタジオシュカでは、初回のカウンセリングでお体の状態を詳しくお伺いし、あなたに最適な施術計画をご提案いたします。
無理のない範囲で継続できることが大切ですので、ライフスタイルに合わせて調整していきましょう。
まとめ:季節の変わり目を元気に乗り切るために
いかがでしたか?
季節の変わり目に風邪をひきやすいのは、東洋医学では「衛気」の不足や「肺」の機能低下が関係していると考えられています。
今日からできることを少しずつ始めてみましょう!
まとめのポイント:
- 体を温める習慣(白湯、三首を守る、入浴)
- 肺を潤す白い食材を積極的に摂る
- ツボ押しで体を守る力をサポート
- 深い呼吸で気の巡りを整える
- 質の良い睡眠で体を回復させる
すべてを一度に始める必要はありません。できることから一つずつ、無理なく続けていくことが大切です。
あなたの体質に合わせたケアを知りたい、もっと専門的なサポートが欲しいという方は、ぜひスタジオシュカにご相談ください。
東洋医学の知恵を活かして、季節の変わり目も元気に過ごしていきましょう!
あなたの健やかな毎日を、心から応援しています♪
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
免責事項
個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。鍼灸は医療行為の代替ではありません。体調が優れない場合は医療機関を受診してください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
