秋の味覚で体を整える!栗・さつまいも・柿の薬膳効果と食べ方【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-10-02 季節の養生法
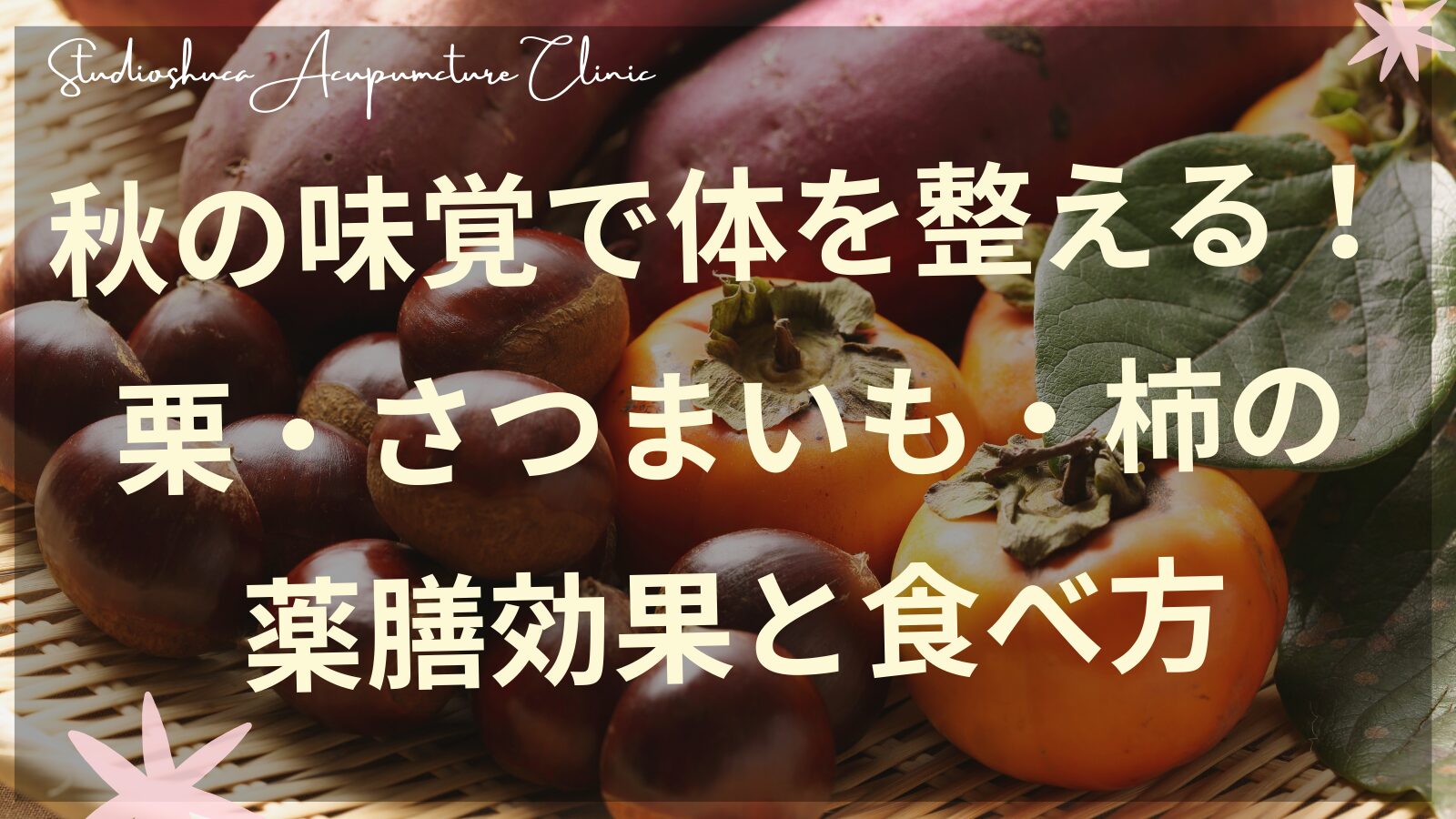
東洋医学から見た秋の体の変化と食養生の大切さ
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
秋の気配を感じる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか?「最近肌が乾燥してカサカサになってきた」「のどがイガイガして咳が出やすい」「食欲の秋で食べ過ぎて胃腸の調子が…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
実は、これらの不調は季節の変わり目に起こりがちな体の自然な反応なんです!東洋医学では、秋は「肺」の季節と言われ、乾燥による影響を受けやすい時期とされています。
この記事を読むとわかること:
- 栗・さつまいも・柿の薬膳的効果と体への働きかけ
- 秋の不調をサポートする具体的な食べ方
- 東洋医学に基づいた季節養生の実践方法
- 日常に取り入れやすい秋の食材活用法
この記事はこんな方向け:
- 秋の味覚を健康的に楽しみたい30代40代50代の女性
- 季節の変わり目の不調が気になる方
- 東洋医学や薬膳に興味がある方
- 自然な方法で体調をケアしたい方
今日は、秋の代表的な味覚である栗・さつまいも・柿を使った、体に優しい薬膳的なアプローチをお伝えします。最後まで読んでいただければ、きっと今日から実践したくなるはずですよ✨
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
秋は「肺」の季節~乾燥に注意が必要な理由
東洋医学の五行説では、秋は「金」に属し、「肺」と深い関わりがあるとされています。肺は呼吸を司るだけでなく、皮膚や鼻、のどなど体の表面を守る働きも担っていると考えられているんです。
秋になると空気が乾燥し、この「肺」の機能が影響を受けやすくなります。そのため、次のような症状が現れやすいと言われています:
- 肌のカサつきや乾燥
- のどの渇きや咳
- 鼻の乾燥やムズムズ感
- 便秘がちになる
これらは体が季節の変化に適応しようとしている自然な反応なので、心配しすぎる必要はありません。大切なのは、適切な食べ物で体をサポートしてあげることなんです🍂
季節の変わり目に起こりやすい体の変化
秋は夏の暑さから冬の寒さへと移り変わる季節です。この時期は気温の変化が激しく、体も大きな変化を経験します。
一般的に、以下のような変化が起こりやすいとされています:
- 気の流れの変化:夏に活発だった「気」の動きが、冬に向けて内側に向かい始める
- 血液循環の変化:外気温の低下により、体の表面への血流が減少する傾向
- 水分代謝の変化:汗をかく量が減り、体内の水分バランスが変わる
これらの変化は自然なものですが、急激すぎると体調不良の原因になることがあります。そこで重要になるのが、食べ物による体のサポートなんです!
食べ物で体を整える「薬膳」の基本的な考え方
薬膳というと難しそうに感じるかもしれませんが、実はとてもシンプルな考え方なんです✨
薬膳では、食べ物にはそれぞれ「性質」があると考えられています:
- 温性・熱性:体を温める働きが期待される(栗、しょうが、にんにくなど)
- 涼性・寒性:体を冷やす働きが期待される(柿、きゅうり、トマトなど)
- 平性:温めも冷やしもしない穏やかな性質(米、じゃがいも、キャベツなど)
季節や体質に合わせてこれらの食材をバランス良く取り入れることで、体の調子を整えることが期待できます。個人差がありますので、ご自身の体調と相談しながら取り入れることが大切です。
栗の薬膳効果~体を温めて「腎」をサポート
秋の味覚といえば、まず思い浮かぶのが栗ですよね!栗は見た目も可愛らしく、食べると心もほっこりする食材です🌰
栗が持つ東洋医学的な性質と体への働きかけ
東洋医学では、栗は「温性」の食材として分類されています。これは、体を温める働きが期待できることを意味します。
栗の主な特徴は以下の通りです:
- 「腎」をサポート:生命力の源とされる「腎」の働きを助けるとされています
- 体を温める:冷えやすい秋の体を内側から温める効果が期待されます
- 消化に優しい:胃腸に負担をかけにくく、消化しやすい食材と言われています
- 気を補う:疲れやすい時期のエネルギー補給をサポートすると考えられています
特に、朝晩の冷え込みで体が冷えやすいこの季節には、栗のような温性食材がとても重宝するんです!
効果的な栗の食べ方と摂取量の目安
栗を効果的に摂取するためのポイントをご紹介します:
摂取量の目安:
- 1日5~6粒程度が適量とされています
- 食べ過ぎると消化に負担をかける可能性があります
- 個人差がありますので、体調に合わせて調整してください
効果的な摂取タイミング:
- 朝食に取り入れると、一日のエネルギー源として期待できます
- 間食として午前中に食べるのもおすすめです
- 夜遅い時間は避け、消化の時間を考慮しましょう
栗を使ったおすすめの調理法
栗の栄養を効果的に摂取できる調理法をご紹介します:
1. 茹で栗:
- 最もシンプルで栗の甘みを味わえる方法です
- 20〜30分茹でて、自然な甘さを楽しみましょう
2. 蒸し栗:
- 栄養素の流出を抑えられる調理法です
- 蒸し器で15〜20分蒸すと、ホクホクの食感になります
3. 栗ご飯:
- 主食として取り入れやすい方法です
- お米と一緒に炊くことで、栗の甘みが全体に広がります
どの調理法も簡単で美味しいので、ぜひお試しください!
さつまいもの薬膳効果~消化力をサポートする優秀食材
秋の味覚で忘れてはならないのが、さつまいもです🍠甘くて美味しいだけでなく、体にとても優しい食材なんですよ!
「脾胃」を助けるさつまいもの特徴
東洋医学では、さつまいもは「平性」で「甘味」を持つ食材として分類されています。
さつまいもの主な働きは以下の通りです:
- 「脾胃」をサポート:消化器系の働きを助けると言われています
- 気を補う:エネルギーを補給し、疲労回復をサポートするとされています
- 血を養う:血液の質を良くする働きが期待されます
- 便通を良くする:食物繊維により、お通じの改善が期待できます
特に、食欲の秋で胃腸が疲れがちな時期には、消化に優しいさつまいもがぴったりなんです✨
腸内環境ケアが期待できる理由
さつまいもが腸内環境に良いとされる理由をご説明します:
豊富な食物繊維:
- 水溶性と不溶性の両方の食物繊維がバランス良く含まれています
- 善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善が期待されます
- お通じの改善にも役立つと言われています
ヤラピン:
- さつまいも特有の成分で、切った時に出る白い汁の正体です
- 腸の働きをサポートする作用があると言われています
ただし、個人差がありますので、体調に合わせて摂取量を調整することが大切です。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
体に優しいさつまいもの食べ方
さつまいもの栄養を最大限に活かす食べ方をご紹介します:
皮ごと食べる:
- 皮にも豊富な栄養が含まれています
- 食物繊維も皮に多く含まれているんです
- よく洗って、皮ごと調理しましょう
調理法による違い:
- 蒸し芋:栄養の流出が少なく、消化に優しいとされています
- 焼き芋:甘みが強く美味しいですが、消化には時間がかかる場合があります
- 煮物:他の食材と組み合わせやすく、バランス良く摂取できます
摂取量の目安:
- 1日100g程度(中サイズ半分程度)が目安です
- 食べ過ぎると胃腸に負担をかける可能性があります
- ゆっくりよく噛んで食べることが大切です
柿の薬膳効果~秋の乾燥対策に最適な潤い食材
「柿が赤くなれば医者が青くなる」という言葉があるように、柿は昔から体に良い食材として親しまれてきました🍅
体を潤し「肺」をケアする柿の働き
東洋医学では、柿は「涼性」の食材として分類され、特に秋の乾燥対策に適していると考えられています。
柿の主な特徴は以下の通りです:
- 体を潤す:乾燥による不調をケアする働きが期待されます
- 「肺」をサポート:呼吸器系の不調に対するケア効果が期待されます
- 熱を冷ます:体内の余分な熱を取り除く作用があると言われています
- のどを潤す:のどの乾燥や咳に対するケア効果が期待されます
特に、空気が乾燥しがちな秋には、柿のような潤い効果が期待できる食材がとても重宝するんです!
咳や喉の不調をサポートする摂取方法
柿を効果的に摂取する方法をご紹介します:
そのまま食べる:
- 最も手軽で、柿の栄養を丸ごと摂取できます
- よく熟した甘い柿を選びましょう
- 1日1個程度が目安です
柿茶として:
- 干し柿を熱湯で煮出してお茶として飲む方法です
- のどの乾燥が気になる時におすすめです
- 個人差がありますので、体調に合わせて調整してください
他の食材との組み合わせ:
- はちみつと組み合わせると、より潤い効果が期待できます
- 白きくらげと一緒にデザートとして楽しむのもおすすめです
体質別の柿の取り入れ方の注意点
柿は涼性の食材のため、体質によって注意が必要です:
冷え性の方:
- 食べ過ぎると体を冷やしすぎる可能性があります
- 温かい飲み物と一緒に摂取することをおすすめします
- 1日半個程度から始めて、体調を見ながら調整しましょう
胃腸が弱い方:
- 空腹時は避け、食後のデザートとして摂取しましょう
- よく熟した柔らかい柿を選ぶことが大切です
摂取に適したタイミング:
- 食後30分~1時間後がおすすめです
- 夜遅い時間は避け、消化の時間を考慮しましょう
体質には個人差がありますので、ご自身の体調と相談しながら取り入れることが大切です。
秋の三大食材を組み合わせた簡単薬膳レシピ
ここからは、栗・さつまいも・柿を使った簡単で美味しいレシピをご紹介します!どれも手軽に作れて、体に優しいものばかりですよ✨
体を温める栗とさつまいもの蒸し料理
栗とさつまいもの蒸し物
【材料(2人分)】
- 栗 6個(皮を剥いておく)
- さつまいも 1本(輪切りにする)
- 塩 少々
【作り方】
- 蒸し器に栗とさつまいもを入れます
- 強火で15~20分蒸します
- 竹串がスーッと通れば完成です
- お好みで塩を少し振ってお召し上がりください
この組み合わせは、栗の温性とさつまいもの平性がバランス良く、体を穏やかに温めてくれると期待されます。冷え対策にもおすすめです!
詳しい冷え対策については、こちらの記事でもご紹介しています。
潤いチャージの柿とはちみつのデザート
柿のはちみつ和え
【材料(2人分)】
- 柿 1個(食べやすい大きさに切る)
- はちみつ 大さじ1
- レモン汁 少々
【作り方】
- 柿を一口大に切ります
- はちみつとレモン汁を混ぜ合わせます
- 柿にかけて、軽く混ぜて完成です
- 10分ほど置くと、より味が馴染みます
はちみつも潤い効果が期待できる食材なので、柿との組み合わせで相乗効果が期待できます。のどの乾燥が気になる時にもおすすめです!
一週間の献立への取り入れ方
秋の三大食材を無理なく日常に取り入れる方法をご提案します:
月曜日:朝食に栗入りおかゆ
火曜日:おやつにふかしたさつまいも
水曜日:夕食後のデザートに柿
木曜日:お昼に栗ご飯
金曜日:間食にさつまいもチップス
土曜日:柿とヨーグルトのデザート
日曜日:栗とさつまいもの煮物
このように、毎日違う食材を取り入れることで、飽きずに続けることができます。また、体質に合わせて量や頻度を調整することも大切です。
消化に関するケアについては、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
スタジオシュカでの季節養生サポートについて
ここまで、秋の三大食材についてお話ししてきましたが、「自分の体質に本当に合っているかしら?」「もっと詳しく知りたい」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
東洋医学に基づいた体質診断とアドバイス
スタジオシュカでは、東洋医学の観点から一人ひとりの体質を丁寧に診させていただいています。
体質診断の内容:
- 舌診・脈診による体質チェック
- 生活習慣や症状の詳しいお聞き取り
- 季節に合わせた食材選びのアドバイス
- 個人の体質に適した養生法のご提案
例えば、冷え性の方には温性食材を中心に、熱がこもりやすい方には平性や涼性食材をバランス良く取り入れることをお勧めしています。
体質は一人ひとり異なりますので、専門家による個別のアドバイスが大切だと考えています。
鍼灸での秋の不調ケアアプローチ
食養生と合わせて、鍼灸による体のケアも効果的だと言われています:
秋の不調に対するアプローチ:
- 肺経のツボを使った呼吸器ケア
- 脾胃経のツボによる消化力サポート
- 腎経のツボを使った冷え対策
- 自律神経を整える全身調整
これらのアプローチにより、体の内側から季節の変化に適応しやすい状態づくりをサポートします。ただし、効果には個人差があり、施術効果を保証するものではありません。
厚生労働省でも、鍼灸の安全性と有用性について情報が提供されています。
個人に合わせた食養生指導
当院では、施術と合わせて日常生活での食養生についてもアドバイスさせていただいています:
個別指導の内容:
- 体質に合った食材選びの具体的なアドバイス
- 調理法による効果の違いのご説明
- 季節ごとの養生ポイントのご提案
- 継続しやすい取り入れ方のご相談
食べ物は毎日のことですので、無理なく続けられる方法を一緒に見つけていくことを大切にしています。
季節に合わせた食材の選び方については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ
今日は、秋の三大食材である栗・さつまいも・柿の薬膳的な活用法についてお話しさせていただきました✨
大切なポイントをおさらいします:
- 栗:体を温めて「腎」をサポート、1日5~6粒が目安
- さつまいも:消化力をサポートし腸内環境ケアに期待、1日100g程度
- 柿:体を潤し「肺」をケア、1日1個程度が目安
これらの食材は、それぞれ異なる性質を持っているため、バランス良く取り入れることが大切です。また、体質には個人差がありますので、ご自身の体調と相談しながら楽しんでくださいね。
秋は「食欲の秋」と言われるように、美味しい食材が豊富な季節です。ただ食べるだけでなく、東洋医学の知恵を活かして体をサポートする食べ方を実践することで、より健やかに過ごすことができるでしょう。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもありますが、適切な食養生で体をいたわってあげることで、冬に向けた体づくりができると考えられています。
もし「自分の体質がよくわからない」「もっと詳しく知りたい」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。一人ひとりに合わせたアドバイスで、あなたの季節養生をサポートさせていただきます!
素敵な秋の味覚とともに、健やかな毎日をお過ごしくださいね🍂
免責事項:
個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
農林水産省でも、食材の栄養や安全性について詳しい情報が提供されています。
