風邪でもないのに咳が止まらない!秋の長引く咳をケアする東洋医学的アプローチ【松戸・流山・我孫子から10分の女性の悩み専門の鍼灸】
2025-10-14 季節の養生法
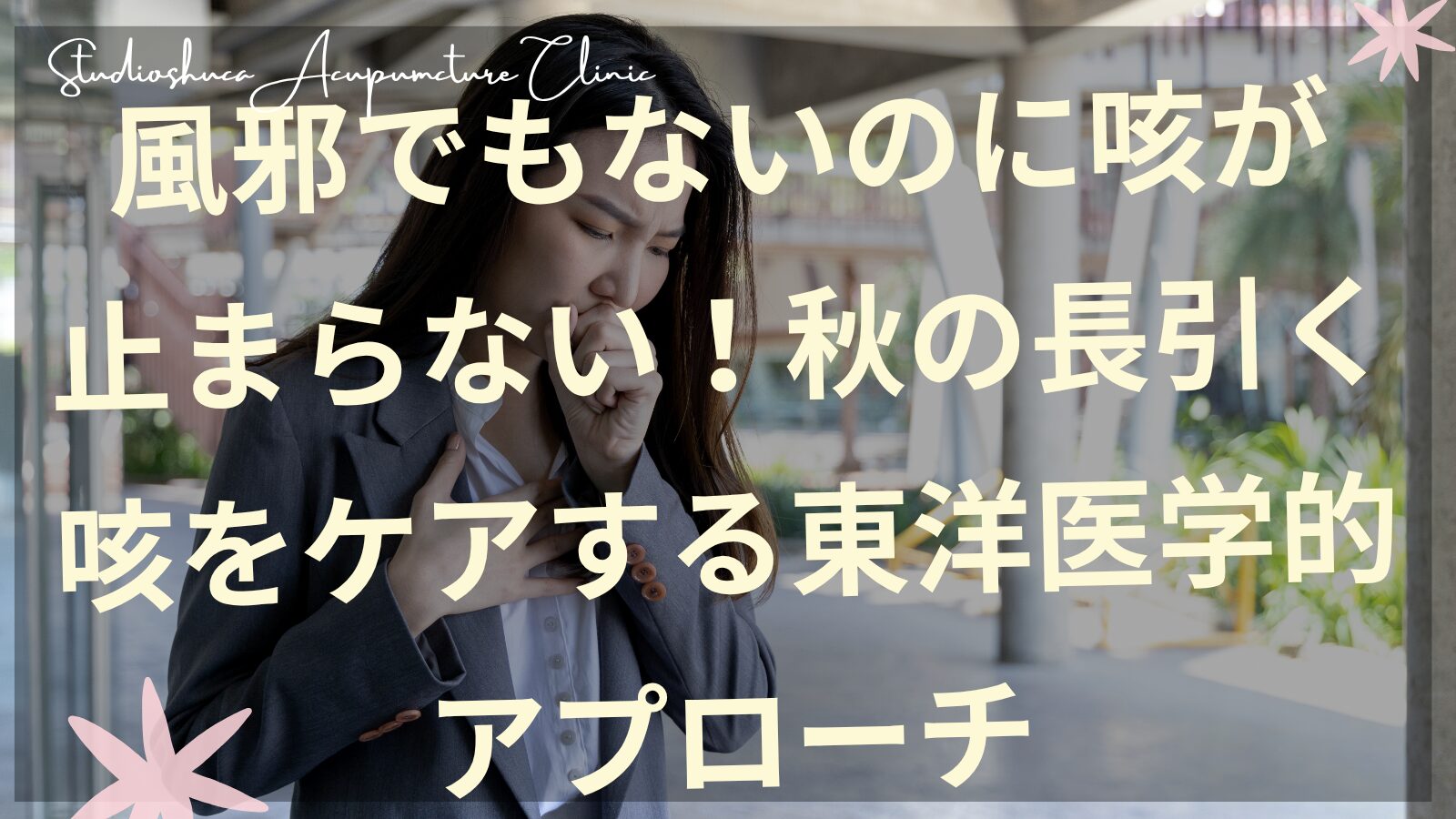
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
風邪を引いたわけでもないのに、咳が2週間以上続いている…
夜中に咳き込んで目が覚めてしまう…
そんなお悩みはありませんか?
秋になると咳が長引きやすいのは、実は偶然ではないんです。
東洋医学では、秋は「肺」の季節とされています。
乾燥した空気が呼吸器系に影響を与えやすい時期なんですよ。
このブログでは、秋の長引く咳を東洋医学の視点からケアする方法をお伝えします。
セルフケアで実践できる具体的な方法から、体質に合わせた養生法まで、あなたの呼吸器を守るヒントが見つかるはずです!
こんな方におすすめの記事です
- 風邪でもないのに咳が止まらない方
- 夜中や明け方に咳き込んで眠れない方
- 毎年秋になると咳が長引く方
- 咳止め薬に頼らず自然な方法でケアしたい方
- 東洋医学的なアプローチに興味がある方
秋の長引く咳でお悩みの方へ
風邪でもないのに咳が止まらない、夜中に咳き込んで眠れない…そんなお悩みはありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
なぜ秋は咳が長引くのか?東洋医学から見た理由
「風邪は治ったはずなのに、咳だけが残っている…」
秋になると、こんな声をよく聞きます。
実は、秋特有の気候が呼吸器に影響を与えているんです。
秋の乾燥と「燥邪」の影響
東洋医学では、秋の乾燥した空気を「燥邪(そうじゃ)」と呼びます。
燥邪は体内の潤いを奪い、特に呼吸器系に影響を与えるとされています。
西洋医学的に見ても、湿度が低下すると気管支粘膜が乾燥します。
すると、ウイルスや細菌への防御機能が低下しやすいと言われているんです。
秋の乾燥が引き起こすトラブル:
- 喉のイガイガ感
- 空咳(痰が出ない咳)
- 声がかすれる
- 鼻の乾燥
肺が最も弱る季節だから
東洋医学の五行説では、秋は「肺」の季節とされています。
肺は呼吸器系全般を司り、「潤いを好む」臓器です。
秋の乾燥した空気は、肺にとって最も過酷な環境なんですよ。
また、一般的に疲労やストレスが溜まると、呼吸器の機能が低下しやすいと言われています。
夏の疲れが残っている秋口は、特に注意が必要です。
気圧変化と寒暖差のストレス
秋は台風シーズンでもあります。
気圧の変化は自律神経に影響を与えると言われており、体調を崩しやすくなります。
朝晩の寒暖差も大きく、体温調節がうまくいかないことも。
こうした環境ストレスが、咳を長引かせる一因となっているんです。
詳しくは季節の変わり目に揺らぐ自律神経を整える!五月病予防の東洋医学的アプローチもご参考にしてください。
東洋医学から見た「秋の長引く咳」の背景
では、東洋医学では咳が長引く原因をどう捉えているのでしょうか。
ここでは3つの視点からお伝えしますね。
燥邪(そうじゃ)による肺の乾燥
燥邪は秋特有の邪気(体に悪影響を与える要因)です。
体内に侵入すると、肺や気管支の潤いを奪うと考えられています。
すると以下のような症状が現れやすくなります:
- 空咳が続く
- 痰が出にくい、または粘っこい痰が少量出る
- 喉の乾燥感
- 鼻の乾燥
- 皮膚の乾燥
「肺は潤いを好む」という東洋医学の考え方から、体内の潤いが不足すると咳が長引くとされています。
肺気の弱りと免疫力の低下
東洋医学では「肺気(はいき)」という概念があります。
肺気とは、肺の働きを支えるエネルギーのことです。
ストレスや疲労、加齢により肺気が弱まると、以下のような影響があると言われています:
- 免疫機能のサポート力が低下
- 呼吸器系のバリア機能が弱まる
- 外からの刺激(冷たい空気、乾燥)に対する防御力が落ちる
- 回復力が鈍くなる
一般的に、肺気が弱い方は風邪を引きやすく、治りにくい傾向があるとされています。
個人差はありますが、体質改善のアプローチが有効な場合があります。
気・血・水のバランスの乱れ
東洋医学では、体は「気・血・水」の3つの要素で構成されていると考えます。
このバランスが乱れると、さまざまな不調が現れるとされています。
咳が長引く場合によく見られるパターン:
①水の停滞(痰湿タイプ)
- 水分代謝が悪く、体内に余分な水分が溜まる
- 痰が絡む、喉に違和感が残る
- むくみやすい、体が重だるい
②陰虚(いんきょ)タイプ
- 体内の潤いが不足している
- 空咳、喉の乾燥
- 手足のほてり、寝汗をかきやすい
③気虚(ききょ)タイプ
- エネルギー不足で回復力が低い
- 疲れやすい、声に力がない
- 風邪を引きやすく、長引きやすい
ご自身がどのタイプに近いか、チェックしてみてくださいね。
秋の咳をケアする!肺を潤す食材選び
東洋医学には「医食同源」という考え方があります。
日々の食事が、体を整える薬にもなるという考えです。
秋の咳ケアには、「肺を潤す食材」がおすすめですよ!
白い食材が肺を守る理由
東洋医学では、五行説に基づいて食材の色と臓器を関連づけています。
秋と関連する「肺」には、白い食材が良いとされているんです。
白い食材は一般的に、体を潤す性質を持つと言われています。
また、水分を多く含み、食物繊維も豊富なものが多いですよ。
おすすめ食材トップ7とその取り入れ方
①大根
辛味成分が気の巡りをサポートし、痰を出しやすくすると言われています。
取り入れ方:朝食に大根おろしを添える、味噌汁に入れる
②白きくらげ
肺を潤す代表的な食材で、薬膳でもよく使われます。
取り入れ方:スープやデザートに、水で戻して使用
③梨
秋の果物の代表で、生でも加熱しても肺を潤すとされています。
取り入れ方:そのまま食べる、すりおろして温め、はちみつを加える
④れんこん
粘り成分が喉や気管支を保護すると言われています。
取り入れ方:すり流し汁、きんぴら、煮物
⑤はちみつ
咳を鎮める効果が期待され、古くから民間療法でも使われています。
取り入れ方:温かい飲み物に加える、大根はちみつ
⑥ゆり根
肺を潤し、咳を鎮める伝統的な食材です。
取り入れ方:茶碗蒸し、煮物、ゆり根ご飯
⑦松の実
肺を潤し、空咳をケアすると言われています。
取り入れ方:サラダにトッピング、おやつとして
具体的な献立例:
朝食:大根おろし、納豆、味噌汁(れんこん入り)
昼食:白身魚の蒸し物、ほうれん草のお浸し、白米
夕食:鶏肉と大根の煮物、白きくらげのスープ
間食:梨、松の実
さらに詳しい食材情報は秋の乾燥から肺を守る!潤いチャージの食材選びと東洋医学ケアもご覧くださいね。
避けたい食材と食べ方
咳が長引いているときは、以下のような食材や食べ方を控えましょう。
- 辛すぎるもの:唐辛子、わさび(少量の生姜は気の巡りに良いとされています)
- 冷たいもの:アイスクリーム、冷たい飲み物
- 脂っこいもの:揚げ物、ファストフード
- 甘すぎるもの:ケーキ、チョコレート(痰が増えやすいと言われています)
- 乾燥したもの:せんべい、クッキー
個人差がありますので、ご自身の体調を観察しながら調整してくださいね。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な呼吸器ケアをご提案いたします。
秋の咳・呼吸器ケアについて詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
自宅でできる!咳をケアするツボ押しセルフケア
東洋医学では、体には「経絡(けいらく)」という気の通り道があると考えられています。
経絡上にある特定のポイント「ツボ」を刺激することで、体の不調をケアできると言われているんです。
ここでは、咳に関連する経絡とツボをご紹介しますね!
肺経・大腸経とは?
東洋医学では、肺と大腸は表裏関係にあるとされています。
つまり、密接につながっていて、お互いに影響し合うということです。
肺経(はいけい):
胸から始まり、腕の内側を通って親指まで流れる経絡です。
呼吸器系の不調に関係が深いとされています。
大腸経(だいちょうけい):
人差し指から始まり、腕の外側を通って顔まで流れる経絡です。
免疫機能のサポートに関係があると言われています。
この2つの経絡のバランスを整えることが、咳のケアにつながるんですよ。
咳に効果的な4つのツボと刺激法
①尺沢(しゃくたく)【肺経】
位置:肘の内側、肘を曲げたときにできるシワの外側(親指側)の凹み
期待される体験:肺の熱を取り、咳を鎮めるとされています
刺激法:
- 反対の手の親指でツボを探す
- やや強めに押して5秒キープ
- ゆっくり離して5秒休む
- これを5回繰り返す
②孔最(こうさい)【肺経】
位置:肘と手首の中間、腕の内側(親指側)
期待される体験:急性の咳、喉の痛みをケアすると言われています
刺激法:
- 反対の手の親指で探す
- ゆっくり押し込むように刺激
- 10回繰り返す
③太淵(たいえん)【肺経】
位置:手首の内側、親指側の脈が触れる部分
期待される体験:肺気を補い、慢性的な咳をサポートすると言われています
刺激法:
- 反対の手の親指でツボを押さえる
- 小さな円を描くようにマッサージ
- 30秒間続ける
④合谷(ごうこく)【大腸経】
位置:手の甲、親指と人差し指の骨が交わる部分のやや人差し指寄り
期待される体験:免疫力のサポート、呼吸器系の不調全般に良いとされる万能ツボです
刺激法:
- 反対の手の親指と人差し指で挟むように押す
- やや強めに3秒押して3秒離す
- 10回繰り返す
注意点:
- 痛気持ちいい程度の強さで押しましょう
- 呼吸を止めず、ゆっくり呼吸しながら行います
- 食後すぐは避けましょう
- 効果には個人差があります
セルフケアの効果的なタイミング
ツボ押しは、いつでもどこでもできるのが魅力です!
でも、特に効果的なタイミングがあるんですよ。
朝起きた時:
- 体が目覚め、気の巡りが活発になる時間
- 太淵、合谷を各3分程度刺激
就寝前:
- リラックス効果も期待できる時間
- 尺沢、太淵を優しく刺激
咳が出そうな時:
- その場ですぐに合谷を押す
- 深呼吸と合わせて行うとより良いでしょう
お風呂上がり:
- 血行が良くなっているタイミング
- 全てのツボを軽く刺激
継続することが大切ですので、無理のない範囲で続けてくださいね。
呼吸法で肺機能をサポートする方法
呼吸は生命活動の基本です。
でも、意外と正しい呼吸ができていない方が多いんですよ。
東洋医学では、深い呼吸が気の巡りを整え、自律神経のバランスを取ると言われています。
腹式呼吸が肺気を養う理由
現代人は浅い胸式呼吸になりがちです。
ストレスや緊張が続くと、無意識に呼吸が浅くなってしまうんです。
腹式呼吸には、以下のような利点があると言われています:
- 肺を大きく使えるため、酸素をしっかり取り込める
- 副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できる
- 横隔膜が動くことで、内臓のマッサージ効果がある
- 気の巡りが良くなるとされている
東洋医学では、「気は呼吸によって体内を巡る」と考えられています。
深い呼吸は、肺気を養い、全身の気の流れを整えるんですよ。
1日5分でできる呼吸法の実践手順
では、具体的な腹式呼吸の方法をご紹介しますね!
基本の腹式呼吸:
- 背筋を伸ばして、楽な姿勢で座る(床でも椅子でもOK)
- 両手をお腹に当てる
- 鼻からゆっくり4秒かけて息を吸う(お腹を膨らませる)
- 2秒間、息を止める
- 口からゆっくり8秒かけて息を吐く(お腹を凹ませる)
- これを5分間繰り返す
ポイント:
- 吸う時間よりも、吐く時間を長くする
- お腹の動きを手で感じながら行う
- 力まず、リラックスして行う
- 雑念が湧いたら、呼吸に意識を戻す
慣れてきたら:
- 吸う時間を6秒、吐く時間を12秒に延ばす
- 実践時間を10分に延長する
個人差がありますので、無理のない範囲で行ってくださいね。
咳が出そうな時の緊急対処法
咳が出そうになったら、すぐに試せる呼吸法があります!
咳止め呼吸法:
- 背筋を伸ばす
- 鼻からゆっくり深く息を吸う
- 息を3秒止める
- 口をすぼめて、細く長く息を吐く(10秒以上)
- これを3回繰り返す
この呼吸法は、咳反射を抑える効果が期待されています。
会議中や人前で咳が出そうな時に、ぜひ試してみてくださいね。
また、秋のウォーキングで血の巡りケア!東洋医学が勧める適度な運動法も呼吸を深める良い習慣になりますよ。
生活環境と習慣で咳をケアする
日々の生活環境を整えることも、咳のケアには欠かせません。
ここでは、すぐに実践できる方法をお伝えしますね!
湿度管理の重要性と具体的な方法
秋は空気が乾燥する季節です。
室内の湿度を適切に保つことが、呼吸器ケアの基本なんですよ。
理想的な湿度:50~60%
この範囲に保つことで、気道粘膜の潤いが維持されやすいと言われています。
湿度管理の具体的な方法:
①加湿器の活用
- 超音波式や気化式がおすすめ
- 定期的に掃除して清潔に保つ
- 就寝時は枕元に置く
②濡れタオルを室内に干す
- 簡単で経済的な方法
- 寝室、リビングなど各部屋に
- アロマオイルを数滴垂らすのもおすすめ
③観葉植物を置く
- 自然な加湿効果が期待できる
- 空気清浄効果もあると言われています
④こまめな換気
- 朝晩5~10分ずつ窓を開ける
- 空気を入れ替えることで、ウイルスや細菌の濃度も下がります
おすすめのアロマオイル:
- ユーカリ:呼吸器系のサポートが期待できる
- ティーツリー:抗菌作用があると言われている
- ラベンダー:リラックス効果が期待できる
※アロマオイルは直接肌につけず、必ず希釈して使用してください
体を温める温活習慣
東洋医学では、冷えは万病の元と言われています。
特に、体が冷えると肺気が弱まりやすいとされているんです。
温活のポイント:
①首元を温める
- 首には太い血管が通っています
- マフラーやスカーフで保温
- 室内でもネックウォーマーを活用
②お風呂でじっくり温まる
- 38~40度のぬるめのお湯
- 15~20分ゆっくり浸かる
- 入浴剤やバスソルトを使うのもおすすめ
③温かい飲み物を摂る
- 生姜湯、葛湯、ハーブティー
- 白湯を少しずつ飲む習慣も良いでしょう
- 冷たい飲み物は避け、常温以上で
④3つの首を温める
- 首、手首、足首を冷やさない
- レッグウォーマーや手袋を活用
詳しくは朝晩の冷え込みで体調を崩さない!秋の温活養生術もご参考に。
睡眠環境の整え方
質の良い睡眠は、体の回復力を高めると言われています。
夜中に咳き込んで眠れない方は、睡眠環境を見直してみましょう。
睡眠環境チェックリスト:
①寝具の選び方
- 清潔な寝具を使う(こまめに洗濯)
- 枕の高さを調整(首に負担がかからない高さ)
- 掛け布団は軽めで保温性の高いものを
②室温・湿度
- 室温:18~22度
- 湿度:50~60%
- エアコンは乾燥しやすいので、加湿器と併用
③就寝前の習慣
- 寝る1時間前からスマホ・PCを見ない
- 温かい飲み物を飲む(カフェインは避ける)
- 軽いストレッチや呼吸法でリラックス
④寝室の環境
- 暗く静かな環境を作る
- 寝る前に換気をする
- アロマディフューザーでリラックス
個人差がありますので、ご自身に合った環境を見つけてくださいね。
スタジオシュカの鍼灸でできる呼吸器ケア
ここまで、自宅でできるセルフケアをたくさんお伝えしてきました。
でも、「一人で続けるのが難しい」「もっと本格的にケアしたい」という方もいらっしゃいますよね。
スタジオシュカでは、東洋医学の観点からあなたの体質に合わせたケアをご提案しています。
東洋医学的な体質診断とは
東洋医学では、一人ひとりの体質を丁寧に見極めることから始めます。
「四診(ししん)」という伝統的な診察法を用います。
①望診(ぼうしん):
- 顔色、表情、姿勢などを観察
- 舌の色や形を見る「舌診」も含まれます
②聞診(ぶんしん):
- 声の調子、咳の音などを聞く
- 体臭なども参考にすることがあります
③問診(もんしん):
- 症状の経過、生活習慣などを詳しくお聞きします
- 睡眠、食欲、排便なども重要な情報です
④切診(せっしん):
- 脈を診る「脈診」
- お腹を触る「腹診」
- 体の状態を触って確認します
これらを総合的に判断し、あなたの体質タイプを見極めます。
その上で、最適なケアプランをご提案するんですよ。
鍼灸施術による呼吸器系のサポート
鍼灸施術では、経絡やツボに直接アプローチします。
セルフケアよりも、より深い部分にアプローチできると言われています。
施術で使用する主な経絡:
- 肺経
- 大腸経
- 腎経(肺と深い関係があるとされています)
- 脾経(水分代謝に関係)
体質に応じたツボの選択:
陰虚タイプの方:
- 太淵、尺沢、復溜など
- 体を潤すツボを中心に
気虚タイプの方:
- 足三里、気海、関元など
- エネルギーを補うツボを
痰湿タイプの方:
- 豊隆、陰陵泉、水分など
- 水分代謝を整えるツボを
施術で期待される体験:
- リラックス効果
- 体が温まる感覚
- 呼吸がしやすくなる感じ
- 喉の違和感の軽減
※効果には個人差があり、保証するものではありません
※鍼灸は医療の代替ではありません
季節養生指導の内容
スタジオシュカでは、施術だけでなく、日常生活のアドバイスも大切にしています。
季節養生指導の内容:
①食事のアドバイス
- あなたの体質に合った食材選び
- 避けた方が良い食材
- 簡単なレシピのご紹介
②生活習慣の見直し
- 睡眠リズムの整え方
- 運動の取り入れ方
- ストレスケアの方法
③セルフケアの指導
- ご自宅でできるツボ押し
- 呼吸法の実践サポート
- お灸の使い方(希望される方)
④季節に応じたアドバイス
- 秋なら乾燥対策、温活など
- 季節の変わり目の過ごし方
- 次の季節への準備
継続的にケアを受けることで、体質が整いやすくなると言われています。
一緒に、季節に負けない体づくりをしていきましょう!
詳しくは食欲の秋を健康的に!消化力をサポートする胃腸ケアの養生法も参考になりますよ。
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた秋の呼吸器ケアプランを一緒に考えていきましょう。
まとめ:秋の咳は体質改善のサイン
ここまで読んでくださって、ありがとうございます!
秋の長引く咳について、東洋医学の視点からたくさんお伝えしてきました。
最後にポイントをまとめますね。
秋に咳が長引く理由:
- 秋の乾燥(燥邪)が肺を傷つける
- 肺気が弱まりやすい季節
- 気圧変化や寒暖差のストレス
自宅でできるケア方法:
- 肺を潤す白い食材を取り入れる
- ツボ押しセルフケアを続ける
- 腹式呼吸で肺気を養う
- 湿度管理と温活習慣
- 睡眠環境を整える
大切なのは、毎日コツコツ続けることです。
一度に全部やろうとせず、できることから始めてみてくださいね。
秋の咳は、実は体からのメッセージなんです。
「もっと体を労わってほしい」「生活習慣を見直してほしい」
そんな体の声に耳を傾けて、この機会に体質改善に取り組んでみませんか?
一人で悩まず、困ったときは専門家に相談することも大切です。
スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせたケアをご提案しています。
松戸・流山・我孫子からも通いやすい場所にありますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
あなたの呼吸が楽になり、元気な毎日を過ごせますように!
一緒に、秋を健やかに乗り切りましょう😊
免責事項:
個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。鍼灸は医療行為の代替ではありません。症状が続く場合や悪化する場合は、医療機関を受診してください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
