日照時間の減少で気分が沈みがちな方へ!心を温める11月の養生法【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-11-08 季節の養生法
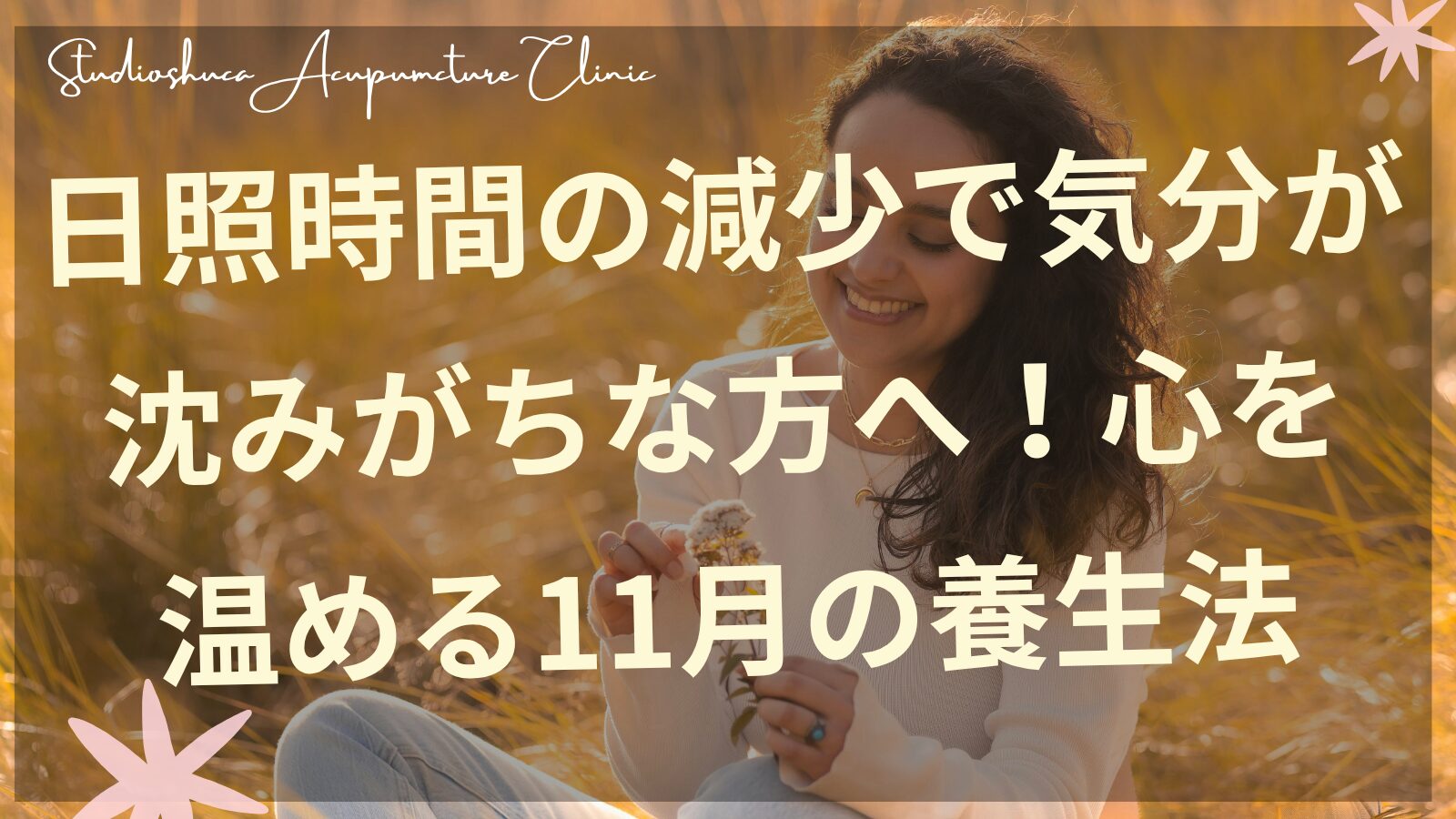
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
11月に入って日が短くなり、「なんだか気分が沈みがち」「朝起きるのがつらい」と感じていませんか?
実はこれ、あなただけではないんです。日照時間の減少は、私たちの心と体に大きな影響を与えると言われています。
この記事では、東洋医学の視点から「心を温める」11月の養生法をご紹介します。日照不足による気分の落ち込みや体のだるさは、東洋医学では「陽気不足」と捉えることができるんです。
つまり、体を温め活動的にするエネルギーが不足している状態なんですね。
この記事を読むとわかること
- 日照時間の減少がなぜ気分に影響するのか
- 東洋医学から見た秋冬の心身の変化
- 心と体を温める具体的な養生法
- 自宅でできる簡単なセルフケア方法
この記事はこんな方におすすめ
- 秋冬になると気分が沈みやすい方
- 朝の目覚めが悪く、やる気が出ない方
- 体の冷えと心の冷えを同時に感じている方
- 東洋医学的なケアに興味がある方
これから寒くなる季節も、心身ともに温かく過ごせるヒントをお伝えしますので、最後までお読みくださいね!
季節の不調でお悩みの方へ
日照時間の減少による気分の落ち込みや体の重だるさでお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から心身のバランスを整え、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
日照時間の減少が心身に与える影響とは?
11月になると、日の出は遅くなり、日の入りは早くなります。この日照時間の変化が、私たちの心と体に様々な影響を与えるんです。
「なんだか最近、気分が晴れない」「やる気が出ない」と感じているなら、それは日照不足が関係しているかもしれません。
西洋医学から見た日照不足とセロトニン
西洋医学では、日光を浴びることで脳内の「セロトニン」という神経伝達物質が生成されると言われています。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の安定や前向きな気持ちに関わっているんです。
一般的に、日照時間が短くなると、このセロトニンの生成が減少すると考えられています。すると、気分が落ち込んだり、無気力になったり、眠気が増したりすることがあるんですね。
また、日光を浴びることで体内で生成されるビタミンDも、気分の安定に関わると言われています。
日照時間の減少は体内時計の乱れにもつながり、睡眠の質が低下することもあります。朝起きるのがつらくなったり、夜なかなか眠れなくなったりするのは、こうした体内リズムの変化が影響している可能性があるんです。
実際、秋から冬にかけて気分が落ち込みやすくなる「季節性情動障害(SAD)」という状態もあり、日照時間との関連が指摘されています。
詳しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター:こころの情報サイトでも情報が提供されています。
東洋医学から見た秋冬の「陽気不足」
東洋医学では、自然界の変化と人間の体は密接に関わっていると考えられています。
秋から冬にかけて、太陽の光が減り、気温が下がっていくこの時期は、自然界の「陽気」が減少していく時期なんです。
「陽気」とは、体を温め、活動的にし、明るい気持ちをもたらすエネルギーのこと。反対に「陰気」は、体を冷やし、静かにし、内向的にするエネルギーです。
11月は、陽気が減り、陰気が増えていく移行期。この自然界の変化に合わせて、私たちの体も陽気が不足しがちになると考えられているんです。
陽気が不足すると、気分が沈みやすくなったり、やる気が出なくなったり、体が冷えやすくなったりします。まさに、日照時間の減少で感じる不調と重なりますね。
東洋医学では、この陽気不足を補い、心身のバランスを整えることが、秋冬の養生の基本だと考えられています。
東洋医学から見た11月の心身の変化
東洋医学では、心と体は一体であり、特に内臓の働きが感情や精神状態に深く関わっていると考えられています。
11月の気分の落ち込みを理解するために、東洋医学の視点から心身の変化を見ていきましょう。
「心(しん)」と気分の関係
東洋医学でいう「心(しん)」は、西洋医学の心臓だけでなく、精神活動や感情、意識、思考をつかさどる臓腑とされています。
「心は神(しん)を蔵す」と言われ、私たちの心の状態を司る大切な場所なんです。
心の陽気が充実していると、明るく前向きな気持ちでいられ、物事に意欲的に取り組めると考えられています。
反対に、心の陽気が不足すると、気分が沈んだり、不安になったり、無気力になったりしやすくなるんですね。
11月の日照時間の減少は、まさにこの「心の陽気」を不足させる要因の一つ。太陽の光は自然界の陽気の源であり、それを浴びることで私たちの体内の陽気も養われると考えられているんです。
また、心は「火」の性質を持つとされ、温かさを好みます。体が冷えると心の働きも弱まりやすいため、心と体の温めが大切なんですね。
「脾(ひ)」の働きと心のエネルギー
東洋医学でいう「脾(ひ)」は、消化吸収を司り、気血を生み出す源とされています。
食べ物から栄養を吸収し、それを「気」や「血」に変えて全身に送る、とても大切な働きをしているんです。
脾の働きが良好だと、十分な気血が生成され、心にも栄養が届き、精神的に安定すると考えられています。
反対に、脾の働きが弱まると、気血が不足し、心の栄養も足りなくなってしまいます。すると、気力が出ない、考えがまとまらない、不安になりやすい、といった状態になりやすいんですね。
11月は気温が下がり、体が冷えやすくなる時期。脾は冷えに弱く、冷えると働きが低下しやすいんです。
また、甘いものが無性に食べたくなるのも、脾が弱っているサインの一つ。脾は甘味を好みますが、過度な糖分摂取は逆に脾の負担になることもあるため、適度な甘みを温かい形で摂ることが大切です。
秋から冬への移行期に起こりやすい不調
東洋医学の五行説では、秋は「金」、冬は「水」に属します。この「金」から「水」への移行期である11月は、体のバランスが崩れやすい時期なんです。
秋から冬への移行期に起こりやすい不調として、以下のようなものがあります:
- 気分の落ち込み、憂鬱感
- 無気力、やる気の低下
- 朝起きるのがつらい
- 体の重だるさ、疲れやすさ
- 手足の冷え、体全体の冷え
- 食欲の変化(甘いものへの欲求増加)
- 眠気が増す、または不眠
- 人と会うのが億劫になる
これらは全て、陽気の不足と関連していると考えられています。
また、寒暖差で崩れる自律神経も、この時期の不調に関わっています。
大切なのは、これらの変化を「自然な体の反応」として受け止めること。そして、適切な養生で心身のバランスを整えていくことなんです。
心を温める!11月の養生法7つの習慣
それでは、具体的にどのように心と体を温めていけばいいのでしょうか?
ここからは、東洋医学の知恵を活かした、11月の養生法を7つご紹介します。どれも自宅で簡単にできるものばかりですので、できることから始めてみてくださいね!
①朝の光を浴びる習慣づくり
日照時間が短い11月だからこそ、朝の貴重な光を活用することが大切です。
起床後30分以内に、窓辺で5~10分過ごす習慣をつけてみてください。曇りの日でも、外の光は室内の何倍も明るいんです。
一般的に、朝の光は体内時計をリセットし、セロトニンの生成をサポートすると言われています。
東洋医学的には、朝は陽気が最も盛んな時間帯。この時間に外の気を取り込むことで、体内の陽気が養われると考えられているんです。
具体的な方法:
- 起きたらすぐにカーテンを開ける
- 窓辺で深呼吸を5回する
- 朝食を窓際で食べる
- ベランダや庭に出て、空を見上げる
朝の光を浴びることは、夜の睡眠の質向上にもつながると言われています。秋の夜長に質の良い睡眠をとることで、心身のバランスが整いやすくなるんですね。
②温かい飲み物で内側から温める
朝起きてすぐ、白湯またはショウガ紅茶を飲む習慣をつけましょう。
東洋医学では、温かい飲み物は「脾」を温め、気血の生成をサポートすると考えられています。脾が温まると、心にも栄養が届き、心も温まるんです。
白湯は内臓を温め、消化機能をサポートすると言われています。ショウガは体を温める性質を持ち、気の巡りを促すとされているんですね。
11月は特に、シナモンや黒糖を加えた温かい飲み物がおすすめです。シナモンは体を温め、黒糖は血を補い、心を落ち着かせる甘みがあると言われています。
おすすめの温かい飲み物:
- 白湯(朝起きてすぐ、就寝前)
- ショウガ紅茶(黒糖やハチミツを加えて)
- シナモンミルク(豆乳でもOK)
- ほうじ茶(カフェインが少なく温まる)
冷たい飲み物は内臓を冷やし、脾の働きを弱めてしまう可能性があります。11月は特に、常温以上の温かいものを選ぶようにしましょう。
③足元から全身を温める足湯習慣
毎晩寝る前に、10~15分の足湯を実践してみてください。
足には「心」や「腎」につながる経絡が通っていると考えられており、足元を温めることで心身のバランスが整うとされているんです。
特に足の裏には「湧泉(ゆうせん)」というツボがあります。土踏まずの少し上、足指を曲げたときにできるくぼみの部分です。
湧泉は、腎の気を補い、疲労回復や不安の軽減に用いられると伝統的に言われているツボなんです。足湯で温めることで、このツボの働きもサポートできると考えられています。
効果的な足湯の方法:
- お湯の温度:40~42度(熱すぎないように)
- 時間:10~15分
- 深さ:くるぶしまで浸かる
- 追加:粗塩ひとつまみ、またはラベンダーやベルガモットのアロマオイル2~3滴
足湯をしながら、ゆっくり深呼吸をすると、さらにリラックス効果が期待できます。
体を温める習慣は、女性の体全体のバランスにも良い影響があると言われているんですね。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な11月の養生法をご提案いたします。
日照不足による心身の不調について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
④心を温めるツボ押しセルフケア
心を落ち着かせ、温めるツボを2つご紹介します。気持ちが沈んだとき、不安を感じたときに試してみてください。
膻中(だんちゅう)
- 位置:胸の中心、左右の乳頭を結んだ線の真ん中
- 効果:心を落ち着かせ、胸のつかえを取ると言われるツボ
- 押し方:深呼吸しながら、優しく円を描くように5回押す
膻中は東洋医学で「気会」と呼ばれ、全身の気が集まる場所とされています。ここを刺激することで、滞った気が巡り始めると考えられているんです。
神門(しんもん)
- 位置:手首の内側、小指側の少しくぼんだところ
- 効果:不安や緊張を和らげ、心を穏やかにすると伝統的に用いられるツボ
- 押し方:親指で優しく10秒×3回押す
神門は心経に属し、精神の安定をサポートすると考えられています。仕事中や移動中にも簡単に押せるので、気持ちが落ち着かないときにぜひ試してみてください。
ツボ押しをするときは、強く押しすぎず、「痛気持ちいい」程度の力加減で行いましょう。深呼吸と組み合わせると、さらに効果的だと言われています。
⑤色と香りで心を温める環境づくり
東洋医学の五行説では、暖色系(オレンジ、黄色、赤)が「火」のエネルギーを持ち、心を活性化すると考えられています。
部屋の環境を少し変えるだけで、心の温まり方が変わってくるんです。
色で心を温める:
- オレンジや黄色のクッションやブランケットを置く
- 暖色系のライトを使う(間接照明がおすすめ)
- 赤やピンクの花を飾る
香りで心を温める:
- 柑橘系の香り(オレンジ、ゆず、レモン):気の巡りを促すと言われる
- シナモンの香り:体を温める性質があるとされる
- キャンドルの炎:炎を見ることも、心の「火」を養う方法の一つ
視覚や嗅覚からの刺激は、心の状態に影響を与えると言われています。特に、日照時間が短い11月は、こうした環境づくりが心のサポートになるんですね。
⑥軽い運動で気の巡りを促す
東洋医学では「動けば陽気が生まれる」と考えられています。
適度な運動は体内のエネルギーを活性化させ、気血の巡りを促すと言われているんです。
ただし、激しい運動は気を消耗させるため、心地よい程度の運動がおすすめです。
おすすめの運動:
- ウォーキング(20~30分、日中に)
- ストレッチ(朝起きたとき、就寝前)
- ヨガやラジオ体操
- 階段の上り下り
特に日中、外で体を動かすことで陽気を取り込めます。太陽の光を浴びながらの運動は、心身両方に良い影響があると考えられているんですね。
運動後は必ず体を冷やさないよう、温かい飲み物を摂りましょう。汗をかいたらすぐに着替えることも大切です。
呼吸法と組み合わせた運動も、心身のバランスを整えるのに効果的だと言われています。
⑦食事で心と脾を養う
東洋医学では、食べ物の性質(温・涼・寒・熱・平)を考えながら、体を整えていきます。
11月は特に、体を温め、気血を補う食材を選ぶことが大切なんです。
心と脾を養う食材:
- さつまいも:脾を養い、気を補う。甘みが心を落ち着かせるとされる
- かぼちゃ:体を温め、気を補う。ビタミン豊富で免疫サポートにも
- 栗:腎を補い、足腰の冷えを改善すると言われる
- 黒糖:血を補い、体を温める性質があるとされる
- 鶏肉:気を補い、体を温める
- 卵:血を補い、心の栄養に
- 豆腐:脾を養い、消化しやすい
温める調味料:
- ショウガ:体を温め、気の巡りを促す
- ネギ:陽気を補い、風邪予防にも
- シナモン:体を温め、血の巡りを促す
避けるべき食材:
- 冷たい飲み物、アイス
- 生野菜(適度なら良いが、食べ過ぎは体を冷やす)
- 刺激物(辛すぎるもの、カフェインの摂りすぎ)
食事は温かい形で摂ることが基本です。同じ食材でも、温かいスープにするか、冷たいサラダにするかで、体への影響が変わってくるんですね。
朝食には特に、温かいスープやお粥がおすすめ。脾を優しく温め、一日の気血生成をサポートしてくれると考えられています。
鍼灸でできる心身のバランスケア
ここまでセルフケアをご紹介してきましたが、「一人で続けるのが難しい」「もっと本格的にケアしたい」という方もいらっしゃると思います。
そんなときは、東洋医学の鍼灸によるサポートも選択肢の一つです。
東洋医学の鍼灸によるアプローチ
鍼灸では、体のツボや経絡を刺激することで、気血の巡りをサポートし、心身のバランスを整えることが期待されています。
日照不足による気分の落ち込みや体のだるさは、東洋医学的には陽気不足や気血の滞りと捉えることができます。
鍼灸施術では、一人ひとりの体質や症状に合わせて、適切なツボを選んでアプローチします。
例えば:
- 心の陽気を補うツボ
- 脾の働きをサポートするツボ
- 気血の巡りを促すツボ
- 体を温めるツボ
これらを組み合わせることで、心身のバランスを整えるお手伝いをさせていただいています。
ただし、効果には個人差があり、鍼灸は医療行為の代替ではありません。気になる症状がある場合は、まず医療機関にご相談ください。
自律神経のバランスをサポートする施術
一般的に、鍼灸施術はリラックス効果があり、副交感神経を優位にすることで自律神経のバランスをサポートすると言われています。
東洋医学では、自律神経の乱れは「気の巡りの滞り」と捉えることができます。
日照時間の減少による体内リズムの乱れは、自律神経のバランスにも影響を与えやすいんです。季節の変わり目に揺らぐ自律神経を整えることは、心身の健康にとって大切なんですね。
鍼灸施術では、リラックスした状態で施術を受けることで、心も体も緩み、気の巡りが促されると考えられています。
多くの方が施術中に眠ってしまったり、施術後に「体が軽くなった」「気持ちがすっきりした」と感じられることがあります。
ただし、個人の体質により体験には個人差があります。
継続的なケアの大切さ
東洋医学では、体質改善には時間がかかると考えられており、継続的なケアが推奨されます。
1回の施術で劇的に変わるというよりも、定期的にケアを続けることで、徐々に体が整っていくイメージなんです。
季節ごとに体の状態は変化するため、その時期に合わせた養生が大切です。11月は陽気を補う養生、冬は腎を養う養生、春は気の巡りを促す養生…というように、季節に応じたアプローチが効果的だと考えられています。
一人で続けるのが難しい場合は、専門家のサポートを受けることで、自分の体質に合った方法を見つけやすくなります。
スタジオシュカでは、一人ひとりのお悩みや体質に合わせた季節養生のアドバイスもさせていただいています。
まとめ:11月を心温かく過ごすために
ここまで、日照時間の減少による気分の落ち込みと、心を温める11月の養生法についてお伝えしてきました。
大切なポイントをもう一度振り返りましょう:
- 日照時間の減少は、心身に影響を与える自然な変化
- 東洋医学では「陽気不足」と捉え、温める養生が基本
- 朝の光、温かい飲み物、足湯など、できることから始める
- ツボ押し、色と香り、運動、食事で心と体を温める
- 継続することで、徐々に体が整っていく
11月の気分の沈みは、決してあなたが弱いからではありません。自然界の変化に体が反応しているだけなんです。
だからこそ、その変化を受け入れながら、優しく自分をケアしていくことが大切なんですね。
完璧にすべてをやろうとしなくて大丈夫です。今日は足湯だけ、明日は温かい飲み物を意識する、というように、できることから少しずつ始めてみてください。
小さな習慣の積み重ねが、やがて心と体を温め、11月という季節を心地よく過ごす力になっていきます。
そして、もし一人で続けるのが難しいと感じたら、どうぞ遠慮なくプロのサポートを受けてください。
あなたの心と体が、この11月も、そしてこれから来る冬も、温かく穏やかでありますように。
いつでもお気軽にご相談くださいね!
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた11月の養生プランを一緒に考えていきましょう。
※個人の体質により体験には個人差があります。
※施術効果を保証するものではありません。
※鍼灸は医療行為の代替ではありません。気になる症状がある場合は、まず医療機関にご相談ください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
