食欲の秋を健康的に!消化力をサポートする胃腸ケアの養生法【千葉県柏市の女性専門鍼灸院】
2025-09-29 季節の養生法
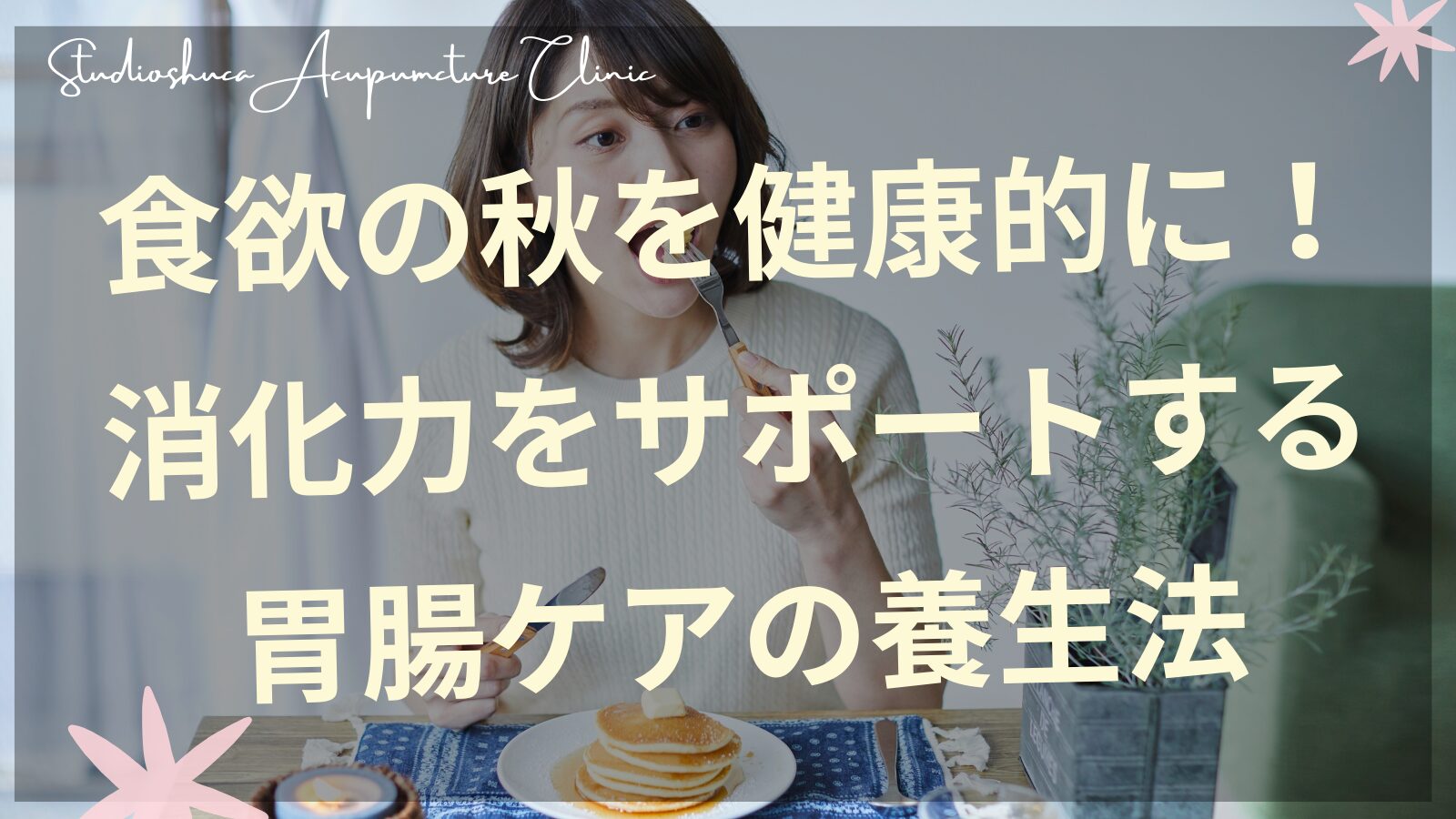
秋の胃腸不調、あなたも心当たりはありませんか?
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
「食欲の秋」という言葉の通り、秋になると美味しいものがたくさん出回り、ついつい食べ過ぎてしまいがちですよね!
でも食べた後の胃もたれや消化不良に悩まされている方も多いのではないでしょうか?
秋は本来、体が冬に向けて栄養を蓄える大切な時期なんです。
この時期に胃腸の調子を整えることで、より健康的に秋の味覚を楽しむことができますよ✨
この記事はこんな方におすすめです:
- 秋になると食べ過ぎてしまい胃腸の調子が気になる方
- 消化力の低下を感じている30代40代50代の女性
- 東洋医学の養生法で体調を整えたい方
この記事を読むと、東洋医学の視点から「脾胃(ひい)」の働きをサポートし、食欲の秋を健康的に楽しむための具体的な方法がわかります。
消化力をサポートする食事法、胃腸をケアするツボ押し、生活習慣の整え方まで、今日から実践できる内容をお伝えしていきますね!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
食欲の秋に起こりがちな胃腸トラブル
秋になると、こんな症状に心当たりはありませんか?
- 食後の胃もたれや膨満感が気になる
- 美味しいものを見ると我慢できずについ食べ過ぎてしまう
- 便秘や下痢を繰り返しやすくなる
- 食べた後に眠くなったりだるくなったりする
これらは決してあなただけの悩みではありません!
実は、気温や湿度の変化が自律神経に影響を与え、胃腸の働きにも変化が起こりやすい時期なんです。
一般的に、自律神経のバランスが崩れると消化機能にも影響が出ると言われています。
特に副交感神経が優位になりすぎると、胃腸の働きが過度に活発になり、食欲が増進する傾向があるとされているんですよ。
年齢とともに変わる消化力の特徴
30代、40代、50代と年齢を重ねるにつれて、消化力にも変化が現れます。
30代の特徴:
ストレスや不規則な生活で胃腸の調子が不安定になりがちです。
仕事や育児で忙しく、早食いや外食が多くなることも影響していると考えられます。
40代の特徴:
基礎代謝の低下に伴い、消化酵素の分泌量も減少傾向にあると言われています。
同じ量を食べても以前より胃もたれを感じやすくなる方が多いんです。
50代の特徴:
ホルモンバランスの変化により、自律神経も影響を受けやすい時期です。
胃腸の働きが不規則になり、食後の不快感を感じる方が増えるとされています。
どの年代でも共通しているのは、体の変化に合わせたケアの重要性です!
東洋医学から見た「脾胃」の働きと秋の関係
脾胃とは?消化吸収をサポートする重要な機能
東洋医学では、消化機能を「脾胃(ひい)」という概念で捉えています。
これは西洋医学でいう脾臓や胃とは少し異なり、消化・吸収・運搬といった一連の働き全体を指しているんです。
脾胃の主な働き:
- 食べ物を消化し、栄養を吸収する「運化作用」
- 水分代謝を調整する「水湿運化」
- 栄養を全身に送り届ける「昇清作用」
東洋医学的には、脾胃が元気だと全身に栄養が行き渡り、体調が安定すると考えられています。
逆に脾胃の働きが弱くなると、消化不良や疲労感、むくみなどが起こりやすくなるとされているんです。
個人差はありますが、脾胃の状態は舌の色や形、お腹の張り具合などから推測することができると言われています。
秋の気候が脾胃に与える影響
東洋医学の五行説では、秋は「肺」の季節とされていますが、脾胃とも密接な関係があります。
秋の気候の特徴:
- 朝晩の気温差が大きくなる
- 空気が乾燥してくる(燥邪の影響)
- 湿度の変化が激しい
これらの変化が脾胃にどう影響するかというと、一般的に以下のようなことが起こりやすいと言われています:
気温差により自律神経が不安定になり、消化機能にも影響が出る可能性があります。
また、乾燥により体内の水分バランスが変化し、消化液の分泌にも変化が起こることがあるとされているんです。
自律神経を整えて、妊娠しやすい体へ!女性のための不妊ケアでも詳しくお話ししていますが、自律神経の安定は消化機能の安定にもつながると考えられています。
消化力をサポートする秋の食事養生法
脾胃をいたわる食べ方の基本
東洋医学では、「どう食べるか」がとても重要視されています。
脾胃をいたわる食べ方の基本をご紹介しますね!
よく噛むことの大切さ:
一口30回以上噛むことを心がけましょう。
噛むことで唾液の分泌が促進され、消化をサポートすると言われています。
また、満腹中枢が刺激されるため、食べ過ぎの予防にも効果が期待できます。
温かいものを摂る習慣:
冷たい食べ物や飲み物は、脾胃の働きを弱めるとされています。
特に朝一番には温かいお茶や白湯を飲むことで、胃腸を温めて一日の消化活動をサポートできると考えられているんです。
腹八分目を心がける:
「もう少し食べられるかな」というところで箸を置くのがポイントです。
満腹まで食べてしまうと、脾胃に負担をかけてしまう可能性があります。
消化をサポートする秋の食材選び
秋に旬を迎える食材の中には、消化をサポートしてくれるものがたくさんあります✨
おすすめの食材:
- 山芋:消化酵素が豊富で、脾胃の働きをサポートするとされています
- 大根:消化を助ける酵素が含まれ、胃もたれの緩和に役立つと言われています
- 生姜:体を温め、消化機能を高める効果が期待できます
- かぼちゃ:甘味があり脾胃を補養し、消化しやすい食材です
- さつまいも:食物繊維が豊富で、腸内環境を整えるサポートをしてくれます
これらの食材を使った具体的なレシピとして、山芋とろろご飯や大根おろしを使った料理、生姜を効かせた温かいスープなどがおすすめです。
冷え性改善で体の中から温活!妊活を成功させるためのヒントでは、他にも体を温めてくれる食材について詳しくご紹介していますので、参考にしてみてくださいね。
摂取タイミングも重要:
朝食には消化の良いお粥や温かいスープを。
昼食にはしっかりとした食事を。
夕食は軽めにして、就寝3時間前には済ませることが理想的とされています。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
胃腸ケアに効果的なツボ押しセルフケア
東洋医学では、特定のツボを刺激することで胃腸の働きをサポートできると考えられています。
ここでは、ご自宅で簡単にできるツボ押しの方法をご紹介しますね!
足三里(あしさんり)- 胃腸の働きをサポートするツボ
足三里は「胃腸のツボ」として最も有名なツボの一つです。
ツボの場所:
膝のお皿の下から指4本分下がったところで、すねの骨の外側にあります。
押すとちょっと痛気持ちいい感じがする場所です。
押し方:
- 親指で3~5秒間ゆっくり押す
- ゆっくり力を抜く
- これを5~10回繰り返す
足三里を刺激することで、胃腸の働きをサポートし、消化機能の安定に役立つと伝統的に言われています。
個人差はありますが、食前30分前や食後1時間後に行うのが効果的とされているんです。
中脘(ちゅうかん)- 消化機能をケアするツボ
中脘は胃の調子を整えるのに重要なツボです。
ツボの場所:
おへそから指4本分上がったところ、みぞおちとおへその中間点にあります。
押し方:
- 人差し指、中指、薬指の3本を使って優しく押す
- 時計回りに小さく円を描くようにマッサージ
- 2~3分間続ける
中脘への刺激は、胃もたれや膨満感の緩和に役立つとされています。
ただし、食後すぐは避けて、空腹時や食前に行うのがおすすめです。
ツボ押しと呼吸法の組み合わせ:
ツボを押しながら、ゆっくりとした腹式呼吸を行うとより効果的と言われています。
鼻から4秒で息を吸い、8秒かけて口から息を吐く。
このリズムで行うことで、副交感神経が優位になり、消化機能のサポートにつながるとされているんです。
冷えやむくみ解消に!自宅で簡単にできるツボ押し&鍼灸で血行促進では、他にも様々なセルフケアのツボをご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。
スタジオシュカ鍼灸治療院での胃腸ケアアプローチ
個人の体質に合わせた施術方法
スタジオシュカでは、お一人お一人の体質や症状に合わせたオーダーメイドの施術をご提供しています。
体質診断のポイント:
- 舌の色や形、苔の状態から脾胃の状態を確認
- お腹の張りや硬さを触診でチェック
- 食事の好み、消化の状態、排便の状況などを詳しくお伺い
東洋医学的な体質診断により、その方に最適なツボを選択し、適切な刺激量で施術を行います。
例えば、冷え性の方には体を温める効果が期待されるツボを、ストレス性の胃腸不調の方には自律神経を整えるとされるツボを選択するなど、個別にアプローチしていきます。
鍼灸で期待できる胃腸への働きかけ
鍼灸施術では、以下のような働きかけが期待されています:
自律神経の調整:
鍼灸により副交感神経が優位になることで、消化機能のサポートが期待できると言われています。
血流の促進:
胃腸周辺の血流が改善されることで、消化機能の安定化に役立つとされています。
内臓の働きの調整:
特定のツボへの刺激により、胃腸の蠕動運動が調整され、消化吸収のサポートにつながると考えられているんです。
ただし、効果には個人差があり、施術効果を保証するものではありません。
また、鍼灸は医療行為の代替ではないことをご理解ください。
施術の頻度について:
一般的に、週1~2回のペースで継続することで、体質の安定化がサポートされると言われています。
症状の程度や体質により個人差がありますので、施術計画については個別にご相談させていただいています。
厚生労働省「食事バランスガイド」でも、バランスの取れた食事の重要性が示されており、鍼灸によるケアと合わせて生活習慣の見直しも大切だと考えています。
また、日本東洋医学会では、東洋医学の正しい知識と活用法について情報を提供しており、私たちもこれらの指針に基づいた施術を心がけています。
まとめ:食欲の秋を健康的に楽しむために
食欲の秋を健康的に楽しむためのポイントをまとめますね✨
今日からできること:
- よく噛んで、温かいものを腹八分目で食べる
- 山芋、大根、生姜などの消化をサポートする食材を取り入れる
- 足三里や中脘のツボ押しを日課にする
- 規則正しい食事時間を心がける
秋は体が冬に向けて準備をする大切な季節です。
この時期に胃腸を整えることで、寒い季節も元気に過ごせる基盤づくりができますよ!
体質改善は一朝一夕にはいきません。
でも、毎日の小さな積み重ねが必ず体の変化につながります。
もし一人で続けるのが不安でしたら、私たちがサポートいたします!
東洋医学の知識を活かして、あなたの体質に合った最適なケア方法を一緒に見つけていきましょう。
美味しい秋を、体調を崩すことなく思いっきり楽しんでくださいね🍂
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
免責事項:
個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
