寒暖差で崩れる自律神経をサポート!季節の変わり目を乗り切る体づくり【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-09-20 季節の養生法
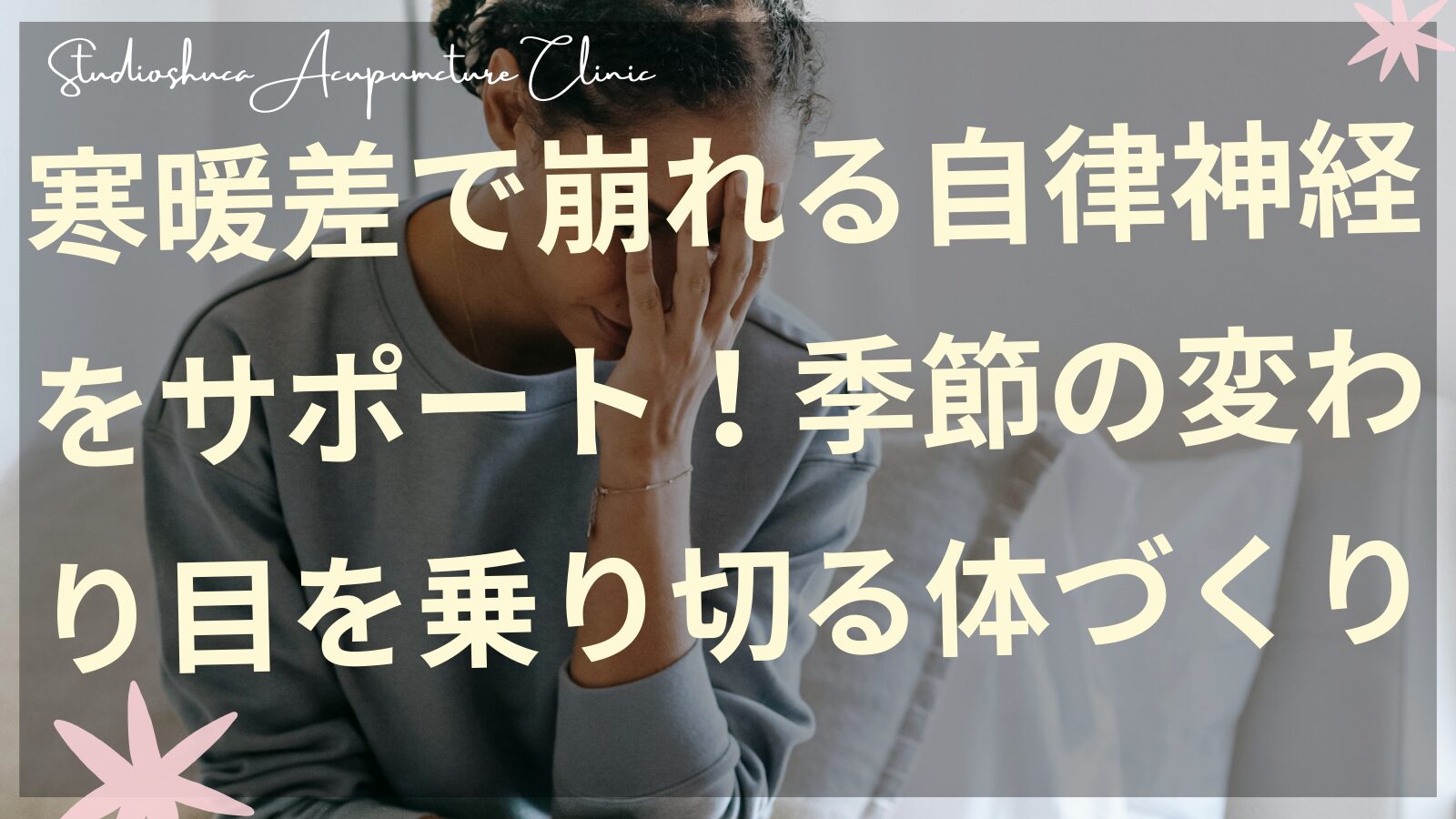
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
9月も半ばを過ぎ、朝晩の涼しさと日中の暑さの差に体がついていかない…そんなお悩みはありませんか?
「なんだかだるい」「疲れが取れない」「夜眠れない」など、季節の変わり目には様々な不調を感じやすくなります。
実は、こうした症状は東洋医学では「気の巡り」が滞ることで起こると考えられているんです!
この記事では、寒暖差による自律神経の乱れを東洋医学の視点からサポートする方法をお伝えします。
この記事を読むとわかること:
- 寒暖差が体に与える影響と東洋医学的な解釈
- 自宅でできる「気の巡り」を整えるセルフケア法
- 季節の変わり目を元気に乗り切る生活習慣のコツ
こんな方におすすめ:
季節の変わり目に体調を崩しやすい30代・40代・50代の女性で、自然な方法で体調管理をしたい方
最後までお読みいただくと、今日からすぐに実践できるセルフケア法がわかり、季節に負けない体づくりを始められますよ♪
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
季節の変わり目に起こりやすい体の変化とは
9月から10月にかけての季節の変わり目には、多くの方が様々な不調を感じられます。
「毎年この時期になると調子が悪くなる」というお声をよく聞くのですが、これには理由があるんです!
寒暖差が体に与える影響について
一般的に、気温差が7度以上になると体に負担がかかると言われています。
私たちの体は、外気温の変化に合わせて体温を調節していますが、この調節機能を担っているのが自律神経なんです。
朝は15度、昼間は25度といった寒暖差があると:
- 体温調節のために自律神経がフル稼働
- 交感神経と副交感神経の切り替えが忙しくなる
- 結果として疲労が蓄積しやすくなる
こうした状態が続くことで、だるさや頭痛、眠りの質の低下といった症状が現れやすくなると考えられています。
自律神経の働きと季節の関係性
自律神経は、私たちが意識しなくても心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を調節してくれる大切な神経です。
東洋医学では、この自律神経の働きと深く関わっているのが「気」の流れだと考えられています。
季節の変わり目には:
- 気圧の変化
- 湿度の変化
- 日照時間の変化
これらの影響で、気の巡りが滞りやすくなると言われているんです。
特に秋は、東洋医学では「肺」の季節とされ、呼吸器系や皮膚の乾燥に注意が必要な時期とされています。
東洋医学から見た寒暖差疲労の背景
東洋医学では、体の不調を「気・血・水」のバランスの乱れから捉えます。
寒暖差による疲労も、この観点から理解することができるんです♪
「気・血・水」の観点から見た症状分析
「気」の滞り:
- だるさや疲労感
- やる気の低下
- イライラしやすい
「血」の巡りの悪化:
- 肩こりや首こり
- 頭痛
- 手足の冷え
「水」の代謝不良:
- むくみ
- 胃腸の不調
- めまい
これらの症状は、東洋医学的には気・血・水の巡りを整えることでサポートが期待されると考えられています。
※個人差があります。効果を保証するものではありません。
季節の変わり目と「腎」の関係性
東洋医学では、秋から冬にかけて「腎」の働きが重要になると言われています。
「腎」は現代医学の腎臓とは少し異なり、生命エネルギーの貯蔵庫のような役割を果たすとされています。
季節の変わり目に不調を感じやすい方は、この「腎」の働きをサポートすることが大切だと考えられているんです。
腎の働きが低下すると:
- 疲れやすくなる
- 冷えを感じやすくなる
- 夜の眠りが浅くなる
これらの症状に心当たりがある方は、腎をサポートする養生法を試してみることをおすすめします。
体質別の現れ方の違い
東洋医学では、一人ひとりの体質に合わせたアプローチが大切だと考えられています。
陽虚体質の方:
- 冷えを強く感じやすい
- 疲労感が抜けにくい
- 温かいものを好む傾向
陰虚体質の方:
- のぼせや火照りを感じやすい
- 夜眠りにくい
- 口や皮膚の乾燥を感じやすい
気虚体質の方:
- だるさや疲労感が強い
- 食後に眠くなりやすい
- 風邪をひきやすい
ご自身の体質を理解することで、より効果的なセルフケアを選択できるようになります。
※体質の判断には個人差があります。詳しくは専門家にご相談ください。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
気の巡りを整える生活習慣とセルフケア
ここからは、実際にご自宅でできる「気の巡り」を整える方法をご紹介します!
東洋医学のエッセンスを取り入れながら、無理なく続けられる方法を選びました♪
朝の「気を巡らせる」5分間ルーティン
朝の過ごし方で、一日の気の巡りが決まると言われています。
忙しい朝でもできる、5分間のルーティンをご紹介しますね!
1. 深呼吸で気を整える(2分)
- 窓を開けて新鮮な空気を取り入れる
- 鼻から4秒かけて息を吸う
- 4秒間息を止める
- 口から8秒かけてゆっくり息を吐く
- これを5回繰り返す
2. 軽いストレッチで体を目覚めさせる(2分)
- 首をゆっくり左右に回す
- 肩甲骨を寄せるように腕を後ろに引く
- 腰を左右にひねる
3. 気を巡らせるツボ押し(1分)
- 頭頂部の「百会」を軽く押す
- 手首の「神門」を優しくマッサージ
このルーティンは、気の巡りをサポートすることが期待されています。
※効果には個人差があります。無理をせず、体調に合わせて行ってください。
寒暖差に負けない食材選びのコツ
食べ物にも「温性」「涼性」「平性」があると東洋医学では考えられています。
季節の変わり目には、体を温めすぎず冷やしすぎない「平性」の食材を中心に、体調に合わせて調整することが大切です!
おすすめの「平性」食材:
- 白米、玄米
- じゃがいも、さつまいも
- キャベツ、ニンジン
- りんご、ぶどう
体を温める「温性」食材(冷えを感じる時に):
- 生姜、ニンニク
- シナモン、八角
- 鶏肉、エビ
- もち米、栗
体を冷ます「涼性」食材(のぼせや火照りを感じる時に):
- きゅうり、トマト
- レタス、セロリ
- 豆腐、豆乳
- 梨、すいか
朝の体調や天候に合わせて、食材を選んでみてくださいね♪
※食材の効果には個人差があります。アレルギーや持病がある方は医師にご相談ください。
自律神経をサポートするツボ押し法
東洋医学では、特定のツボを刺激することで気の巡りをサポートできると考えられています。
自律神経の乱れをサポートするとされるツボをご紹介しますね!
百会(ひゃくえ)- 頭のてっぺん
- 両耳を結んだ線と鼻筋の延長線が交わる点
- 中指で優しく3秒間押して離すを5回
- 気持ちの安定をサポートするとされています
神門(しんもん)- 手首のツボ
- 手のひら側の手首、小指側のくぼみ
- 親指で円を描くように30秒マッサージ
- 心を落ち着かせるサポートが期待されています
三陰交(さんいんこう)- 足首のツボ
- 内くるぶしから指4本分上、骨の後ろ側
- 親指でゆっくり3秒押して離すを5回
- 女性特有の不調をサポートするとされています
ツボ押しは、お風呂上がりや就寝前に行うのがおすすめです。
※強く押しすぎないよう注意してください。妊娠中の方は専門家にご相談ください。
夜の「気を鎮める」入浴法と過ごし方
夜は、昼間に巡らせた気を鎮めて、質の良い睡眠につなげることが大切です。
東洋医学的な夜の過ごし方をご紹介しますね♪
理想的な入浴法:
- お湯の温度は38-40度(熱すぎないように)
- 入浴時間は15-20分程度
- ラベンダーやカモミールの入浴剤もおすすめ
- 入浴後は体を冷やさないよう注意
就寝前の過ごし方:
- スマホやテレビは就寝1時間前まで
- 読書や軽いストレッチで心を落ち着ける
- 部屋の照明を暗めに調整
- 温かい白湯やカモミールティーもおすすめ
良質な睡眠は、自律神経を整える上でとても重要だと言われています。
※入浴法や睡眠の質改善効果には個人差があります。
東洋医学の鍼灸で期待されるサポート
セルフケアだけでは難しい場合、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。
東洋医学の鍼灸では、どのようなサポートが期待されるのでしょうか?
鍼灸施術で期待される体験
鍼灸施術を受けた方からは、このような声をいただいています:
- 「施術後、体が軽くなった感じがする」
- 「深いリラクゼーションを感じられた」
- 「血行が良くなった感覚がある」
- 「夜ぐっすり眠れるようになった」
鍼灸は、体のツボに細い鍼やお灸を用いて刺激を与え、気血の巡りをサポートする施術です。
一般的に、鍼灸施術では以下のような効果が期待されると言われています:
- 筋肉の緊張緩和
- 血行促進
- リラクゼーション効果
- 自然治癒力のサポート
※効果には個人差があります。鍼灸は医療の代替ではありません。
季節養生における鍼灸の役割
東洋医学では、季節ごとに体調管理のポイントが異なると考えられています。
秋の季節養生では、特に以下の点を重視します:
- 「肺」の働きをサポートする
- 乾燥から体を守る
- 冬に向けて「腎」の力を蓄える
鍼灸施術では、季節の特性を考慮しながら、一人ひとりの体質に合わせたアプローチを行います。
例えば、秋の不調でお悩みの方には:
- 肺経のツボへのアプローチ
- 乾燥対策をサポートするツボ選択
- 自律神経のバランスを整えるツボ刺激
このように、季節と体質の両方を考慮した施術を行うことが、東洋医学の特徴です。
※施術内容や効果には個人差があります。
スタジオシュカでの季節養生アプローチ
スタジオシュカ鍼灸治療院では、東洋医学の理論に基づいた季節養生をサポートしています。
当院の特徴をご紹介させていただきますね♪
体質診断からスタート:
- 東洋医学的な体質診断を行います
- 生活習慣や体調の変化を詳しくお聞きします
- 一人ひとりに最適なアプローチを提案します
季節に合わせた施術:
- 秋なら「肺」をサポートするツボを中心に
- 乾燥対策や免疫力サポートも重視
- 冬に向けた体づくりもお手伝い
セルフケア指導も充実:
- ご自宅でできるツボ押し法をお教えします
- 季節に合った食材選びのアドバイス
- 生活習慣改善のサポート
私たちは、鍼灸施術だけでなく、皆様が日常生活の中で健康を維持できるようサポートすることを大切にしています。
柏市で季節養生に興味をお持ちの方は、お気軽にご相談くださいね!
※施術効果を保証するものではありません。個人差があります。
まとめ:季節に負けない体づくりを始めよう
寒暖差で自律神経が乱れやすい季節の変わり目も、東洋医学の知恵を活用することで上手に乗り切ることができます!
今回ご紹介した内容をまとめると:
セルフケアのポイント:
- 朝の5分ルーティンで気の巡りをサポート
- 体質に合った食材選びで内側から体をケア
- 自律神経をサポートするツボ押しを習慣に
- 夜は気を鎮める入浴法と過ごし方を実践
大切なのは、完璧を目指さず、できることから少しずつ始めることです♪
体調が良い日もあれば、そうでない日もあるのが自然なこと。
ご自身の体の声に耳を傾けながら、無理のないペースで続けてみてくださいね。
もし「一人では続けるのが難しい」「自分に合った方法を知りたい」と感じられたら、専門家のサポートを受けることも一つの選択肢です。
季節の変わり目も、笑顔で過ごせる毎日を応援しています!
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
免責事項:
- 個人の体質により体験には個人差があります
- 施術効果を保証するものではありません
- 医療行為の代替ではありません
- 気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
