温かいものを食べても冷えが取れない原因と対策!体質別の温活アプローチ【柏市の季節養生の鍼灸院】
2025-10-18 季節の養生法
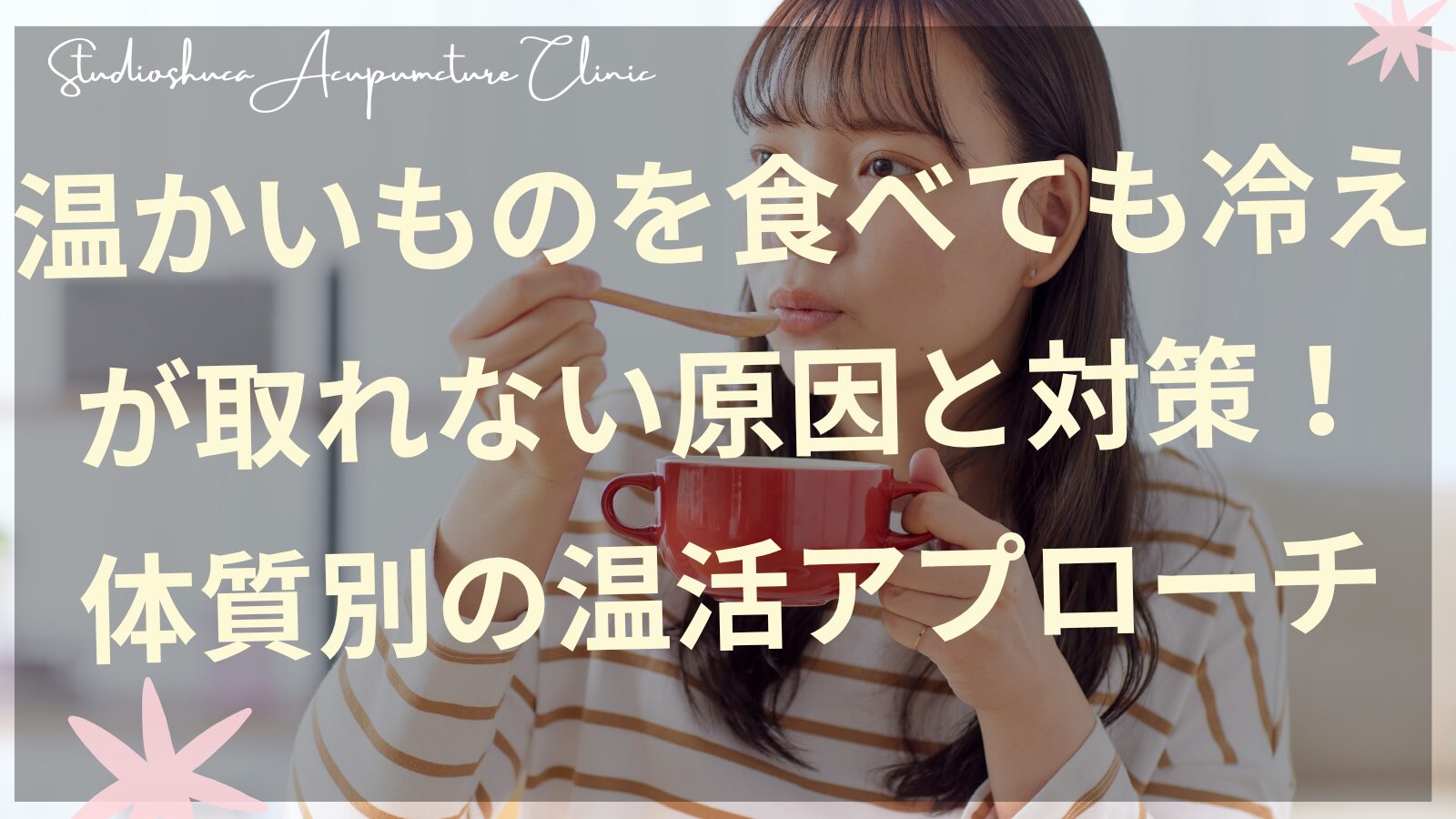
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
「温かいスープを飲んでいるのに、手足が冷たいまま…」
「お風呂で温まっても、すぐに冷えてしまう…」
そんなお悩み、ありませんか?
実は、温かいものを食べても冷えが取れない原因は、体質に合わない温活をしている可能性があるんです。
東洋医学では、冷えのタイプを4つに分類し、それぞれに適したアプローチがあります。
このブログでは、あなたの体質タイプを見極め、内側から温まる食べ方のコツをお伝えしていきますね!
この記事を読むとわかること
- 温かいものを食べても冷える理由
- 4つの冷えタイプと体質チェック
- 体質別のおすすめ食材と食べ方
- 内側から温まる飲み物・スープ術
- 鍼灸でサポートできる体質改善
こんな方におすすめの記事です
- 温活を頑張っているのに効果を感じられない方
- 手足の冷えがなかなか改善しない方
- 自分に合った冷え対策を知りたい方
- 30代・40代・50代で冷えが気になる女性
それでは、一緒に体質に合った温活を見つけていきましょう!
季節の不調でお悩みの方へ
季節の変わり目や特有の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
温かいものを食べても冷えが取れない理由とは?
表面だけ温めても内側が冷えている状態
温かい飲み物や食べ物を口にすると、一時的に体がポカポカしますよね。
でも、すぐに手足が冷たくなってしまう…
それは、体の表面だけが温まって、内側まで熱が届いていない状態なんです。
一般的に、体温は内臓などの深部体温と、手足などの末梢体温に分けられるとされています。
深部体温が低いと、いくら表面を温めても、体の芯から冷えている感覚が続くと言われています。
また、血流の巡りが悪いと、温かい血液が全身に行き渡らず、特に手足の先まで熱が届きにくくなります。
だから、温かいものを飲んでも「なんだか冷える…」という状態になってしまうんですね。
体質に合わない温活をしている可能性
「毎日生姜を摂っているのに効果がない」
「温かいものばかり食べているのに変わらない」
そんな風に感じている方、いらっしゃいませんか?
実は、冷え対策は体質によって必要なアプローチが違うんです。
東洋医学では、一人ひとりの体質を見極めて、その人に合った方法を選ぶという考え方があります。
例えば、エネルギー不足の方には「気」を補う食材が良いとされ、血が不足している方には「血」を補う食材が良いとされています。
画一的な温活では、体質に合わないために効果が感じられないこともあるんですね。
消化吸収力が低下している
どんなに良い食材を食べても、消化吸収力が弱っていると体に取り込めないと考えられています。
東洋医学では、消化器系の働きを「脾(ひ)」と呼び、食べ物を「気」や「血」に変える大切な役割があるとされています。
この「脾」の働きが弱まると、食べ物からエネルギーを十分に取り出せなくなると言われているんです。
冷たいものや生ものを食べ過ぎたり、早食いや過食を続けたりすると、胃腸に負担がかかります。
すると、せっかく温かい食事をしても、その栄養を体に活かせない…という状態になってしまうんですね。
東洋医学から見た「冷え」の背景
気・血・水の巡りと冷えの関係
東洋医学では、私たちの体は「気・血・水」の3つの要素で成り立っていると考えられています。
それぞれを簡単に説明すると…
- 気(き): 生命エネルギーのこと。体を動かす力や温める力の源
- 血(けつ): 栄養を運ぶもの。西洋医学の血液と近い概念
- 水(すい): 体液全般のこと。リンパ液や汗なども含まれる
この3つがバランス良く巡っていると、体は健康に保たれると言われています。
逆に、どれかが不足したり、巡りが悪くなったりすると、冷えなどの不調が起こりやすくなるんです。
例えば…
- 気が不足すると、体を温める力が弱まる
- 血が不足すると、栄養が末梢まで届かず手足が冷える
- 水が滞ると、むくみや冷えが起こりやすくなる
冷えの改善には、この「気・血・水」のバランスを整えることが大切だと考えられているんですね。
五臓(特に脾・腎)と体温調節
東洋医学では、内臓を「五臓六腑」と呼び、それぞれに役割があると考えられています。
特に冷えと関係が深いのが、「脾(ひ)」と「腎(じん)」です。
脾(ひ)は、消化器系の働きを指します。
食べ物を「気」や「血」に変換する大切な臓器とされているんです。
脾の働きが弱まると、いくら食べても栄養が体に行き渡らず、エネルギー不足になると言われています。
腎(じん)は、生命エネルギーの源と考えられている臓器です。
体を温める「陽気(ようき)」を蓄える場所とされています。
腎の働きが弱まると、体全体の温める力が低下し、慢性的な冷えにつながると考えられているんですね。
特に自律神経を整えて、妊娠しやすい体へ!女性のための不妊ケアでも解説していますが、ホルモンバランスと腎の関係は深いとされています。
秋の季節特性と冷えの関連性
秋は「肺」の季節と言われ、乾燥の影響を受けやすい時期です。
朝晩の寒暖差が大きくなり、自律神経が乱れやすくなることも特徴なんです。
また、夏の冷房や冷たい飲食物の影響が、秋になって体に表れることもあります。
「夏は平気だったのに、秋になって急に冷えを感じるようになった」
そんな方は、夏の生活習慣が影響している可能性があるんですね。
季節の変わり目に揺らぐ自律神経を整える!五月病予防の東洋医学的アプローチでも解説していますが、季節の変わり目は体調管理が特に大切です。
あなたはどのタイプ?4つの冷え体質チェック
それでは、あなたの冷え体質をチェックしていきましょう!
該当する項目が多いタイプが、あなたの体質の可能性が高いです。
気虚タイプ(エネルギー不足)の特徴
気虚タイプは、エネルギーが不足している状態です。
以下の項目に当てはまるものはありますか?
- 疲れやすく、すぐに横になりたくなる
- 階段を上ると息切れする
- 声が小さい、または話すのが億劫
- 風邪をひきやすい
- 胃腸が弱く、食後に眠くなる
- 汗をかきやすい
- 朝起きるのがつらい
気虚タイプの方は、体を動かすエネルギーそのものが不足しているため、温める力も弱まっていると考えられます。
消化の良い食事で「気」を補うことが大切だとされています。
血虚タイプ(血の不足)の特徴
血虚タイプは、栄養を運ぶ「血」が不足している状態です。
以下の項目に当てはまるものはありますか?
- 顔色が悪い、青白い
- めまいや立ちくらみがよくある
- 髪や肌が乾燥しやすい
- 爪が割れやすい
- 生理の量が少ない、または生理不順
- 眠りが浅く、夢をよく見る
- 目が疲れやすい
血虚タイプの方は、栄養が末梢まで届きにくいため、手足の先が特に冷えやすいと言われています。
鉄分やタンパク質を意識的に摂取することが推奨されています。
陽虚タイプ(温める力の不足)の特徴
陽虚タイプは、体を温める力そのものが不足している状態です。
以下の項目に当てはまるものはありますか?
- 手足だけでなく、お腹や腰も冷える
- とにかく寒がり
- むくみやすい
- トイレが近い(頻尿)
- 下痢しやすい
- 温かい飲み物を好む
- 冬が苦手
陽虚タイプの方は、体全体の温める機能が低下しているため、慢性的な冷えを感じやすいとされています。
温性の食材やスパイスを取り入れることが良いと言われています。
気滞タイプ(気の巡りの滞り)の特徴
気滞タイプは、エネルギーの巡りが滞っている状態です。
以下の項目に当てはまるものはありますか?
- ストレスを感じやすい
- お腹が張りやすい
- イライラしやすい
- のぼせと冷えが混在している
- 肩こりや首こりがある
- 生理前にイライラする(PMS)
- ため息が多い
気滞タイプの方は、エネルギーの流れが滞っているため、熱が偏りやすく、上半身はのぼせるのに下半身は冷える…という状態になりやすいと言われています。
リラックスできる香りの良い食材を取り入れることが推奨されています。
一人ひとりに合わせた季節養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な seasonal care をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
体質別!内側から温まる食材選びと食べ方のコツ
それでは、体質別におすすめの食材と食べ方をご紹介していきますね!
気虚タイプにおすすめの食材と食べ方
気虚タイプの方は、「気」を補う食材を選ぶことが大切だとされています。
おすすめ食材
- 山芋(長芋)
- 鶏肉
- かぼちゃ
- 栗
- もち米
- きのこ類
- さつまいも
食べ方のコツ
- 消化に良い温かい食事を心がける
- 少量ずつ、よく噛んでゆっくり食べる
- 生姜を少量加えると、消化をサポート
- 煮る、蒸すなど優しい調理法を選ぶ
避けたい食べ方
- 冷たいものや生ものの過剰摂取
- 早食い、ながら食べ
- 食べ過ぎ(腹八分目を心がける)
妊活に役立つ栄養素とおすすめ食材ランキング!妊娠しやすい体づくりをサポートでも、エネルギーを補う食材について詳しく解説しています。
血虚タイプにおすすめの食材と食べ方
血虚タイプの方は、「血」を補う食材を意識的に摂取することが良いとされています。
おすすめ食材
- レバー(鶏・豚)
- 赤身肉
- ほうれん草
- 黒ゴマ
- プルーン
- なつめ
- 黒豆
食べ方のコツ
- 鉄分とタンパク質を一緒に摂取
- 温かいスープに赤身肉や緑黄色野菜を入れる
- ビタミンCと一緒に摂ると吸収が良いとされる
- 黒い食材を積極的に取り入れる
避けたい食べ方
- 過度なダイエット
- 栄養バランスの偏り
- 食事を抜くこと
陽虚タイプにおすすめの食材と食べ方
陽虚タイプの方は、体を温める「陽」の食材を選ぶことが推奨されています。
おすすめ食材
- 羊肉
- 鮭
- えび
- にんにく
- にら
- シナモン
- 生姜
食べ方のコツ
- スパイスを活用し、体の内側から温める
- 温かい料理をゆっくり食べる
- スープは具だくさんにして栄養価を高める
- 冬場は特に温性の食材を意識
避けたい食べ方
- 生野菜サラダばかり食べる
- 冷たいデザート
- 南国フルーツの過剰摂取
冷え性改善で体の中から温活!妊活を成功させるためのヒントも参考にしてみてくださいね。
気滞タイプにおすすめの食材と食べ方
気滞タイプの方は、「気」の巡りを良くする香りの良い食材を取り入れることが良いとされています。
おすすめ食材
- 柑橘類(みかん、グレープフルーツ、ゆず)
- 三つ葉
- セロリ
- 大葉
- ジャスミン
- ミント
- 春菊
食べ方のコツ
- 香りを楽しみながらリラックスして食事
- 温かいハーブティーを取り入れる
- ゆっくり深呼吸しながら食べる
- 食事の時間を大切にする
避けたい食べ方
- 早食い、ながら食べ
- 食べ過ぎ
- ストレスを感じながらの食事
すべての体質に共通する大切なポイント
体質に関わらず、すべての方に共通する大切なポイントがあります!
1. 朝食を抜かない
朝食は一日のエネルギー源です。
温かいお粥やスープなど、消化に良いものを食べることが推奨されています。
2. よく噛んでゆっくり食べる
よく噛むことで消化吸収がサポートされると言われています。
一口30回を目安に、ゆっくり味わいましょう。
3. 食事は常温以上で
冷たいものは胃腸を冷やすと考えられています。
飲み物も常温か温かいものを選びましょう。
4. 腹八分目を心がける
食べ過ぎは消化力を低下させると言われています。
「もう少し食べたいな」くらいで止めるのがコツです。
5. 季節の食材を取り入れる
旬の食材は栄養価が高く、その季節に必要な栄養が含まれているとされています。
内側から温まる!体質別おすすめ飲み物・スープ術
体を温める飲み物の選び方
飲み物選びにも、ちょっとしたコツがあるんです!
温度だけでなく、食材の性質も重要
東洋医学では、食材を「温性」「涼性」「平性」に分類します。
体を温めたい時は、温性の食材を選ぶことが良いとされています。
カフェインの摂りすぎに注意
コーヒーや緑茶は体を冷やすと言われることがあります。
飲む場合は、午前中に1〜2杯程度にとどめるのが良いでしょう。
水分補給のタイミング
一度にたくさん飲むのではなく、少しずつこまめに飲むことが推奨されています。
食事中の水分の摂りすぎは、消化液を薄めると考えられているので注意が必要です。
体質別おすすめドリンクレシピ
体質別におすすめの飲み物をご紹介しますね!
気虚タイプにおすすめ
- 生姜紅茶: 紅茶に生姜のスライスを入れて、ほんのり甘みを加える
- 黒豆茶: 黒豆を炒って煮出したお茶。エネルギーを補うとされる
血虚タイプにおすすめ
- なつめとクコの実のお茶: なつめ3個、クコの実10粒をお湯で煮出す。血を補うと言われる
- ほうじ茶: 体を温め、胃腸に優しいとされる
陽虚タイプにおすすめ
- シナモン入りホットミルク: 温めた牛乳にシナモンパウダーを振りかける。体を芯から温めるとされる
- ゆず茶: ゆずジャムをお湯で溶かして。ビタミンCも豊富
気滞タイプにおすすめ
- ジャスミンティー: 香りが気の巡りを良くすると言われる
- ミントティー: リラックス効果が期待され、ストレス緩和に良いとされる
冷えをサポートするスープの作り方
スープは体を温めるのに最適な料理です!
すべての体質におすすめ: 根菜たっぷりの味噌汁
- 大根、にんじん、ごぼうなどの根菜をたっぷり入れる
- 味噌は発酵食品で腸内環境をサポートするとされる
- 具だくさんにすることで栄養バランスが整う
気虚・陽虚タイプにおすすめ: 鶏肉と生姜のスープ
- 鶏もも肉、生姜、長ネギ、にんじんを煮込む
- 鶏肉は「気」を補うとされる
- 生姜は体を温める効果が期待される
血虚タイプにおすすめ: レバーとほうれん草のスープ
- 鶏レバー、ほうれん草、しょうがを煮込む
- 鉄分が豊富で「血」を補うと言われる
- レバーの臭みは牛乳に浸すと軽減される
気滞タイプにおすすめ: 三つ葉と豆腐のスープ
- 豆腐、三つ葉、えのき茸を入れた和風スープ
- 三つ葉の香りが気の巡りをサポートするとされる
- さっぱりしていて食べやすい
食事以外で気をつけたい温活のポイント
食べるタイミングと生活リズム
食事のタイミングも、実は大切なんです!
朝食は7時〜9時がおすすめ
東洋医学では、この時間帯は「胃」の働きが活発になるとされています。
夕食は就寝の3時間前までに
遅い時間の食事は、消化に負担をかけると言われています。
規則正しい食事時間
毎日同じ時間帯に食事をすることで、体内リズムが整いやすくなるとされています。
食べる速度と消化力の関係
「早食いは良くない」とよく言われますが、これには理由があるんです。
よく噛むことで…
- 唾液がたくさん出て、消化をサポート
- 満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ
- 食材の味をしっかり感じられる
一口30回を目安に、ゆっくり味わいながら食べましょう!
避けたい食習慣
冷えを悪化させる可能性のある食習慣をチェックしましょう。
- ながら食べ: スマホを見ながら、テレビを見ながらの食事は消化に良くないとされる
- 夜遅い時間の食事: 胃腸に負担がかかり、睡眠の質も下がると言われる
- 冷たいものの摂りすぎ: 特に朝一番の冷たい飲み物は胃腸を冷やす
- 食べ過ぎ: 消化力を低下させる原因に
- 栄養バランスの偏り: 特定の食材ばかり食べると、体のバランスが崩れやすい
東洋医学の鍼灸で体質改善をサポート
冷えに関連する経絡とツボ
東洋医学では、体には「経絡(けいらく)」というエネルギーの通り道があると考えられています。
特に冷えに関係が深いとされる経絡は…
- 任脈(にんみゃく): 体の前面中央を通る経絡。下腹部の冷えと関連
- 腎経(じんけい): 足の内側を通る経絡。体を温める力と関連
- 脾経(ひけい): 足の内側を通る経絡。消化吸収と関連
これらの経絡上にある重要なツボをご紹介しますね。
関元(かんげん)
- おへその下、指4本分のところ
- 体を温めるツボとして知られる
- セルフケア: 手のひらで優しく温めるように押す
足三里(あしさんり)
- 膝のお皿の下、外側のくぼみから指4本分下
- 消化力をサポートするツボとされる
- セルフケア: 親指で円を描くように押す
三陰交(さんいんこう)
- 内くるぶしの上、指4本分のところ
- 女性の冷えに良いとされるツボ
- セルフケア: ゆっくり3秒押して3秒離すを繰り返す
※セルフケアのツボ押しは、あくまで補助的なケア方法です。効果を保証するものではありません。個人の体質により感じ方には個人差があります。
スタジオシュカでの体質別アプローチ
スタジオシュカでは、一人ひとりの体質に合わせたアプローチでサポートさせていただいています。
初回カウンセリング
- 丁寧な問診で体質を見極めます
- 生活習慣や食事内容もお伺いします
- 舌診や脈診などで体の状態をチェック
体質に合わせた施術プラン
- 気虚タイプには、「気」を補うツボを中心に
- 血虚タイプには、「血」を補うツボを中心に
- 陽虚タイプには、温める力を高めるツボを中心に
- 気滞タイプには、気の巡りを良くするツボを中心に
食事アドバイス
- 体質に合った食材をご提案
- 季節に応じた養生法をお伝え
- 続けやすい方法を一緒に考えます
継続的なサポート
- 体質改善には時間がかかることもあります
- 焦らず、一緒に取り組んでいきましょう
- LINEでのご相談も受け付けています
※個人の体質により体験には個人差があります。施術効果を保証するものではありません。
鍼灸と食事療法の相乗効果
鍼灸と食事療法を組み合わせることで、より良いサポートが期待できると言われています。
鍼灸でできること
- 気・血・水の巡りをサポート
- 内臓の働きをサポート
- 自律神経のバランスをサポート
食事療法でできること
- 体に必要な栄養素を補給
- 体質に合った食材で体を整える
- 日常生活で継続できる
この2つを組み合わせることで、内側と外側の両方からアプローチできるんです!
ただし、体質改善には時間がかかることもあります。
焦らず、継続することが大切だと言われています。
※鍼灸は医療行為の代替ではなく、体質改善をサポートするものです。医療的な診断や治療が必要な場合は、医療機関を受診してください。
専門家と一緒に季節養生を始めませんか?
季節の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた季節養生プランを一緒に考えていきましょう。
まとめ: 自分の体質を知って内側から温まる体へ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
温かいものを食べても冷えが取れない理由、わかっていただけましたでしょうか?
大切なポイントをおさらいしましょう
- 冷えのタイプは人それぞれ。自分の体質を知ることが第一歩
- 気虚・血虚・陽虚・気滞の4タイプで、必要な食材が違う
- 体質に合った食材選びと食べ方で、内側から温まる体づくり
- 食べるタイミング、速度、生活習慣も大切
- 鍼灸と食事療法を組み合わせると、より良いサポートが期待できる
体質改善は、一朝一夕にはいかないこともあります。
でも、毎日の食事を少し意識するだけで、体は少しずつ変わっていくと言われています。
「今日から何か一つでも取り入れてみよう」
そんな気持ちで、できることから始めてみてくださいね!
秋は寒暖差が大きく、体調を崩しやすい季節です。
でも、この時期にしっかり体を整えておくと、これからの冬を元気に過ごせますよ。
もし「自分の体質がよくわからない」「一人では続けられるか不安」という方は、いつでもご相談くださいね。
スタジオシュカでは、あなたの体質に合わせた季節養生を、一緒に考えていきます。
内側から温まる体で、毎日を元気に過ごしましょう!
※個人の体質により体験には個人差があります。効果を保証するものではありません。鍼灸は医療行為の代替ではありません。医療的な診断や治療が必要な場合は、医療機関を受診してください。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
