秋のだるさを翌朝に残さない!帰宅後15分のリフレッシュ習慣【松戸・流山・我孫子から10分の女性の悩み専門の鍼灸】
2025-10-20 季節の養生法
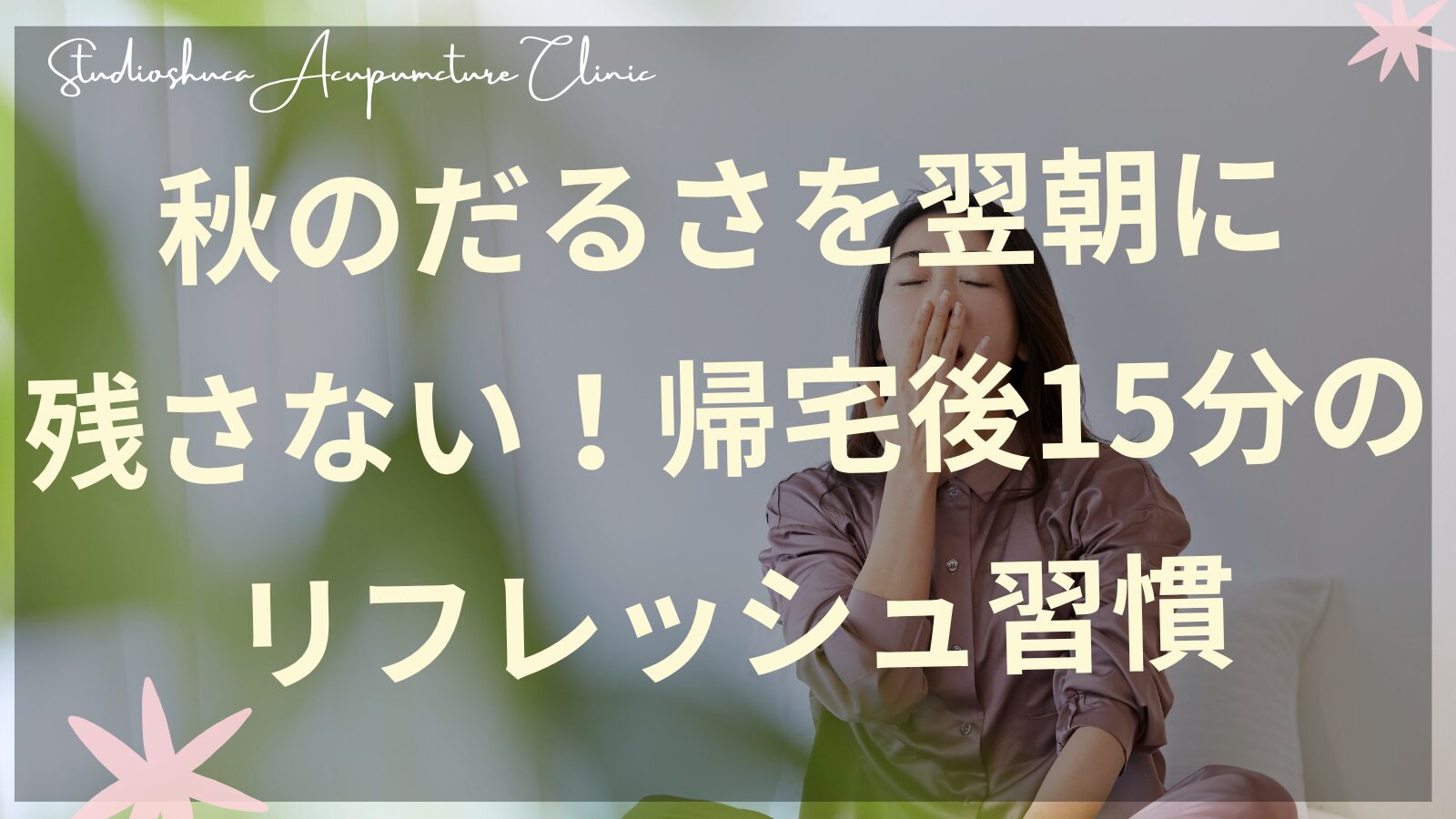
こんにちは!スタジオシュカ鍼灸治療院の宮崎圭太です。
秋になってから、仕事が終わって帰宅するとぐったり…。夕食を作る気力もなく、ソファに座り込んだまま時間が過ぎてしまう。そんな経験はありませんか?
実は、秋特有の「疲れやすさ」には理由があるんです。
東洋医学では、秋は「肺」の季節とされ、気が下降し、乾燥の影響を受けやすい時期です。この季節の特性を理解せずに過ごすと、疲れが抜けにくく、翌朝もだるさを引きずってしまうことがあります。
でも大丈夫です!
帰宅後のたった15分間の過ごし方を変えるだけで、秋の疲れをリセットし、翌朝スッキリ目覚めることができるんです。
このブログでは、東洋医学の知恵に基づいた「帰宅後15分のリフレッシュ習慣」を具体的にご紹介します。
この記事を読むとこんなことがわかります:
- 秋に疲れやすくなる理由(東洋医学的視点)
- 帰宅後15分でできる具体的なリフレッシュ法
- 疲労回復をサポートするツボの押し方
- 翌朝スッキリ目覚めるための夜の過ごし方
この記事はこんな方におすすめです:
- 仕事から帰るとぐったりして何もできない方
- 翌朝も疲れが残っている方
- 秋になってから特に疲れやすくなった方
- 夜の時間を有効に使いたい方
それでは、秋の疲れを翌日に持ち越さないための具体的な方法を見ていきましょう!
秋の不調でお悩みの方へ
秋の疲れや季節の変わり目の不調でお困りではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、季節に負けない体づくりのお手伝いをさせていただいています。
もし東洋医学の季節養生に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
なぜ秋は疲れやすいの?東洋医学から見た秋の特徴
秋になると「なんだか疲れやすい」「体が重い」と感じる方が多いのには、ちゃんと理由があるんです。
東洋医学では、秋は特別な季節として位置づけられています。
秋は「肺」の季節
東洋医学の五行説では、秋は「肺」と深く関わる季節とされています。
肺は呼吸を司るだけでなく、気(エネルギー)を全身に巡らせる大切な働きをしていると考えられているんです。
秋になると、この肺の働きが影響を受けやすくなると言われています。
特に乾燥する秋は、肺にとって負担がかかりやすい時期なんですよ。
気が下降する時期の体の変化
夏の間、体の陽気(活動的なエネルギー)は上に向かって上昇していました。
でも秋になると、この陽気が下に降りていく時期に入ります。
この変化に体がついていけないと、だるさや疲れやすさを感じやすくなるんです。
自律神経も、交感神経優位から副交感神経優位へと切り替わっていく時期で、このバランスの変化が疲労感につながることがあります。
乾燥が体に与える影響
秋は空気が乾燥する季節ですよね。
東洋医学では、乾燥は「燥邪(そうじゃ)」と呼ばれ、体に悪影響を及ぼすと考えられています。
肺は潤いを好む臓器とされているため、乾燥の影響を最も受けやすいんです。
肺の機能が低下すると、気の巡りが滞り、疲れやすくなると言われています。
また、秋は「憂い」という感情と関連があるとされ、なんとなく気分が沈みがちになることも。
こうした心身の変化が重なって、秋は疲れを感じやすい季節なんですね。
日本東洋医学会では、季節と臓器の関係について詳しい情報を提供しています。
秋の疲れを翌日に残さない「帰宅後15分リフレッシュ習慣」
それでは、具体的なリフレッシュ習慣をご紹介していきますね!
この5つのステップを、帰宅後の15分間で実践してみてください。
【ステップ1】玄関で深呼吸3回(1分)
玄関で靴を脱いだら、まず立ったままゆっくりと深呼吸を3回行います。
やり方はとっても簡単です!
- 鼻から4秒かけて息を吸います
- 口から8秒かけてゆっくり息を吐き出します
- これを3回繰り返します
この時、「仕事は終わった」「今日も頑張った」と心の中で唱えながら、気持ちを切り替えましょう。
ゆっくりとした深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になり、リラックスモードに入りやすくなると言われています。
たった1分ですが、この深呼吸が体と心の切り替えスイッチになるんですよ♪
【ステップ2】着替えと同時に体をゆるめる(3分)
部屋着に着替える時間も、無駄にしません!
着替えながら、体を軽く動かして緊張をほぐしていきましょう。
おすすめの動き:
- 肩を大きく後ろに5回、前に5回回す
- 首をゆっくり右に3回、左に3回回す
- 肩甲骨を寄せたり開いたりする動きを10回
特に肩甲骨周りを意識的に動かすことがポイントです。
東洋医学では、肩甲骨周りには「肺経」という経絡が通っていると考えられています。
秋の養生では肺のケアが大切なので、この部分をほぐすことは理にかなっているんです。
デスクワークで凝り固まった体を、ゆっくりとほぐしてあげてくださいね。
【ステップ3】温かい飲み物で内側から温める(3分)
着替えが終わったら、温かい飲み物を準備しましょう。
おすすめの飲み物:
- 白湯
- 生姜湯
- 菊花茶
- 温かいハーブティー
大切なのは、スマホを見ずに、飲み物の温かさや香りに意識を向けることです。
ゆっくりと一口ずつ味わいながら飲んでみてください。
体を内側から温めることで、秋の乾燥から体を守り、リラックス効果も期待できます。
特に生姜湯は体を温める働きがあると言われ、菊花茶は肺の潤いをサポートすると考えられているんですよ。
【ステップ4】簡単なツボ押しで疲労ケア(5分)
温かい飲み物を飲み終わったら、ソファや床に座ってツボ押しタイムです。
疲労回復をサポートするツボを刺激していきましょう。
詳しいツボの位置や押し方は、次のセクションでご紹介しますね!
【ステップ5】今日の「よかったこと」を1つ思い出す(3分)
ツボ押しをしながら、または終わった後に、今日あった「よかったこと」を1つ思い出してみてください。
どんなに小さなことでも構いません。
- お昼のランチが美味しかった
- 同僚が優しい言葉をかけてくれた
- 天気が良くて気持ちよかった
- 仕事でちょっとした成功があった
こんな些細なことでいいんです。
ポジティブな出来事に意識を向けることで、心の疲れもリセットされやすくなります。
これは東洋医学でいう「心(しん)」を整える養生法の一つなんですよ。
一人ひとりに合わせた秋の養生を
体質は人それぞれです。当院では、東洋医学の観点からあなたに最適な秋の養生法をご提案いたします。
季節養生について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
疲労回復をサポートする3つのツボ
それでは、ステップ4で使う3つのツボについて、詳しくご紹介していきますね。
足三里(あしさんり):万能の疲労回復ツボ
位置:膝のお皿の外側、指4本分下にあります。
足三里は、胃腸の働きをサポートすると言われる万能のツボです。
「足の三里を灸すれば健康長寿」という言い伝えがあるほど、昔から大切にされてきたツボなんですよ。
疲労回復だけでなく、消化機能のサポートにも期待されるツボです。
押し方:
- 親指をツボに当てます
- 3秒かけてゆっくり押します
- 3秒かけてゆっくり離します
- これを5回繰り返します
- 左右両方行います
痛気持ちいいくらいの強さがちょうど良いですよ。
湧泉(ゆうせん):生命力を高めるツボ
位置:足裏の中央より少し上、足の指を曲げたときにできるくぼみです。
湧泉という名前は「生命力が湧き出る泉」という意味があるんです。
腎経の重要なツボで、疲れをケアし、元気をサポートすると言われています。
足裏なので少し強めに押しても大丈夫です。
押し方:
- 両手の親指を重ねてツボに当てます
- 体重をかけながら10秒間押します
- ゆっくり力を抜きます
- これを5回繰り返します
- 左右両方行います
お風呂上がりに押すと、より効果的と言われていますよ。
合谷(ごうこく):頭痛・肩こりケアのツボ
位置:手の甲、親指と人差し指の骨が交わる部分にあります。
合谷は「万能のツボ」として知られ、頭痛や肩こりのケアに期待されるツボです。
気の巡りをサポートし、ストレス緩和にも良いと言われています。
手にあるので、いつでもどこでも押せるのが嬉しいですね!
押し方:
- 反対の手の親指と人差し指でツボを挟みます
- 3秒かけて押します
- 3秒かけて離します
- これを10回繰り返します
- 左右両方行います
仕事中でも、ちょっとした休憩時間に押せるのでおすすめです♪
注意事項:
- 妊娠中の方は、一部のツボを避ける必要があるため、専門家に相談してください
- 強く押しすぎないように、「痛気持ちいい」程度の力加減で
- 持病がある方は、医師に相談の上実践してください
- 個人の体質により体験には個人差があります
15分習慣を続けるための実践のコツ
「毎日15分続けるのは大変そう…」と思っていませんか?
大丈夫です!続けるためのコツをお伝えしますね。
完璧を目指さない
まず大切なのは、完璧を目指さないことです。
15分が難しい日は、5分からでも構いません。
できるステップだけやるのもOKです。
「今日は疲れすぎているから、深呼吸とツボ押しだけにしよう」
こんな感じで、柔軟に対応してくださいね。
継続することが何より大切なので、自分に優しくしてあげることが続けるコツなんです。
家族に協力をお願いする
家族と一緒に住んでいる方は、この15分間を邪魔されないようにお願いしましょう。
「帰宅後の15分間は自分の時間にさせてね」
こう伝えるだけで、家族も理解してくれるはずです。
お子さんがいる方は、パートナーに協力をお願いするのも良いですね。
家事の分担を相談するのも一つの方法ですよ。
この時間が、結果的に家族みんなのためになることを、理解してもらいましょう。
自分に合ったアレンジをする
ご紹介した方法は、あくまで基本です。
自分に合ったアレンジを加えて、より楽しく続けられるようにしてくださいね。
アレンジの例:
- 好きな音楽をかけながら実践する
- アロマを焚いてリラックス空間を作る
- 季節に合わせた飲み物を楽しむ
- 照明を少し暗くして落ち着いた雰囲気にする
自分だけの特別な時間にすることで、より続けやすくなりますよ♪
スタジオシュカの秋の養生サポート
セルフケアも大切ですが、一人で続けるのが難しいこともありますよね。
そんな時は、私たちスタジオシュカにお任せください。
東洋医学に基づいた体質診断
スタジオシュカでは、東洋医学に基づいた体質診断を行っています。
脈診、舌診などの伝統的な診断法を用いて、一人ひとりの体質タイプを見極めます。
「なぜ秋に疲れやすいのか」
その理由は、人それぞれ違うんです。
あなたの体質に合わせた、最適なケア方法をご提案させていただきます。
個人差がありますが、多くの方が体質の特徴を知ることで、セルフケアもより効果的になったと感じていらっしゃいます。
一人ひとりに合わせた養生プラン
体質診断の結果をもとに、あなただけの養生プランを一緒に考えていきます。
セルフケアでは届かない部分を、鍼灸施術でサポートさせていただきます。
鍼灸施術では、経絡の流れを整え、気血の巡りをサポートすることが期待されています。
また、食事や生活習慣についても、具体的なアドバイスをさせていただきます。
「こんな小さなことでも聞いていいのかな?」
どんなことでもお気軽にご相談くださいね。
継続しやすい施術スケジュール
働く女性でも通いやすいよう、施術スケジュールは柔軟に対応しています。
松戸・流山・我孫子から10分とアクセスも良好です。
まずはLINE相談で、お気軽にお問い合わせください。
あなたのライフスタイルに合わせた、無理のないペースで続けていけるようサポートいたします。
※個人の体質により体験には個人差があり、施術効果を保証するものではありません。医療行為の代替ではありません。
まとめ:秋のだるさは「帰宅後15分」で変わる
秋は疲れやすい季節ですが、対処法はちゃんとあります。
帰宅後の15分間の過ごし方を変えるだけで、驚くほど体が楽になるんです。
今日からできる5つのステップ:
- 玄関で深呼吸3回
- 着替えながら体をゆるめる
- 温かい飲み物を飲む
- ツボ押しで疲労ケア
- 今日のよかったことを思い出す
この習慣を続けることで、翌朝スッキリ目覚められるようになり、夜の時間も有効に使えるようになります。
休日の疲れも軽減され、予定を楽しめるようになるでしょう。
完璧を目指さず、できる範囲から始めてみてくださいね。
一人で続けるのが難しい場合は、私たちスタジオシュカがサポートいたします。
東洋医学の知恵を活かして、秋の疲れに負けない体づくりを一緒に始めましょう♪
厚生労働省の健康づくりのための睡眠指針でも、質の良い睡眠と疲労回復の関係について詳しく説明されています。
あなたの毎日が、もっと軽やかで心地よいものになりますように。
今日の帰宅後から、ぜひ試してみてくださいね!
専門家と一緒に秋の養生を始めませんか?
秋の養生は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。スタジオシュカ鍼灸治療院で、あなたの体質に合わせた秋の養生プランを一緒に考えていきましょう。
※本記事の内容は、東洋医学の伝統的な考え方に基づいた養生法をご紹介するものです。個人の体質により体験には個人差があり、効果を保証するものではありません。持病のある方や妊娠中の方は、実践前に医師にご相談ください。鍼灸は医療行為の代替ではありません。
季節養生を実践されている方の声もご紹介しております。
